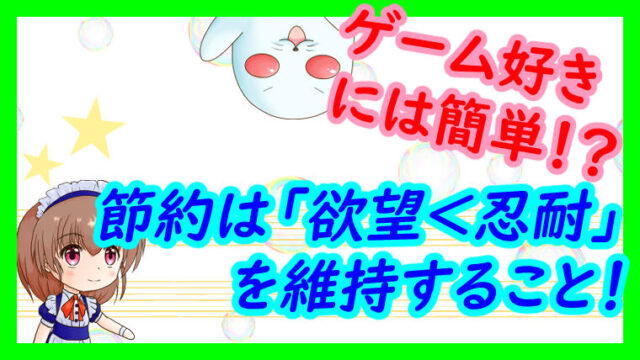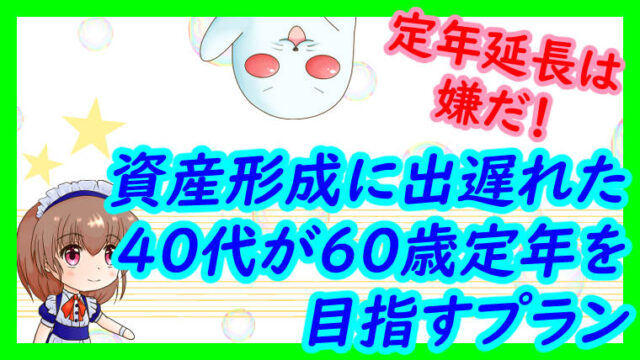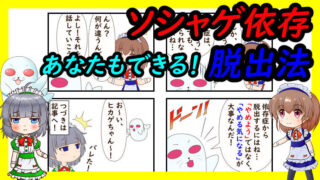老後が不安!
いくら貯蓄すれば老後は安心なの?
老後の目標貯蓄額を達成するにはどうすればいいの?
そもそも目標貯蓄額が無理すぎて現実感ないのだけど…
この記事は、こんな心配・疑問に答える内容になっています!
資産運用の第一歩は、目標を立てること!
でも、目標は現実的でないとやる気もでないですよね?
それは目標立てを失敗しているかもしれないね。無理な目標を立てても、意味はないよ!
夢を見ず、現実的な目標設定をすることが資産運用の第一歩ですね!
- 貯金のみで実施する目標貯蓄額の実現性の確認
- 資産運用を前提とした必要な毎月の貯蓄額
- 節約、配当金で目標貯蓄額は低くできる。
- 資産運用しないのは人生縛りプレイ。しかし、不必要に資産運用でリスクを取る必要はなし。
- 初心者向けの資産運用方法の概要
- 「自分の場合」で目標貯蓄額を考えよう!
- 目標達成のハードルを下げるためには資産運用が鍵!
当ブログは、地味でつまらないけど堅実着実で老後を見据えた長期の投資戦略を前提としています。
要するに短期間で儲けることはできないローリスクローリターンを目指した資産運用になります。よって、誰がやっても差異が出にくい再現性の高い投資方針です。
投資を考える前に目標貯蓄額を思い出そう!
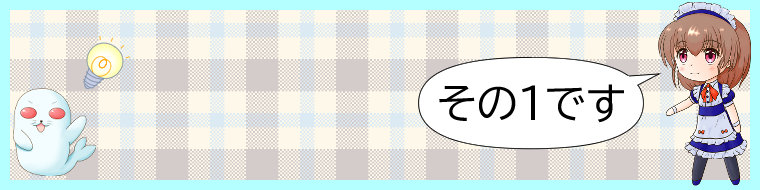
老後のための貯蓄を目標とした場合、その貯蓄額は人それぞれです。そもそも摂生した生活を送るのであれば、それほど貯蓄は必要ないでしょう。貯金がないと心配になってしまう人は貯蓄に余裕を持ちたいでしょう。実情面でも性格面でも目標貯蓄額は変わります。
老後のための目標貯蓄額は「自分ならいくら?」ということを考えるべきです。ネットでよく見かける平均値情報だけを参考にしない方がよいです。
必須になるのは「自分の生活レベルの把握」です。そのために家計簿をつけることは重要です。老後の医療費も加味しつつ、自分の場合の老後のための目標貯蓄額を考えてみましょう。
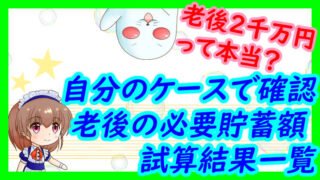
何度も使いまわしてるけど、このブログの方針を再掲するよ。

ローリスクローリターンの資産運用を長期間続けて、堅実着実に経済的自由に近づくためのプランですね。
定年延長は嫌なので、理想的な目標としては60歳時点で「収入>生活費」にすることを目指すよ。
資産運用は長期間続けるほど有利になるから、早くから資産運用を始めた人は60歳まで時間を使わずに経済的自由を獲得できるかもしれませんね!
とはいえ、いきなり理想目標を目指すと目標達成のハードルが高くなってしまうので、まずは寿命まで貯蓄がもつような目標設定を考えようね!
「収入>生活費」とできれば、貯蓄は減らなくなるから、長生きリスクを考える必要はなくなります。貯蓄寿命が無限大になる代わりに、貯蓄目標額は高くなります。
でも、亡くなる時に貯蓄が残っていてもそれは無駄なお金になってしまいますよね?
無駄な貯蓄をなるべくしない、という方針でいくのであれば年々貯蓄が減少していく精神的プレッシャーと引き換えに、老後のための目標貯蓄額を減らすことができます。
たとえば、想定寿命を長めに見ておいて、110歳まで貯蓄がもてばOK、という目標を立てるのもひとつの考えでしょう。
まずは寿命まで貯蓄が底を突かないような目標貯蓄額を達成させることを考えましょう!
60歳で定年するには?
目標貯蓄額を考える上でポイントになる情報は下記でしたね。
- 毎月の出費(生活費、医療費)は?
- 年金の受給額は?
- 退職金は?
- 何歳まで生きる?
- 物価上昇率の想定は?
上記で紹介した記事を参考に自分の場合はいくら必要なのか、おおよその金額を掴みましょう。
参考として、一例を示しておきます。医療費を除いた生活費18万円/月ならけっこう余裕を持ちつつ趣味出費もいけるのではないでしょうか。節約・摂生するならもっと目標貯蓄額は下げられそうですね。
- 現在40歳、生活費18万円/月、医療費1万円/月(74歳まで)、2万円/月(75歳以降)、物価上昇率+0.5%/年
60歳~100歳までの累計支出:116,341,893円 - 年金受給額16万円/月
60歳~100歳までの累計収入:69,120,000円 - 退職金15,000,000円
⇒60歳定年時の目標貯蓄額:32,221,893円(約3200万円)
※貯金のみで老後に備える場合
繰り返しになりますが、前提条件次第で目標貯蓄額の計算結果は大きく変わります。自分の老後の生活前提を考えながら、目標貯蓄額を定めましょう。
上記の一例では「3200万円」となっていますが、節約・摂生した生活を送るならば、目標貯蓄額が2000万円以下の計算結果にだってなります。
年金16万円/月、医療費除いて生活費18万円/月で、目標貯蓄額3200万円ですか…
結局、肝になるのは、毎月いくら赤字なのか?だね。医療費以外で毎月2万円の赤字なら、想定寿命100歳で目標貯蓄額3200万円って試算だね。
節約したり、投資で配当金を得られるようになれば、目標貯蓄額は下げられますね!
そういうこと!たとえば生活費を2万円圧縮すると、目標貯蓄額は2000万円って試算になるね。
月2万円の差で1200万円も目標貯蓄額が変わるんですね…
物価上昇率や医療費は仮のものだから絶対ではないけどね。
なんにせよ、早くから老後に向けた取り組みをすれば老後リスクはだいぶ減らせそうですね!
いくらあれば安心できる?
計算で求めた老後の目標貯蓄額は、数字で見えるのである程度は理論的で明確です。
しかし、理論的に目標貯蓄額を計算できたとしても、寿命や医療費、物価上昇率など「仮に想定している」部分があるので、絶対に信用できる目標貯蓄額というわけではありません。
この「絶対ではない」という事に対して、人間には厄介な問題があります。それは「感情」です。
言ってしまえば性格次第であって、仮に目標貯蓄額を達成したとしても、人によっては不安になってしまうのです。
「もしも想定外の何かが起きたら…」という心配事を抱える限り、不安は尽きません。人間、分からないことには不安になるものです。
不安の根本にあるのは「分からない」ということです。「分からない」をなくすために学ぶ事は心配を消して安心につながります。しかし、いくら学んでもどうにもならない問題もあります。
学び続けてもどうしようもないと私が考えることは2点あります。
- 寿命やいつ病気になるかなどが分からない(未来情報は入手不能)
- とにかく赤字が嫌いなど(信念・性格的な問題)
①寿命やいつ病気になるかなどが分からない(未来情報は入手不能)
寿命、病気になる時期、物価上昇率、年金受給額の変化などは学んで分かることではないのでお手上げですね。この解決方法は、寿命などの想定地に安全マージンを取る事でしょうか。
例えば、100歳までの生活に必要な貯蓄があれば十分にも思えますが、100歳までなら生きられる可能性は否定できませんね。それならば、110歳まで生きる前提で貯蓄するか。
こういう安全マージンを確保することがひとつの解決策でしょう。その貯蓄は無駄になる可能性が高いですが、そこは安心を買うための代金と思うしかないですね。
「分からない」を「分かる」にすれば、正確な予測ができるし、目標貯蓄額の試算も信頼性が増すのに…
神様でもない限り、すべてを見通すことはできないね…「分からない」という恐怖から完全に逃げることはできないんだよ。
せっかく目標貯蓄額を計算しても、分からない恐怖を押さえるためにどれだけ安全余裕代を取るか、という議論になってしまいそうです。
安全余裕代を取りすぎて目標貯蓄額が膨れて現実的な数字じゃなくなっても意味はないんだけどね。
どの程度の余裕で安心できるのかは各自の性格によるところが大きいから、結局、自分が納得できる数字を各自で模索するしかないね。
②とにかく赤字が嫌いなど(信念・性格的な問題)
分からないことに対する不安であれば、学ぶことにより理論理屈で納得できれば不安を解消できるかもしれません。しかし、信念や性格的な問題となると如何ともしがたいです。理論理屈で覆しがたい領域ですからね。
「とにかく赤字が嫌い」というのは信念の一例ですが、こういう人は老後の年金以外の収入源を確保して、「収入>支出」を維持する努力も必要ですね。
結局は自分が納得できるように目標貯蓄額を調整するしかないのです。
まあ、私自身が赤字が嫌いなタイプなんだけどね…
このブログでの理想的な目標設定も「収入>生活費」で経済的自由を獲得することですもんねw
お金に対する心配が完全になくなるのは、精神的にかなりの解放気分になると思う!
老後にやる事が完全になくなっちゃうのも苦しそうだし、好きでやれる仕事を持てるならば老後の労働収入を検討するのもありかもしれませんね。
定年後は悠々自適に過ごしたいんだー!
本気で何もしなくなったら、ボケるの早くなりそうですよ…老後も何かやりたいことは考えておきましょう!
私は経済的自由を獲得するために不労所得の積み上げを狙っています。手段としては、高配当ETFなどでの配当金・分配金収入です。
しかし、もしも定年後も続けられる好きな仕事ができるのであれば、定年後も労働収入ありきで考えるのもよいと思います。
手段はなんであれ、結果として老後の貯蓄額の目減りに恐怖しなければ問題ありませんからね!
目標貯蓄額は現実的かチェックしよう!
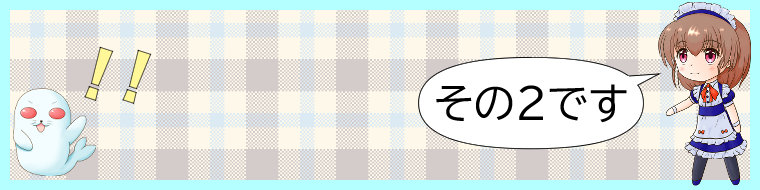
自分の場合の老後に向けた目標貯蓄設定額は分かりましたか?
さて、設定した目標貯蓄額を実際に貯めることができるのかどうか?そこが次の論点です。
単純に貯金だけで貯めようと思うならば、「目標貯蓄額/定年までの時間」で毎月の貯蓄額を計算することができます。その数字は実際に貯蓄できると思える金額でしょうか?
資産運用・投資をしないのは人生縛りプレイ、でしたよね?
資産運用・投資はリスクを伴うから、必要ないなら貯金のみで老後に備えるという選択肢はありだとは思うよ。
目標貯蓄額を達成できない、と思ったら、資産運用や投資を検討ですね!
- 目標貯蓄額まであと3200万円:毎月13.3万円の貯蓄が必要
- 目標貯蓄額まであと2000万円:毎月8.3万円の貯蓄が必要
- 目標貯蓄額まであと1000万円:毎月4.2万円の貯蓄が必要
この例では、現時点の貯蓄額と老後のための目標貯蓄額の差額が残りの必要貯蓄額ですね。目標貯蓄額が3200万円で、現在1200万円の貯蓄ができているのであれば、定年まで残り20年として毎月8.3万円の貯蓄が必要です。
自分の場合はどうなるのかで計算してみてください。毎月の目標貯蓄額に現実味を感じることができないのであれば、対策が必要です。そう、投資と節約の出番です!
40歳からの20年間で老後に備える前提だと、毎月の貯蓄額がかなり厳しいですね…
独身の前提なら、毎月の貯蓄額も結構高めにできるとは思うけど、現時点で貯蓄ゼロだと確かに厳しいね。
節約で生活費を抑えれば目標貯蓄額は下げられるとして…
それでも厳しいならば、いよいよ資産運用・投資の出番だ!
複利の力で毎月の投資額を安くできる!
資産運用することで複利の力の大きさを実感することができます!銀行の預金では利率が低すぎて複利の力を実感できるようなものではないのですよね。資産運用にはリスクを伴いますが、長期運用で投資先を間違わなければ、長期の平均で年利3~5%くらいは出せるかと思います。
「複利の力」とは何なのか?簡単にいうと、年利によるお金の増え方が加速する現象のことです。理解するには数字を使ってみてみた方が手っ取り早いですね。
- 1年目:100万円+5万円=105万円
- 2年目:105万円+5.25万円=110.25万円
- 3年目:110.25万円+5.51万円=115.76万円
- 5年目:121.55万円+6.08万円=127.63万円
- 10年目:155.13万円+7.76万円=162.89万円
5%増えた後のお金に対して翌年はさらに5%増える、という流れになります。そのため、年々お金の増え方が加速するんですね。これが複利の力です。
お金の自己増殖機能!
貯金や定期預金でも自己増殖するのだけど、年利が低すぎて恩恵を感じられなんだよね…
その代わり、貯金や定期預金は元金が失われるようなリスクが(ほぼ)ないですけどね。
リスクを受け入れることで、福利の力を利用できるって感じだね!
複利の力を利用すると、「毎年100万円(毎月8.33万円)×20年=2000万円」という計算にはなりません!結果的に毎月の貯蓄額を抑えることができるわけですね。
自分が設定した目標貯蓄額を達成するために、「毎月いくらを資産運用に回せば、何年後にいくらになるのか?」というシミュレーションは金融庁のホームページにある資産運用シミュレーションを利用すると良いでしょう。
毎月8.33万円を資産運用した場合のグラフを見てみよう!
複利の効果を見るために、運用利回りでの違いを確認ですね!
ちなみに「0%」は資産運用せず、貯金のみの場合と思ってもらえればいいよ。

資産運用の利回りはどういう商品に投資するかによって変わりますが、税金も考慮して悲観的に3%くらいで見ておくのが無難かもしれません。もっと高い利率を狙うならば、それだけリスクの高い商品に投資をする必要が出てきます。
複利の力ってすごい…これがお金の自己増殖機能!
どれだけリスクを取るかは人それぞれだけど、個人的には3~5%くらいで見込んでるかな。
リスクとリターンは表裏一体でしたね。
ローリスクローリターン!ハイリスクハイリターン!これは変えられない真理。
老後のための資産は失うわけにいかないですから、ローリスクで考えないといけませんね。
実際に資産運用をした場合、毎月の貯蓄額がどのくらい変化するのか資産運用シミュレーションで計算した結果を載せておきます。
- 毎月8.33万円を20年、通常の貯金をし続けた場合(年利0%で計算)
⇒19,992,000円の貯蓄になる。 - 毎月6.1万円を20年、年利3%で資産運用した場合
⇒20,026,422円の貯蓄になる。 - 毎月4.9万円を20年、年利5%で資産運用した場合
⇒20,140,650円の貯蓄になる。
20年ともなると複利の力の強さをかなり実感できる数字になります。
ちょっと弱気に見て年利3%とすると、「資産運用なしなら毎月8.33万円貯蓄」が必要なところ「資産運用ありなら毎月6.1万円貯蓄貯蓄」で済むわけですね!
配当金で資産寿命を向上させる!理想目標へ!
複利の力を100%活かすのであれば、投資によって得られる配当金はすべて再投資した方がよいです。
たとえば、100万円を5%で運用したとして、翌年に得た5万円を投資に回さない場合は、翌年も得られる利益は5万円にしかなりません。老後に向けた貯蓄を目標にするのであれば、基本的に得られた利益は再投資です。
しかし、すべてを再投資に回さず、配当金という形で収入を得る方法もあります。配当金は不労所得です。老後の年金に追加される収入源にもなりえます。
収入が増えれば、老後の毎月の赤字が減りますよね。結果的に、資産の減り方が遅くなるので資産寿命が長くなります。
そして、あわよくば、「収入>支出」とすることができれば、資産寿命は永遠です!
ここからは理想的な目標である資産寿命無限大についてです。
年金+配当金で資産寿命を永遠に近づけるのは私自身が目標としているスタイル!
このブログで理想目標としていますね。
定年までは配当金をできるだけ再投資。定年後は配当金を収入として利用するのがいいかな。
配当金で老後の収入を増やせるなら、そもそも目標貯蓄額もさらに下げられますね。
その通り!それがまさに「貯蓄寿命を向上させる」ことにつながるんだよ!
何度も伝えてきた通り、「年金+配当金>生活費」とできれば、貯蓄寿命は無限大です。
老後のための目標貯蓄額の一例をもう一度見てみましょう。
- 現在40歳、生活費18万円/月、医療費1万円/月(74歳まで)、2万円/月(75歳以降)、物価上昇率+0.5%/年
60歳~100歳までの累計支出:116,341,893円 - 年金受給額16万円/月
60歳~100歳までの累計収入:69,120,000円 - 退職金15,000,000円
⇒60歳定年時の目標貯蓄額:32,221,893円(約3200万円)
※貯金のみで老後に備える場合
この例では配当金による収入は考慮してませんでしたね。では、配当金が6万円/月あったとしたらどうなるでしょうか?
- 現在40歳、生活費18万円/月、医療費1万円/月(74歳まで)、2万円/月(75歳以降)、物価上昇率+0.5%/年
60歳~100歳までの累計支出:116,341,893円 - 年金受給額16万円/月+配当金6万円/月
60歳~100歳までの累計収入:98,640,000円 - 退職金15,000,000円
⇒60歳定年時の目標貯蓄額:3,087,095円(約300万円)
配当金なしだと目標貯蓄額3200万円としいたところが、配当金ありだと目標貯蓄額300万円になりました。
そもそも、この計算前提として、物価が上昇しても年金受給額も配当金も据え置きとしているので、割と安全をみた試算です。年金にしても配当金(株式資産)にしてもインフレへ追従してくれることを見込んでもよいでしょう。
インフレ(物価上昇)に対して、年金や配当金が追従するのであれば、現在の価格価値で「年金+配当金>生活費+医療費」となっていれば、ひとまずは安心域に入っているとも考えられます。
- 年金:16万円/月
- 配当金:6万円/月
- 生活費:18万円/月
- 医療費:2万円/月
⇒「収入>支出」で余裕が見えるライン!
資産をすべてリスク資産(投資などによる資産運用)で持っておくのは非常に危険ですので、配当金6万円/月を得るための資産とは別に現金(貯金)を持っておくとよいでしょう。
リスク資産(配当金を得るための資産)と安定資産(自由にいつでも取り出せる貯金)は分けて考えておきましょう。
ここでいつもの画像を再掲!

「配当金を得るための資産」といつでも使えるリスクがない「緊急用資産(安定資産)」は別に用意するんだ!
例えば、配当金を6万円/月として、「配当金を得るための資産」はいくら必要なんですか?
投資先にもよるけど、高配当ETFとかを利用して税引き後で考えて、悲観想定として配当を年2%くらいで考えてるかな。
6万円/月=72万円/年ですから、配当2%で考えるなら3600万円必要な計算ですね。
そして「配当金を得るための資産」とは別に「緊急用資産」の用意だけど、年金受給ができない期間(60歳~64歳)の生活費以上は確保しておかないといけないね。
60歳~64歳は年金なしだし、配当金と退職金で過ごす事になるから、毎月の赤字が出ますもんね。
「生活費:18万円/月、医療費:1万円/月、配当金:6万円/月」この仮定で計算すると…
毎月13万円の赤字…5年間で780万円ですね。退職金でカバーできそう?
そうだね。だから「緊急用資産」は個人でどのくらいもっていれば安心できるか、によるところが大きいかな?
とりあえず、物価上昇に対する収入を悲観的に見て試算した「300万円」は最低限として…将来の突発出費とかも考えてキリよく「1000万円」とか?
まあ、人それぞれということで、今話した前提だと「配当金用資産:3600万円」「緊急用資産:1000万円」で合計4600万円以上が60歳時点であれば、経済的自由といえそうかな?(※金額は2021年現在価値とする)
独身の前提なら、生活費18万円/月はもう少し落とせそうですけどね。もう一声ハードル落とせそうな気もしますね。
医療費とか為替リスクとか金融資産の暴落とかいろいろあるから、マージンはなるべく残したい…
心配しすぎも目標が現実離れしていくって言ってたじゃないですか!w
節約は、毎月の貯蓄額アップと目標貯蓄額削減のダブル効果!
目標貯蓄額到達のための毎月の貯蓄額を捻出するのが厳しい!という人もいるでしょうか。
そうした人は、まずは毎月の出費を抑えることを考えることをオススメします。目標貯蓄額に現実味がないという人は、今の生活スタイルを老後も続けるのは難しくなるでしょう。
今のうちに節約生活に慣れるということは、老後の生活費の低下(目標貯蓄額を下げられる)とともに、毎月の貯蓄に回せる金額が増やせるということです!
現実味のない老後の目標貯蓄額が現実味を帯びるレベルにすることができる、それが節約です!
もちろん、節約ではなく収入を増やすという手段でも、目標貯蓄額達成へ近づくことができます。しかし、収入を増やす努力よりも節約して支出を減らす努力の方が楽なはずです。
私は年間200万円以上貯蓄を達成できています。何をして何をしていないのか?節約についても別途の記事で詳しく説明しようと思います。
収入を増やすには自ら動くことが必要!節約をするには動かなければよい!
結構暴論ですねw たしかに、何もしなければお金も使わずに済みますが…
動くよりも動かない方が楽だからね~。そういう節約は割と取っつきやすいとは思うかな?
でも、何もしないなんてつまらないですよ!
まあ真面目にいうと、生活レベルや生活スタイルを変えずにできる節約から入る方がよいよね。
そこのお話はまた今度の機会ですね!
- 複利の力を利用すれば、毎月の貯蓄額を低くできる。
- それでも毎月の貯蓄額が厳しい金額ならば、生活費節約により目標貯蓄額を見直す。
- 老後の収入源を増やす方法として、配当金を得るという手段もある。
目標達成の投資戦略とは?
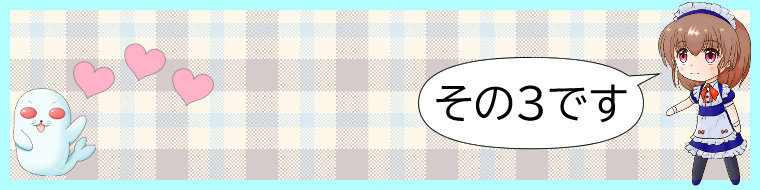
複利の力を活用するために、資産運用、つまり投資が必須です。私がオススメするのは年利3~5%程度の期待での資産運用です。高利率な金融商品は基本的にハイリスクです。
資産運用でお金を得るためにリスクを取る事は必要ですが、必要以上のリスクを取らないようにしましょう。もしも高利率で運用しないと目標貯蓄額に到達できないようであれば、目標貯蓄額の方を見直すことをオススメします。
年利3~5%くらいであれば、比較的ローリスクローリターンの金融商品で達成できる見込みがあります。むしろ、3~5%というのは少し弱気かもしれませんが、将来何があるか分からないので利率の数字は弱気寄りの前提で構えておいた方がよいでしょう。
私がオススメする投資戦略はインデックス投資と高配当ETFです。それぞれ簡単に見てみましょう。詳しくは別途の記事で説明をします。
この記事では軽く触れるだけにとどめるよ。
しっかり説明していくと、かなり長くなるところですもんね。
インデックス投資
インデックスというのは、日経平均株価や東証株価指数、S&P500などのことです。ひとことでいうと、ある市場を表す数字です。特定の株価の平均値などで数字が作られます。
インデックスで表されている数字は多数の株価などで構成されていて、インデックス投資というのはそのインデックス(指数)に連動するように作られた金融商品に投資することです。
噛み砕いてひとことでいうと、日本全体に投資する、米国全体に投資する、といった幅広い範囲に簡単に投資できるがインデックス投資です。
特定の会社に集中投資するスタイルとは真逆で、広く薄く投資することになるので、個別株投資に比べると基本的に値動きは落ち着いています。
初心者がまず資産運用を始めるならば、インデックス投資をやってくれる投資信託(インデックスファンド)に任せるのがよいでしょう。
- 幅広い範囲に投資されるため、比較的安定した利回りが期待できる。
※ファンドにもよるので商品選びは注意が必要! - 信託報酬などのお金がかかる(その分、実利回りは下がる)。
- 100円からの少額投資が可能なため、初心者でも始めやすい。
- 定期定額の自動積立が可能。
- 配当金を自動で再投資にすることができる。
インデックス投資については詳しい記事がいっぱい出回っているので、詳細説明は他サイトにゆだねるよ!
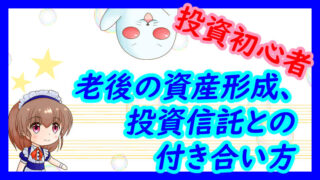
高配当ETF
ETFは上場されている投資信託のことです。投資信託に○○円投資する、というものではなく、株と同じような感覚で、現在○○円のETFを○口購入する、という購入方法になります。
そのため、ふつうの投資信託のように少額からの投資はできません。最低投資額は現在のETFの価格と最低購入口数によります。
また、株と同じようにETFも持っているだけで配当金がもらえるものがあります。その配当利回りがよいETFを高配当ETFと呼んでいます。高配当ETFは、ETF自体の値上がりも期待しつつ、配当ももらえる、という金融商品です。
配当としてお金を受け取る分、利率の関係で複利の力は弱くなってしまいますが、ある程度の利益確定は逐次しておきたい、老後の前から受け取れる収入を増やしたい、老後もなるべく貯蓄を切り崩さずに生活したい、という人にとっては、配当金を受け取れるのは魅力的でしょう。
もちろん、受け取った配当金を再投資することもできます。ただ、配当金を受け取る時に税金がかかるので、配当金を受け取ってからの再投資は税金分は損してしまいます。
ETFは投資信託への投資に比べると投資額も大きくなりやすく若干ハードルが高いです。初心者の一歩目としてはオススメしません。投資になれてきたら、ETFにも挑戦という位置付けで考えておきましょう。
- ETFも種類が豊富にあるため、購入するETFには注意が必要。
- 配当金という形で収入を増やすことができる。
- 配当金を再投資しない場合は、その分、複利の力は弱まってしまう。
※配当金で受け取った分には税金がかかるので再投資するにも税金分は損になる。 - 貯蓄額が増えるにしたがって配当金も増えるので、時間が経つほど生活が楽になることを実感できる。
- 投資信託と違い、投資にはある程度まとまったお金が必要。
- 信託報酬などの費用がかかる(その分、実利回りは下がる)。

まとめ
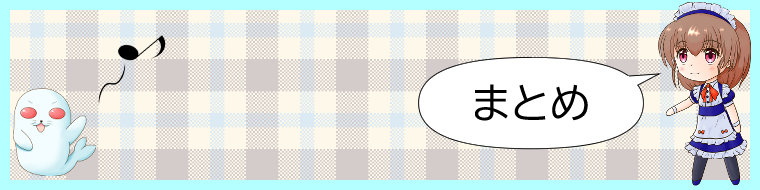
老後に向けた目標貯蓄額の確認とその目標達成の道筋についてお伝えしました。
今回の記事では、投資部分に関しては簡単な紹介に留めましたので、別の記事でもう少し掘り下げて説明をしていきます。
- 現実的な目標貯蓄額の確認
- 目標貯蓄額達成のための毎月の貯蓄額の確認
- 毎月の貯蓄額に現実味がない場合は節約などを考慮して目標を見直す
- 複利の力を活かすには資産運用・投資が必要
- 初心者でも始めやすいのは、インデックスファンドへの投資
- 高配当ETFで配当収入を得る方法もある
私の基本方針は、ローリスクローリターンで気長な長期運用です!
再現性が高く、堅実着実なコツコツ投資・資産運用を求めるならば、今後の記事も参考になると思います!
老後のための資産形成はギャンブルするのではなく堅実着実に積み上げていくことをお勧めしますよ。
定年の年齢に近づくほど、ハイリスクハイリターンの投資には注意だよ!
仮に60歳定年を目指すなら、40歳くらいからそろそろリスクを抑えていきたいところですね。
資産運用・投資は自己責任です!
インデックス投資にしても高配当ETFにしても、商品選びは非常に重要です!また、どの商品を選ぶにしてもリスク商品であることは変わりません。
リスクを認識した上で、自分自身で商品に納得した上で投資をするようにしましょう!
むしろ、よく分からないうちは、まだ学びの時です。分からずに購入するのは絶対にやめましょう!