「老後に向けて投資が大事っていうけど不安…」
「投資信託なら安心って本当?」
「投資信託っていっても何に投資したらいいのか分からないよ…」
そんな人に向けて、実際に初心者から一歩を踏み出して投資を始めた時の経験から、初心者でも比較的安心して投資信託と付き合えるポイントを説明します!
- 投資信託は最初に投資の設定をすれば、あとは放っておいても大丈夫!
- 投資信託の選択を間違わなければ、長期的にはローリスクローリターンを達成しやすい。
- 投資信託は少額から投資が可能なため、少しずつ投資に慣れていくことができる。
- 投資信託は投資のプロが運用してくれるので、投資に対する知識が薄くても大丈夫。
- 投資には元本割れのリスクがある。元本保証されない代わりに、預金よりも大きいリターンが期待できる。
- 投資信託の特性を理解した上で、老後のための資産形成のための投資信託との付き合い方の一例を考える。
基本的には完全に初心者であった私の経験から、初心者にやさしい投資信託との付き合い方を説明するよ!
投資信託については、いろいろなサイトで詳しい説明があります。そのため、この記事での投資信託の説明は初心者が感覚をつかむ程度にしていますよ。
とはいえ、投資信託に対する最低限の知識は持つべきなので、説明パートもちょっと長いです。
とにかく実際に投資をするとなったら、大事なのは投資との付き合い方だよ!
投資信託についてかんたんに学んだあとは、初心者でもかんたんに実践できる投資との付き合い方を見ていきましょう!
ちなみに、このブログでは老後の資産形成を目標とした投資を考えているよ。短期間で大きくもうける投資ではないよ。
要するに、長期視点で堅実安定で誰でも同じような成果を出しやすいローリスクローリターンを目指した付き合い方ですね。
投資信託ってどういうもの?
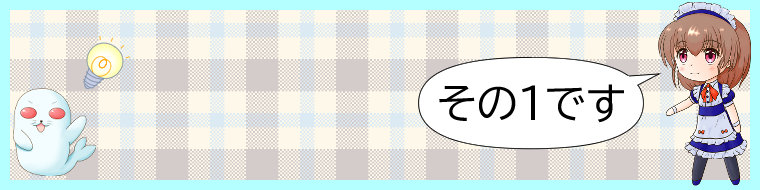
投資そのものは、証券会社で証券口座を開けば自分で株などを購入できます。しかし、投資初心者が投資すべき会社を選定して株を購入するのはハードルが高いです。
そこで登場するのが投資信託というわけです!
投資信託(ファンド)にお金を預けることによって、ファンドマネージャー(資産運用のプロ)が自分の代わりに投資をしてくれます。
預けたお金をファンドマネージャーがどのように資産運用してくれるのかは、投資信託(ファンド)によってことなります。よって、お金を預ける投資信託(ファンド)選びは重要です。
投資先の会社を選定しなくてもよいといっても、結局、投資信託の選定は必要なんですね…
投資する会社をひとつずつ選定するよりも、投資信託をひとつ選定する方がずっと楽だし、投資した後の管理も楽なんだ。
話が脱線しそうなので、それについてはまたあとで聞きますね?
うん。では話を戻して、投資信託へお金を預ける(投資する)イメージを図解するよ。

投資信託について詳細を調べようと思えばいろいろと情報が出てきますが、必ずしも詳細まで把握せずとも投資信託を利用すること自体に問題はありません。
ただし、繰り返しになりますが、投資信託を利用するにあたり、「その投資信託がどのような資産運用・投資をするのか?」というポイントは非常に大事なので、ここだけは見極めが必要です。
投資信託に任せれば資産運用を丸投げできるってことですね!
株の売買や投資先のバランス調整とか、資産運用の難しいところをプロに任せられるのは非常に楽ちん!
手数料を取られてしまうのは残念ですが、それだけの仕事を代わりにやってくれるのだから必要経費と考えましょう。
私が投資を始めた当初、「手数料を取られるくらいなら自分で投資・運用する!」と考えて、最初から自分で個別株などの売買をはじめました。
しかし、これが非常に手間!
「投資をガッツリやろう」と考えている人は問題ないでしょう。むしろ投資経験を積むためにも株売買に手間をかけることは悪くないです。
一方で「投資に時間を割く余裕はない」「長期的にローリスクローリターンで運用できればよい」と考える人が、投資に大きな労力・時間を割くのは目的からズレてしまっているかもしれませんね。
時間は有限です。投資信託は資産運用をするにあたり時間短縮になります。自分の目的にあった投資スタイルを選びましょう。
どうして初心者には投資信託がオススメなの?
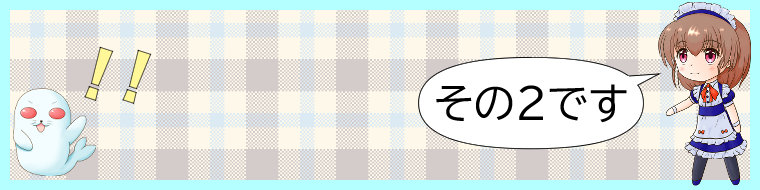
「投資信託がどういうのもなのか?」なんとなくつかめたところで、次は「投資信託が初心者にオススメできるのはなぜか?」をお伝えしていきます。
- 少額から投資できる。
- 金額を決めて投資できる。
- 価格変動に振り回されにくい。
- 定期定額購入ができる。(時間分散、ドルコスト平均法)
- 一度設定したら放っておくだけでもOK。
- 投資先をかんたんに分散できる。
- 投資比率は自動的に調整される。
- 海外への投資もかんたん。
- 自動的に再投資をしてくれる。
初心者にとっての投資信託の利点をまとめると、いろいろあるんですね!
ひとことで言ってしまえば、「細かいことを考えなくてよくなる」というのが初心者にとっての利点だね!
投資信託のくわしい説明は他サイトに任せるとして、利点についてかんたんに触れておきましょう!
かんたんに…とはいえ、ちょっとした長さです。
投資は自己責任です。自分が投資するものについて、最低限は把握しておきましょう。
少額から投資できる
個別株やETFなど、通常は購入単位が決められています。
国内で個別株を買おうとしたら基本的には100株単位での購入しかできません。1株500円の個別株を購入しようとしたら、5万円の投資が必要ということですね。
投資信託の場合は、購入単位や標準価額(株価みたいなもの)に関わらず、100円からの投資が可能です。
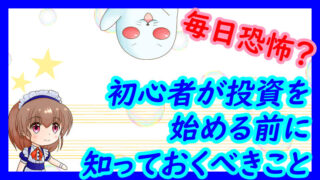
初心者のうちは投資先の価格変動で受ける精神的ダメージに耐えられなくなることもあるよ。
少額投資なら、価値が暴落しても受けるダメージも小さくて済みますね!
初心者は投資に慣れる期間も考えた方がいいよ。
最初は少額投資から!慣れてきたら投資額アップ!
個別株の売買タイミングが絡むと、さらに日中は株価変動が気になってしまったりするよ!
投資をはじめた結果、日常生活に影響が出るようだと問題ですね…
日中に価格変動することがない投資信託はそういう意味では安心だね。
そもそも老後を見据えた長期投資なら、一日の価格変動すら気にする意味がないような…
頭でそう思っていても、心がついていかないのが初心者あるあるだよ。投資信託を少額からはじめるのはいろいろな点で精神的に優しい方法だよ。
金額を決めて投資できる
投資信託には「1口○○円」という価格が設定されています。
1口というのが購入単位で、○○円というのが標準価額と呼ばれる1口あたりの値段です。
しかし、投資信託に投資する場合は1口単位の投資でなくてもOKです!
たとえば、標準価額1万円の投資信託に1000円投資する場合は、0.1口購入、という形になります。
購入単位を無視できるのはありがたいですね!
積立感覚で投資できるね!
価格変動に振り回されにくい
投資信託の価値(評価額)は「標準価額」で決められています。株でいうところの「株価」と同じです。
株の取引時間中、株価は時々刻々と価格が変動します。しかし、標準価額は一日一回更新されるだけです。そのため、日中の変動に心が振り回されなくて済みます。
投資した後、損してるのか得しているのか、すごく気になってしまうのは初心者あるあるだよ…
株価の変動が気になって、他のことに集中できなくなる、なんてこともたまに聞きますね。
長期的な意味で「価格変動に振り回されない」という点については、次の「時間分散、ドルコスト平均法」を参照です。
定期定額購入ができる(時間分散、ドルコスト平均法)
投資信託は「毎月○○円」という定期定額投資の設定ができます。そのため、一度設定してしまえば毎月積立と同じような感覚で投資ができます。
この「毎月定額」という投資の仕方は、「時間分散(ドルコスト平均法)」と呼ばれる分散方法にあたります。分散というのはリスク低減のための投資手法です。
株価(投資信託の場合は「標準価額」)は変動するものです。そのため、投資タイミングによっては「高い時に投資してしまった、安い時に投資できた」というような損得が発生します。
「毎月定額」による投資は、投資タイミングを毎月にすることによって、平均的に考えると「高くもなく安くもない平均的な価格」で投資できる、というものです。
大きく損をしない代わりに、大きく得もしない、というまさにリスク低減の投資手法です。
言葉だけだと理解が難しいと思う!もう少ししっかりと理解したい人はこちらの記事の「ドルコスト平均法」の項目を読んでみてね!
ブログ内の「もくじ」のところから一発で飛べますよ~。
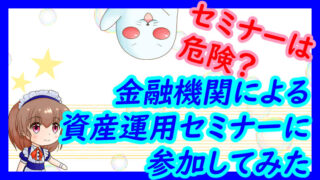
一度設定したら放っておくだけでもOK
前項の「定期定額購入ができる」というもうひとつのメリットとしては、一度「毎月○○円投資」という積立投資設定をしてしまえば、後は放っておいてもOKです。
投資信託にお金を預けてしまえば、あとは投資のプロが適切に資産運用してくれます!この恩恵を受けるために投資信託に手数料を払っているのです!
投資を始める最初の一歩だけは手間がかかりますが、その後はまさに手間いらず!
初心者にとっては、これが一番ありがたいかもしれませんね!
まあ、本当に放っておいてよいのは信用できる投資信託を選んでいる時だけどね…
こわいことを言いますね…ですが、罠のような投資信託があるのもまた事実…
無難な投資信託の選び方はまたあとで話をするよ!
投資先をかんたんに分散できる
「分散」について少しだけ説明するよ。
老後の資産形成を目的として長期的に堅実安定の投資をするのであれば、「分散」という考え方は非常に大事!
「分散」はリスク低減になります。一方でリターンも低減されます。つまり、ローリスクローリターンのための投資が「分散投資」です。リスクとリターンは表裏一体です!
投資の格言で「卵はひとつのカゴに盛るな」と言われているね。
「投資先をひとつに集中させない」ということですね。
- 特定の会社(株)に集中投資する!
⇒投資先のわずか一社の株価が下落したら、全資産が被害を受けてしまう。 - 特定の分野(自動車関連の株)に投資する!
⇒特定分野の景気が悪くなったら、全資産が被害を受けてしまう。 - 国内の会社(株)に幅広く投資する!
⇒日本全体の景気が低迷したら、全資産が被害を受けてしまう。 - 全世界の会社(株)に幅広く投資する!
⇒世界全体の景気が低迷したら、全資産が被害を受けてしまう。 - 株だけではなく債券、不動産やコモディティ(金などの物)にも投資する!
当然、⑤にいくほど分散が効いていて、一部で被害が出ても他でカバーできるようになります。ただし、リスク分散(平均化)ができる分、リターンも分散(平均化)されるため、ローリスクローリターンの考え方になります。
短期間で大きくもうける手法のひとつの「小型株集中投資」の考え方は①に近いですね。
分散についてかんたんに理解したところで、投資信託の話に戻るよ!
投資信託なら「かんたんに分散できる」というお話でしたね。
うん。まあそれも「選ぶ投資信託を間違わなければ」という条件が付くんだけどね。
投資信託はその運用方針に従っていろいろな投資先に投資を行います。この「いろいろな」という部分がポイントです。
投資信託によって「日経平均の構成銘柄全体に投資」「米国の代表企業に投資」「先進国の債券に投資」「日本の不動産に投資」などなど、いろいろな運用方針が決められています。
決められた運用方針に従って、投資信託は幅広く分散投資してくれます。逆に言うと、決められた範囲でしか分散投資されません。
投資信託に任せれば、勝手に分散投資してくれるというのは間違いないよ。
選ぶ投資信託を間違えると「思ったよりも分散できてない!」ってなるわけですね。
そういうこと!リスクとリターンを考えて、自分の投資方針にあった投資信託選びが大事!
投資比率は自動的に調整される
初心者のうちはあまり考えなくてよいかもしれませんが、資産運用をしていると「ポートフォリオ」という言葉を聞くようになります。
「ポートフォリオ」というのは資産の構成内容のことです。
確定拠出年金をやっていれば耳にするかもしれませんが、たとえば「国内株」「国内債券」「海外株」「海外債券」の割合はどうであるべきか、というのもポートフォリオのお話になります。
投資信託は資産運用方針の下、資産構成を自動的に調整してくれます。こういう細かい割合調整や銘柄入替などを自動でやってくれるのは、初心者にとっては非常に助かります!面倒だし、どうしてよいかよくわからない部分ですからね!
こうした調整の範囲も投資信託の運用方針の範囲になるから、完全に投資信託に丸投げとはいかない部分ではあるんだけどね…
資産の割合も投資信託に完全に丸投げするなら、バランス型の投資信託を選ぶのが無難かもしれませんね。
投資している分だけではなく、貯金も資産のひとつだから、自分の資産全体の管理はどこまでいっても自分で考えるところではあるんだけどね。
海外への投資もかんたん
「国内投資だけでは不十分!海外にも投資したい!」
昨今の国内景気を考えると海外投資に魅力を感じる人も多いはずです。
投資信託なら海外投資もハードルが低いです。なぜなら、国内の投資信託が海外投資も扱っているできるからです!
円貨で国内の投資信託に投資すれば、投資信託を経由して海外投資が可能です。
といっても最近は、円貨を外貨に変換せずとも証券会社で勝手に外貨に変えてくれたりするから、投資信託への投資でなくても海外投資への手間・ハードルは下がってきましたが…
自動的に再投資をしてくれる
長期投資において複利の効果は絶大!
毎月8.33万円の資産運用(投資)で年利の差を比較したグラフを見てみましょう。配当金については投資信託先によって変わりますが、仮に再投資有無で年利2%くらいは変わるとみると差のほどが分かりますね。

複利の効果を活かすのであれば、配当金・分配金は再投資する方がよいです。投資信託ではこの再投資を自動的にやってくれます。
もちろん、配当金を出す投資信託の場合は、再投資か配当金を受け取るかを選べるので、強制的に再投資されてしまうわけではないですよ。
そもそも配当金は再投資が前提になっている投資信託も多いのだけどね。
むしろ、配当金を出している投資信託をあまり信用できないのですが…
投資信託の配当金については気を付けた方がよいのは事実。気になる人は「たこ足配当」で調べてみましょう!
投資信託のデメリットは?
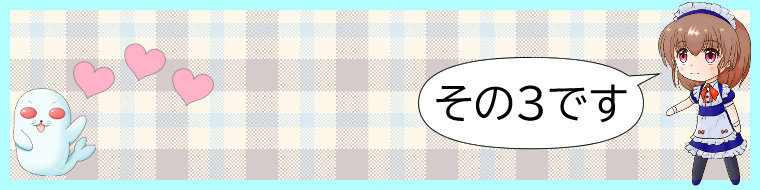
これまで投資信託を初心者にオススメできるよいポイントをお伝えしてきましたが、投資をする以上、デメリットまで理解しておくべきです。
投資は自己責任!メリットばかりを見ないでデメリットもしっかり見ましょう!
デメリットを理解せずに投資を始めると「騙されたー!」ってなってしまうかもしれないよ!
- 初心者は投資信託で罠にハメられやすい。
- 投資信託には手数料がかかる。
- お金を得るには自分で売却をしないといけない。
- 自分で細かい取得銘柄や投資割合などを調整できない。
- 投資としてつまらない。
「初心者は罠にハメられやすい」ってまた不穏ですね…
むしろ初心者だからこそ、投資信託の罠については一番知っておくべきポイントだよ!
初心者は投資信託で罠にハメられやすい
投資信託のデメリットは、他のサイトでもいろいろと情報を見ることができるでしょう。
投資信託の良し悪しを論じるのも大事ですが、投資においては騙されないことが重要です!
投資信託は、初心者が資産運用や投資を検討する上で便利なことは間違いありません。そのため、初心者は投資信託を求める傾向にあり、下手な相手に投資信託の相談をしようものなら、罠のような投資信託を勧められてしまうこともあります。
これから投資信託を考える本当の初心者に一番知っておいてもらいたいポイントです!
投資や資産運用の本気の初心者は、まずは詳しい人に話を聞くべく金融機関に相談しに行こうと考える人が多いと思うのだよね。
とても身に覚えのある話ですね…本当に注意ですね…
たとえ話を挙げておきます。
「今日の夕飯は何にしようか?」
そんなことを考えながら商店街に出かけました。
お肉屋さんでオススメの食材を聞くのと、スーパーでオススメの食材を聞くのでは、どちらの方がお得な買い物ができそうでしょうか?
このたとえ話で言いたいことは、「お肉屋さんでオススメを聞いても、お肉屋さんの立場ではお肉しかオススメしてくれない」「スーパーでオススメを聞けば幅広い範囲の中からオススメを考えてもらえる」ということです。
さらに言うのであれば、「スーパーの店員に聞くよりも近所の奥様方からオススメを聞いた方が購入者の立場からオススメを考えてもらえる」でしょう。
私自身、本当の最初の一歩は投資信託を選んだのだけど、見事に罠にハメられてしまいました…
くわしくはこちらの記事を参照です!

投資信託を利用する際には、最低限の知識は身に付けておきましょう!
年利や手数料の相場感について少し知っておくだけでも違いますよ!
投資信託には手数料がかかる
投資信託は資産運用のプロに運用をお任せする代わりに手数料がかかります。当たり前ですけど、投資信託のデメリットとして避けられないですね。
投資信託の手数料は「投資する時」「運用期間中」「解約時」のタイミングでかかりますが、最近は「運用期間中」だけ手数料がかかるタイプが珍しくないです。
なお、「運用期間中」にかかる手数料は信託報酬として「年間○%」と表示されてます。「○%」というのは運用資産にかかる手数料です。運用資産が増えれば増えるほど手数料も増えるということですね。
余談だけど、「年間○%」の手数料は1年に一度かかるわけではなくて、実際には毎日手数料が発生しているよ。1年間の合計手数料が○%ということだね。
手数料自体は投資信託を利用するための必要経費と考えましょう!自分が資産運用で楽をするための費用です!
とはいえ、手数料が高ければそれだけ利益も減ってしまうから、手数料は安いにこしたことはないよ!
お金を得るには自分で売却をしないといけない
老後のための長期資産運用の観点では、そもそも運用期間中に投資信託を解約(売却)する必要は基本的にはないです。投資信託にお金を投資し続けて、資産を積み上げていく一方で問題ないでしょう。
しかし、老後でお金を使うタイミングになったら自分で投資信託の解約(売却)をしてお金を引き出す必要があります。
投資信託の出口戦略(資産運用後のアクション)について知識を持っておくべきで、売却ペースなどは自分で考えて実行しなければなりません。
かんたんに出口戦略のひとつを説明すると、「投資信託からの引き出し額<投資信託の運用益」であれば、投資信託で積み上げた資産が減ることなく半永久的にお金を引き出し続けることができます。
ちなみに高配当ETFとかなら、何もせずに配当金を得られるよ!その反面、デメリットもあるのだけど。
投資信託でも配当金をえられるものがありますけど、そういう商品は中身に注意が必要なので初心者向きではないです!
自分で細かい取得銘柄や投資割合などを調整できない
これは初心者の立場ではデメリットとして考えなくてよいでしょう。
自分で銘柄や投資割合の調整をしなくても済むようにするための投資信託ですからね!
投資としてつまらない
これは初心者にとってのデメリットではなく、投資に慣れてきた時に発生するデメリットです。
堅実安定のコツコツ投資のローリスクローリターンの運用は、良くも悪くも刺激があまりありません!人間、慣れてくると刺激を求めたくなってしまうもの。しかし、それが罠!
せっかく、堅実安定のローリスクローリターンがうまくいっていたとしても、その安定感につまらなさを感じてハイリスクハイリターンを取りにいった結果、大きな損失を出してしまうパターンが考えられます!
老後の資産形成を目的とするのであれば、つまらない投資をコツコツ続ける忍耐力も欲しいところです。
ハイリスクハイリターンの投資信託もあるけど、このブログでオススメするのはローリスクローリターンの投資信託だよ!
短期間で大きく稼げるのは理想ですけど、ハイリスクハイリターンは誰がやってもうまくいくものではないですもんね。
どういう目的で投資信託を使うの?
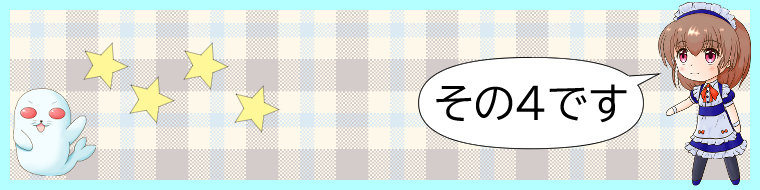
投資信託をどのように活用するのか?ここは非常に大事なポイントです!
これまで投資信託がどういうものかを伝えてきましたが、とにかく堅実安定ローリスクローリターンでの運用をこのブログではオススメします。
なぜならば、このブログは「再現性が高い老後のための資産形成のための投資」を目指しているからです。
多くの人にとって再現性が高い手法というのは、どうしても次のような要件が必要です。
- 専門的な知識が不要
運用をプロに任せれば問題なし!→投資信託でOK - 何かを判断する必要がない
運用をプロに任せれば問題なし!→投資信託でOK - 時間を使わない
運用をプロに任せれば問題なし!→投資信託でOK - 誰がやっても(初心者でも)同じような成果が得られる
運用をプロに任せれば問題なし!→投資信託でOK
⇒要するに、初心者が片手間にできる投資=投資信託です!
この「初心者が片手間にする投資」として適しているのが投資信託というわけです。なんせ、プロが代わりに資産運用してくれるのが投資信託ですからね。
投資信託の活用目的はいろいろあるでしょうけれども、こうした理由からこのブログでは初心者が老後のために活用する目的として投資信託の活用を考えます。初心者をターゲットとするからこそ、再現性(誰がやっても同じような結果になる)が高い方法が欲しいのです。
さて、このブログの投資方針を振り返ってみよう!
他の記事でも使いまわしてるやつー!

投資信託は、老後の「緊急用資産」を稼ぎつつ、運用利益の部分取り崩しで「配当金」相当のお金を半永久的に得る手段にもなるよ!
ローリスクローリターンの投資信託は、老後の着実な資産形成の柱のひとつですね!
ただし、罠のような投資信託には注意だよ…

そもそも投資を始める前に、資産運用の目標額や投資ペースの確認も必要ですよ~!
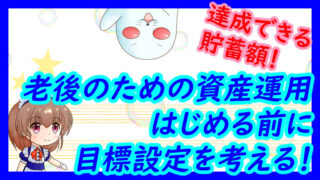
どんな投資信託に投資すればいいの?
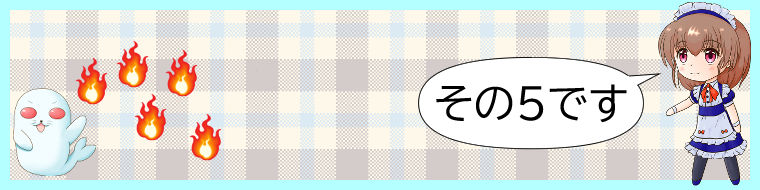
投資信託には大きくわけてインデックスファンドとアクティブファンドがあります。
オススメするのはインデックスファンドです!
詳しい説明は省くけど、アクティブファンドよりもインデックスファンドの方が運用成績が良いって言われているよ!
長期的に見れば、インデックスファンドの優位性は理論的に証明されているらしいですね。
インデックスファンドとアクティブファンド
かんたんにインデックスファンドとアクティブファンドについて説明してきます。詳しい説明は他サイトに多くの情報があるので割愛します。
【インデックスファンド】
とある市場指標(インデックス)に追従するように運用される投資信託(ファンド)。
たとえば、日経平均やTOPIXに追従するような投資信託などがある。
特徴は以下通り。
- 手数料が安い。(ファンドマネージャーの手間が少ない)
- 良くも悪くも市場に追従するため、市場全体の景気が悪化すれば評価額は下落する。
【アクティブファンド】
市場平均(インデックス)よりも高い運用成績を目指す投資信託(ファンド)。
ファンドマネージャーの力量により運用成績も様々。
特徴は以下通り。
- 手数料が高い。(ファンドマネージャーの手間が多い)
- 市場全体の景気が悪い時でも利益を出すための運用を行うが、長期的な運用成績ではインデックスファンドに勝るアクティブファンドは少ない。
インデックスファンド推奨、だけど注意
投資の目的が老後の資産形成であるのであれば、基本的には10年~30年,40年くらいの長期投資をすることになるでしょう。
長期投資前提であるからこそ、手数料が安く、理論的に長期運用であれば運用成績が勝ると言われているインデックス投資が有力な選択です。
手数料が安いほど、手元に残るリターンが増えるよ!
長期だと手数料は0.1%の差でも気にするレベルになります!
インデックスファンドで注意しなければならないことは、「よくもわるくも市場指標に追従する」ということです。
つまり、長期的に経済成長が見られない市場に投資したらインデックスファンドであろうとも利益がでないということです!なぜなら、市場の景気が悪化すれば、そのまま悪化に引きずられてしまうからです。
長期投資ならば、短期的な損得は気にしないくらいでちょうどいい!
それでも気になっちゃうのが人間なんですけどね~…
インデックスファンド、何を選ぶ?
「インデックスファンドに投資をしよう!」と思っても選択肢はいっぱいあります。
その中でなにを選ぶべきでしょうか?
インデックスファンド選びでとくに注意したいポイントはこれ!
- 長期的に右肩上がりの成長が見込める市場であること。
- 投資先に分散を効かせること。
- 手数料が安いこと。
右肩上がりの成長
老後の資産形成のための投資です。当然、老後の時点で資産運用で利益がでていることを期待したいですよね。
市場には波があるので、プラスになる年もあればマイナスになる年があるのは仕方がないです。しかし、平均的に長期でプラスの成績が期待できる市場でなければ、老後の時点での資産運用の利益は期待できません。
結局、どういう市場に投資すればいいのですか?
人気が高いのはやっぱり米国市場だね。全世界も人気が高いね。(’21/7/21時点)
米国は過去何十年という実績から超長期で見れば右肩上がりの実績がありますもんね。
世界全体も基本的には経済成長を続けていく傾向があるから、全世界も右肩上がりが期待しやすいね。
国内はどうなんですか?
国内は日経平均株価のチャートで調べると分かるけど、残念ながら超長期で見た際には右肩上がりとは言えないね…(’21/7/21時点)
経済成長という視点なら各国のGDPの推移も参考になりそうな指標ですね!
投資先は分散
株価、投資信託なら標準価額の変化に振り回されないように、投資タイミングの分散(時間分散、ドルコスト平均法)が便利なことはすでに伝えた通りです。
そのほかに考えられる分散として「投資作の分散」があります。
投資信託の投資先は様々な種類がありますが、なるべく広い分野への投資の方が分散が効いていて安定感があるでしょう。
いろいろな会社の株の詰め合わせになるような「国全体へ投資する投資信託」は広く分散投資できる例だね。国内株への投資なら、「日経平均」や「TOPIX」に連動する投資信託とかね。
人気の投資先の米国なら「S&P500」や「全米株」ですね!
他にも「新興国株」とかもあるね。でもやはり国レベルの分散の究極系は「全世界株」だろうね!
日経平均、TOPIX、S&P500…これらに連動する投資信託というのは、すべて株式投資の分散になります。しかし世の中にある投資対象は株式だけではありません。
投資対象の種類を分散することももちろん考えられます!
ただ、いろいろな投資対象がある中で信頼性が高いのはやはり「株式、債券、不動産」です。これらは歴史ある投資商品であり実績と信頼があります。
最近は不動産といってもREITという形で少ない資金でも投資できるような仕組みができています。といっても、不動産に自分で投資するのとREITを利用して投資するのは完全に別物です。
なお、REITは株式や債券に比べると断然歴史が短い投資商品です。
不動産にも興味はあるけど大きな投資もこわいので、私は管理も楽ちんなREITで今のところは満足かな…
初心者なら管理が楽な資産から始めた方がよいのは間違いないです!
コモディティ(物)にあたる「金」も歴史ある投資対象ですが、「金」自体は利益(配当金・分配金)を生む投資商品ではないので個人的には投資対象として考えてないです。もしも将来、私自身の資産が増えてきて資産防衛を意識するようになったら、分散の一環として「金」も投資対象に検討するかもしれません。
話を戻して、投資商品には「株式、債券、不動産」の他にもいろいろありますが、歴史ある信頼性が高い投資商品はこのあたりだと考えてよいでしょう。
初心者にとっての基本は、株式、債券、REITが対象になるでしょうけれども、それぞれどのくらいの割合で持つべきか、というのは個人個人で正解が違ってきます。
- 株式:債券に比べて、ハイリスクハイリターン
→攻めに向いた投資対象 - 債券:株式に比べて、ローリスクローリターン
→守りに向いた投資対象
長期運用がしやすい若いうちは攻めの株式を重視して、老後が近づくにつれて守りの債券を重視、というのが一般的によく言われるスタイルだね。
このあたりは自分の性格や目標利回りなどと相談といったところですね。
REIT(不動産)はまだ市場規模が大きくないから、株式とかに比べたらオマケくらいの位置付けくらいがよいかもね。(’21/7/21時点)
ちなみに、投資ジャンルもひとつの投資信託で分散してくれる「バランス型ファンド」というものもあります。
たとえば、「国内株式、国内債券、海外株式、海外債券」に分散してくれるファンドですね。ほかにも「国内REIT、海外REIT」も加えて分散してくれるファンドもあります。「海外」についても「先進国、新興国」で分かれていたりもしますよ。
バランス型ファンドはひとつで広く分散してくれるのでありがたいのだけど、個人的には投資対象は自分で配分決めたいかなぁ…手数料もちょっと…
こういう資産配分(ポートフォリオ)の話になると、完全に人それぞれですね~。
手数料の安さ
基本的にインデックスファンドであれば手数料は比較的安いです。アクティブファンドの手数料が高いともいえますね。
手数料の相場感は、自分でいろいろな投資信託を確認して目を肥やすとよいです。同じような投資信託でも扱っている証券会社によって手数料が違ったりもしますよ。
ちなみに、運用されている投資信託の規模が大きいほど手数料も安くなる傾向があります。規模が大きい投資信託は資金が集まっている証拠でもあるので安心感もあります。
投資信託の規模の大きさは「総資産額」を見れば分かります。投資信託を選ぶ時の代表的な確認点のひとつです。
オススメはやっぱりネット証券でチェックしてみることですね!
結局、相場感ってどのくらいがいいとかあるんですか?
個人的な見解になってしまうけど…0.2%以下、できれば0.1%以下を狙いたいね。手数料競争も激しいから、今時点での感覚だけどね。(’21/7/22現在)
オススメの投資信託、結論は?
具体的な投資信託をオススメとして紹介すると、暴落した時などにトラブルが発生するかもしれませんので、投資信託の具体名を挙げることはしません。
今までお伝えしてきたことのまとめをして結論に変えさせていただきます。
しつこく言っているけど、投資はあくまで自己責任で!
ここでオススメしている投資信託の選び方は、初心者による老後の資産形成のための長期投資でローリスクローリターンの運用を目指すものですよ~!
投資目的や投資スタイル、各個人の投資へのリスク許容度によっても選ぶべき投資信託は変わるので注意!
- インデックスファンドを選ぼう!
- 超長期目線で継続的な成長が期待できる市場へ分散投資しよう!
→人気があるのは、S&P500(米国有力企業全体)、全米、全世界あたり。 - 資産運用の方針をよりローリスクローリターンに寄せるのであれば、株式以外に債券などへ投資するのもよいです。
→年齢が高くなるにつれて、安定志向にするのが無難。 - いろいろな投資信託を組み合わせて分散投資を自分で組み立てるのが面倒な人は、バランス型ファンドという選択もあります。
- 投資信託の手数料はなるべく安く!
→目安例としては0.2%以下(’21/7/23時点の個人的感覚値) - 投資信託の総資産額(規模)は大きい方が安心!
初心者にオススメの投資信託との付き合い方とは?
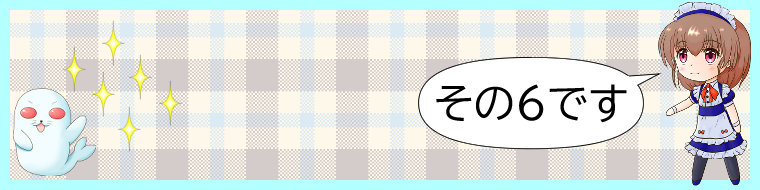
初心者にオススメできる投資の第一歩として、投資信託を紹介しています。
「なぜ投資信託が初心者にオススメなのか?」ここでいったん振り返ってみましょう。
- 専門的な知識が不要
- 何かを判断する必要がない
- 時間を使わない
- 誰がやっても(初心者でも)同じような成果が得られる
⇒初心者は「何もしない」のが投資信託とのオススメの付き合い方!
これはまた思い切った暴論ですね…
いや、ふざけてないよ!?大真面目だよ!
「初心者の誰がやっても同じような成果を出せる再現性のあるローリスクローリターンの投資」
目指している初心者用の投資がこの方針です。
「誰がやっても同じで再現性がある」ということは、人によってやる事にバラツキがでない必要があります。人それぞれ違う行動を取ったら結果も変わってきますから、再現性はないですよね。
つまり、「何もしない」ことがもっとも「誰がやっても同じ結果になる再現性のある行動」です。
そして、「何もしない」ことが許される投資が投資信託への投資なのです。
なんだかダマされてるような気もしますけど、確かに誰もが同じようにできる行動は「何もしない」かもしれませんね。
素直に投資のプロに運用を任せる!これが一番単純。
投資信託を始める最初の一歩だけは行動しないといけませんから、そこだけ頑張ればいいのですね!
【投資信託を始めよう!】
- 証券口座を開設する。手数料の問題からネット証券がオススメ。
- 老後の資産形成の目標を設定して、毎月必要な投資額を決める。
- 証券口座で投資信託の毎月積立の設定を行う。つみたてNISAを利用すると税金面で有利。
- 投資する投資信託を選ぶ。インデックスファンドがオススメ。なるべく分散投資を心掛ける。
- 何もせずに放っておく。(②定期定額積立の設定をしてしまえば、自動的にドルコスト平均法で投資され続ける。)
※資産のリバランスも大事ですが、初心者へのオススメ投資行動としては含めてません。投資に慣れてきてある程度学びを得てからリバランスを視野にいれましょう。
①については、オススメのネット証券口座を調べるといろいろ出てきます。有名どころとしては「SBI証券」「楽天証券」ですね。ほかにもいろいろなネット証券がありますよ。(’21/7/24現在)
②について、必要な投資額は人それぞれ。周りの人のことは気にせず「自分ならいくら必要なのか?」を考えましょう。参考になる記事を置いておきます。
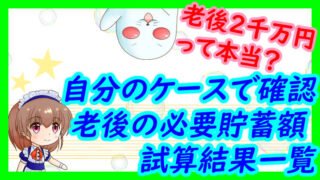
③については、各ネット証券での操作のお話になるので割愛します。
④については、この記事で書いてきたインデックスファンドの選び方を参照にしてください。
⑤だけど、いざ投資を始めると「何もしない」というのが意外と難しかったりするんだよね…
日々変動する評価額とか、あまり見ない方がいい、という話も聞きますね…
評価額が暴落した時とか、「もっと価格が落ちるかも!?」って狼狽して投資した商品を売っちゃうとかね。
結果的に、「高く買って安く売る(損を確定させる)」をいたずらに繰り返してしまう原因ですね。
長期投資をするならば、評価額の上下は気にせず、ひたすら愚直に定期定額投資を続けることだね。
投資信託を売らずに(解約せずに)、ひたすら持ち続ける、買い続ける!ですね。
もちろん、大前提として「投資信託を選び間違えてないこと」だけは大事だけどね!
「何もしない」について、「いかに自分の選んだ投資先を信じることができるか」という精神的な自分との戦いになります。
「投資に対して浅い知識・理解で自分の投資を信じて長期投資を続ける人」と「投資に対して深い知識・理解で自分の投資を信じて長期投資を続ける人」で同じ成果(利回り)を得られるのが投資信託です。
長期投資の対象としてローリスクローリターンの分散が効いたインデックスファンドを選んだとしても、運用成績がマイナスに沈む年があるのも珍しくありません。
結果的に長期的視点では右肩上がりを続けてきたS&P500(米国の代表的な指数)でも数年程度の期間で見ると成績が悪い時期もあるのです。
そうした成績の悪い時期でも選んだ投資信託を解約せずに持ち続けて投資し続けるためには「自分の投資を信じている」ことが大事です。
自分の投資を疑って、成績が悪い時に解約して他の投資信託に乗り換えるようなことを繰り返すと、結果として何もせずに放置していた時よりも悪い運用成績になる、ということになりかねません。
まとめ:投資信託のポイント・注意点
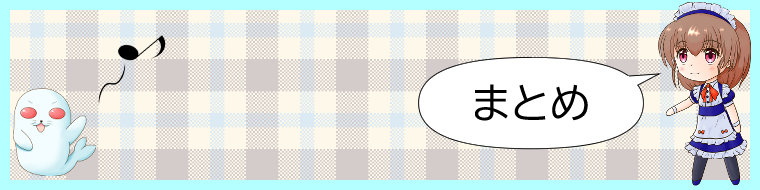
投資初心者にオススメできる投資の第一歩として投資信託をオススメしました。
初心者が老後の資産形成のために投資信託を選ぶべきポイントをおさらいしましょう。
- 投資信託なら少額投資(100円)から投資を始められる!
- 投資信託ならプロが資産運用してくれるから初心者でも大丈夫!
- 定期定額投資を自動的に行える。手間いらず。
- 証券口座は手数料などの観点からネット証券がオススメ。
- どの投資信託に投資するかですべてが決まる。
- 長期投資をするならば、運用成績が悪い時でも慌てず「何もしない」こと。
※投資先の投資信託の右肩上がりの成長を信じられることが大前提。
投資信託は、インデックスファンドで分散を効かせるのがローリスクローリターンの資産運用を目指すポイントだよ!
どの投資信託に投資するかは一番大事!
定期定額投資を始めたら、あとは「何もしない」が初心者にとって基本だよ!
暴落時に投資信託を解約せずに定期定額投資を継続できるか…ここが長期投資できるかどうかのポイントですね。
なんにせよ、初心者が始めやすい投資として投資信託は便利だよ!
根本的なところとして、そもそも老後に向けて資産形成をしようとした際に「今の貯金ペースでは、定年までに必要な目標貯金額が達成できない」場合に投資・資産運用を考えるものです。
投資・資産運用はリスクを負う分、貯金や定期預金などよりも高い年利が期待できます。高い年利による福利効果は非常に大きく、長期視点では貯蓄ペースアップが期待できます。
しかし、投資・資産運用自体はリスクがあります。投資・資産運用の必要がない人は無駄にリスクを負って投資をする必ようはないでしょう。
投資・資産運用は万人にオススメできるものではありません。投資・資産運用は余裕資金の範囲で計画的に!
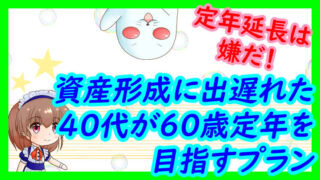
投資は自己責任です!
投資は人に流されてなんとなくするものではありません。投資にはリスクがあることを理解した上で、投資をする必要性・目的がある場合に、はじめて投資・資産運用という選択肢が出てくるものと考えます。
投資ペースも人に流されるものではありません。自分のペースを守って安全資産を確保した上で余裕資金の範囲で投資を行うようにしましょう。
投資は自己責任だよ!何か損失が発生しても誰も保証してくれないよ!
このブログでも投資・資産運用についての責任は負えませんのであしからず、です。
投資についてもっとしっかり勉強したい!という人は、こちらの記事もどうぞ!
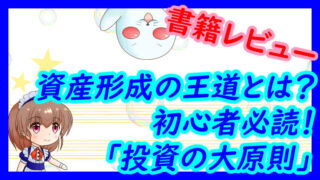



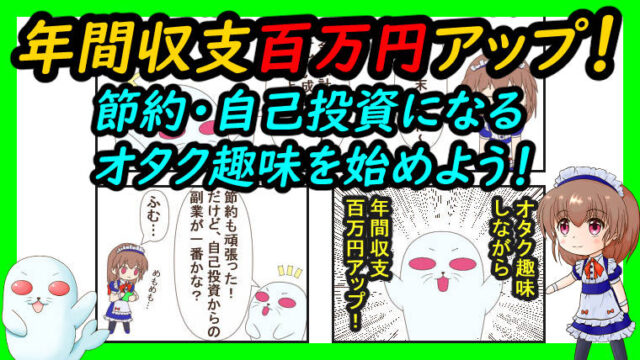
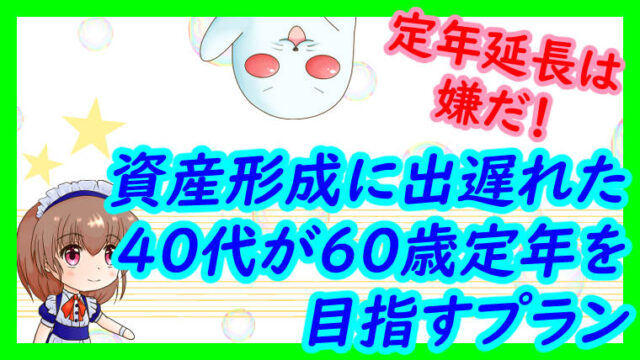
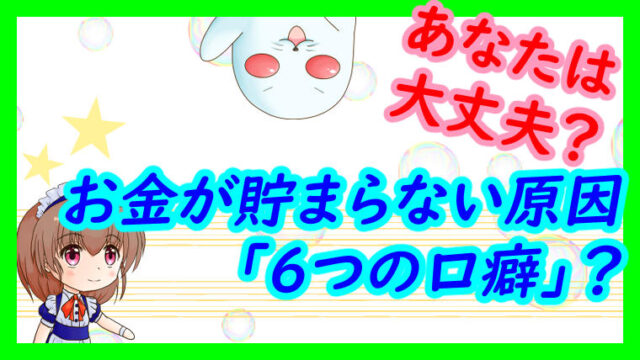



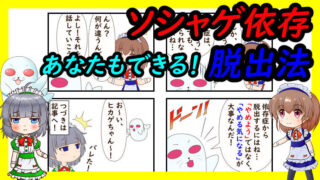




投資信託に話を戻すと、投資信託を販売する人に投資信託のオススメを聞くべきではないということ。
販売者にとって良い商品=購入者にとって良い商品ではありません
もしも投資について相談するのであれば、できる限り中立的な立場の相手に相談すべきでしょう。