「老後の生活が年金だけでは心配…」
「老後にお金で苦労したくない!」
「不労所得で経済的自由を目指したい!」
そんなことを考えている人にオススメなのが配当金!
配当金を得るには投資が必須です。そして、投資初心者でも取り組みやすいのが高配当ETFです。
私は老後リスクを回避するための資産運用として、二大支柱は「投資信託」「高配当ETF」だと考えているよ。
老後リスクを回避するための戦略、高配当ETFに投資する魅力について語っていきましょう!
- 一般の年金保険などはかなりローリスクローリターン。老後に備えてリターンが不足の人はもう一歩リスクを負う事も検討。
- 一般の年金保険は終身で年金を受け取ろうとするとローリターンすぎて元本割れのリスクが高い。
- 配当金は完全な不労所得でかつ半永久的に受け取ることができる。働けなくなっても収入源になる安心感。
- 「年金+配当金>生活費」を実現できれば、老後の資産が尽きることはない。経済的自由の達成。
完全な初心者がいきなりETFに手を出すのはオススメしないよ。
まずは投資信託、慣れてきたらETFも検討、ですね!
まあ投資信託も投資先を間違えると全然ダメだから、投資先の選定は要注意だけどね。
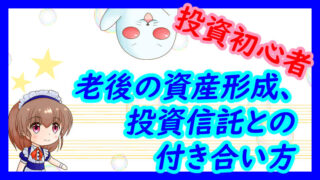
老後リスクを回避するための戦略
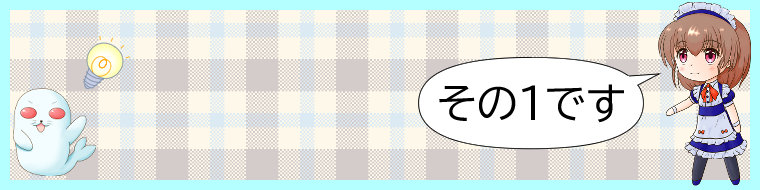
このブログでは、老後リスクを回避するための理想目標として「年金と配当金を合わせて定年後に経済的自由を達成」を掲げています。
経済的自由の達成に向けて
定年を待たずに経済的自由を達成できるに越したことはないです。いわゆるFIRE(経済的独立と早期リタイア)ですね。
資産運用は早期に始めるほど効果が大きいもの。若いうちから資産運用を始めている人だったらFIREの達成も夢ではないでしょう!
まさに「時は金なり」!本来の意味とは違って、言葉通りの意味で!それだけ、長期間の資産運用による福利効果は大きいです。
下のグラフは、毎月8.33万円を「年利○%」で資産運用した場合の貯蓄額の推移だね。
平均年利3~5%くらいで資産運用できたとして、運用なし(年利0%)と比べると、20年間で1.5倍近い差が出てますね。

就職して即資産運用をすれば、定年までおおよそ40年の資産運用期間がありますね。FIREの目標金額は生活レベルによっても変わりますが、40年かからずに目標達成するのは不可能ではないでしょう。
しかし、資産運用を開始するのが遅かった場合は、定年までに十分な運用期間がありません!
それならば、せめて定年延長をしなくてもすむように、「年金+配当金」で経済的自由を達成できればよいではないか!という考え方もありでしょう。
歳をとったからって、資産運用をするのが出遅れたって、今からでも動けば老後の生活を楽にできる!
「老後リスクが不安なのに何もしない!」というのが一番マズイですね!
老後リスク対策に出遅れてもできること
老後リスクを完全になくすには「経済的自由を達成」することです。
経済的自由とは、何もせずとも日々の生活費以上の収入を得られる状態です。
老後になれば年金を受け取る事ができますが、年金だけでは生活費が足りないようだと、今後一生、貯蓄が削られ続けることになり、長生きするほど貯蓄の目減りに怯えて暮らすことになりかねません!
老後の生活費が年金の範囲に収まらないのであれば、収入を増やすしかありません。しかし、老後も安定して仕事ができるとは限りませんね。
そこで提案するのが配当金(不労所得)を得る行動を今からすることです!
FIREは無理でも、老後の年金も考慮して経済的自由を達成するための提案が下の図だよ。
この図も何回目の登場やら…w

年金だけでは足りない分を配当金でカバー!
ここでやっと今回のお話、「高配当ETF」につながるわけですね!
年期を考慮に入れれば、経済的自由のハードルはかなり下がるよ!まあ、60歳までは働かないといけない計算になるとは思うけど…
具体的な金額の計算の参考になる記事を置いておきますね~。
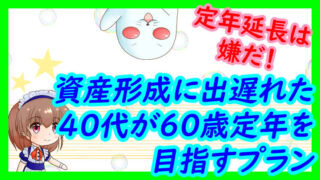
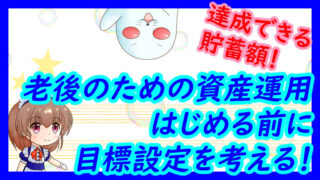
ETFってなに?投資信託ではダメなの?
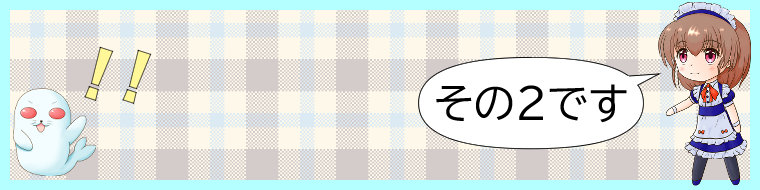
ETFの詳しい説明はいろいろなサイトでされています。よって、この記事ではETFを購入する上で初心者が押さえておきたいポイントだけかんたんに説明します。
といっても、かんたんな内容にとどめているものの基礎的知識だけでそれなりに長い説明になってしまっています…ご承知おきください。
先に結論を言っておくと、投資・資産運用に手間暇をかけたくないなら投資信託だけでもよいよ!
さらに投資の世界へ一歩踏み込みたい人に投資信託の次にオススメするのがETFですね。
あとは不労所得の手段として配当金を求めるなら、やっぱりETFが初心者にとって無難な選択肢ってところかな。
ETFについて知ろう!
ETFは一言でいうならば「上場している投資信託」です。
「上場しているとなにが違うの?」というのが大事なところですね。かんたんにまとめると次の通りです。
- ETFの売買方式は株式と同じ。
- ETFの基準価額(株価)変動は株式と同じ。
- ETFひとつで投資信託のように分散投資が可能。
- 海外ETFは外貨で購入する必要がある。
- 配当金の再投資は自分でやる必要がある。
- 投資信託と同じように信託報酬などの手数料がかかる。
- 投資信託よりもETFの方が信託報酬が安い傾向にある。
- つみたてNISAの対象商品がほぼない。(’21/7/25現在)
各ポイントの内容を説明していくよ!
ETFの売買方式
投資信託は定期定額投資を一度設定すれば、あとは放っておけば勝手にドルコスト平均法で投資されていきます。
しかし、ETFの場合は通常の株式同様、購入したい時に自分で購入作業しないといけません。具体的に自分でやらないといけない作業は以下の通り。
- 購入単位は「株」。何株購入するかを決める。
- 購入方法を決定する。成行・指値・逆指値など知識が必要。
- 取引時間(株式やETFなどを売買できる時間)内で、価格が変動する。よって、いつ購入するかの判断が必要。
- 海外ETFを購入する場合は、外貨の準備が必要(自動換金してくれるサービスもあり)。
投資信託に比べると、購入だけでハードルが上がりますね…
ETFはとても便利だけど、多少の知識が必要になってくるからね。実際にやってみると大した内容ではないのだけど。
完全な投資初心者からすれば、最初の一歩は可能な限りハードルが低い方がいいですね!
だからやっぱり最初はETFよりも投資信託がオススメかなー。
投資信託とETFの売買方式の違いで特に大きいのは「購入単位の違い」「自動購入設定の有無」でしょう。
- 購入単位の違いについて補足
投資信託は金額を指定して投資できるのに対し、ETFは株数を指定して投資になります。
よって、ETFの投資額は最低単位である1株あたりの価格に依存します。つまり、投資信託のように100円からの定額投資ということは(基本的に)できません!
- 自動購入設定の有無について補足
ETFの購入は(基本的に)手動です。
定期定額投資のように積立感覚で時間をかけずに資産運用したい人は、ETFよりも自動化できる投資信託の方が無難です。
※’21/7/25現在、SBI証券には投資信託と似たような売買が可能な「定期買付サービス」というのものもあります。(あくまで「似たような」です。)
ETFの基準価額変動
投資信託は一日一回、基準価額が決まって、一日中同じ基準価額です。一方、ETFは取引時間中、時々刻々と基準価額が変動します。
この基準価額(株価)変動は株式でも同じなので、株式売買を経験したことがある人には当たり前のことですが、投資信託しかやったことがない人からすると、世界が変わった感覚になることでしょう。
常に基準価額の変動(評価損益)を気にしてしまうような人は、日中の価格推移も気になってしまって日常生活に多少の影響が出てしまうかもしれません。
「老後のための長期投資」という意識がしっかり固まっていれば、基準価額の多少の変動は気にならなくなるんだけどね。
それでも暴落とかを目の当たりにしたら狼狽してしまうのが人の心ですよね…
また、基準価額が取引時間中に変動することから、購入しようとしても購入タイミングが分からなくなってしまうということも考えられます。
ETFは手動で購入だから、「少しでも安いタイミングで買う!」って意識が少なからず働いてしまって、なかなか買えなかったりするんだよね~。
ETFに対して手動で「投資信託のような定期定額投資」をしようとしても、人間心理的に難しかったりもするのですね。
ETFの購入はある程度の投資慣れ・知識・思い切りも必要のため、投資初心者向きではありません。
ETFで分散投資
ETFは売買方式が大きく異なることを除けば基本的には投資信託と同じです。ETFは「上場している投資信託」なので、当たり前といえば当たり前ですね。
よって、ETFへの投資も基本的には分散が効いています。
たとえば、米国の代表的企業で構成されている市場指標のS&P500に連動するETFの一例としてVOOというものがあります。同じ市場指標に連動するETFでも運用会社によって種類があります。
分散投資について、軽くおさらいしておくよ!
- 特定の会社(株)に集中投資する!
⇒投資先のわずか一社の株価が下落したら、全資産が被害を受けてしまう。 - 特定の分野(自動車関連の株)に投資する!
⇒特定分野の景気が悪くなったら、全資産が被害を受けてしまう。 - 国内の会社(株)に幅広く投資する!
⇒日本全体の景気が低迷したら、全資産が被害を受けてしまう。 - 全世界の会社(株)に幅広く投資する!
⇒世界全体の景気が低迷したら、全資産が被害を受けてしまう。 - 株だけではなく債券、不動産やコモディティ(金などの物)にも投資する!
当然、⑤にいくほど分散が効いていて、一部で被害が出ても他でカバーできるようになります。ただし、リスク分散(平均化)ができる分、リターンも分散(平均化)されるため、ローリスクローリターンの考え方になります。
短期間で大きくもうける手法のひとつの「小型株集中投資」の考え方は①に近いですね。
ひとつのETFでいろいろな銘柄に投資できています!詳しい投資先(分散状態)はETFの構成割合をチェックしましょう!
海外ETFは外貨で購入
高配当ETFは米国ETFに頼るところが大きいです。(’21/7/25現在の私の考え)
そのため、高配当ETFを狙うならば主力は海外ETFです。この海外ETFを購入するには(基本的に)外貨を準備しないといけません。ETFの購入タイミングを計るのに為替影響も考慮しないといけないわけですね。
ただ、「外貨の準備」という点は、あまり気にしなくても大丈夫です。というのも、証券会社側でETF購入を円貨決済してくれたりもします。よって、事前に自分で外貨準備をせずとも、円貨から外貨への換金を証券会社にお任せにもできます。
自分で外貨を準備しなくていいなら、特に気にするポイントはなさそうですね!
といっても、海外ETFの売買は外貨で表示されるし、為替相場による影響を目の当たりにするのは間違いないよ。
為替リスクが目に見えるというわけですね…
為替リスクが目に見えるのは一長一短だね。見えると気にしてしまうのが人間だから…
海外投資の投資信託の場合、良くも悪くも見えるのは円貨だけだから、あまり為替リスクを気にしない傾向ありますね…
投資して後は放っておくスタイルの長期投資の場合、下手に情報見えない方が精神的には良いかもしれないね~。
配当金の再投資は自分でやる
資産運用において、長期投資をするならば複利の力が非常に大きいことはこれまでもお伝えしてきた通りです。
投資信託の場合、投資先から受ける配当金は自動的に再投資するように設定できます。そもそも、配当金は再投資の前提になっている投資信託が多くあります。
投資信託の場合は、基本的に再投資を前提としている投資信託を選ぶことを推奨です。
たこ足配当になっている可能性もありますしね…
配当金を受け取る場合、受け取る配当金に対して税金がかかってしまうので利益が目減りしてしまいます。
配当金を使うつもりがなく、そもそも配当金を再投資するつもりであるならば、そもそも配当金を受け取らない設定の方がよいです。
しかし、ETFの場合、配当金の再投資は手動でしかできず、配当金は一度受け取る必要があります。配当金を再投資する場合は自分で改めてETF購入をするしかありません。
よって、配当金の扱いについて、再投資を考えている人からすると投資信託の方がよいと考えにもなります。
配当金の受け取りには、良いところも悪いところもあるよ!
配当金の扱いについては、その人の投資スタイル、投資目的にもよりますね。
この点はまたあとで詳しく書いてるよ!
ETFには信託報酬などの手数料がかかる
ここもETFと投資信託で同じです。ETFは上場している投資信託(売買方式が違う投資信託)というだけなので、当然ですね。
特にETF特有の押さえておくべきポイントもありません。
信託報酬などの手数料が投資信託と比較して安い傾向
同じ投資先に投資するのであれば、投資信託に任せるよりもETFの方が手数料が安い傾向にあります。
同じ投資先に投資するのであれば、手数料が安い方が良いに決まっています。しかし、これまで見てきた通り、投資信託の方が手間がかかりません。投資信託とETF、一長一短ありますね。
今はETFと投資信託でそれほど手数料に差が出なくなってきているよ。(’21/7/25現在)
つみたてNISAがほとんど使えない
ETFよりもまずは投資信託、というのは、つみたてNISAの利用可否が非常に大きい!
税の申告方法にもよりますが、通常、投資・資産運用で得た利益の20%が税金になります。(’21/7/25現在、国内の場合)
つみたてNISAは税制面で非常に優位です。条件はありますが、この税金20%が免除になります!
つみたてNISAの口座を開いている人は、つみたてNISAの上限額までは投資信託での運用の方がお得感があるでしょう。つみたてNISAの上限額を超えて投資・資産運用を考えたくなったら、ETFなどを視野にいれるのがよいかと思います。
繰り返しになるけど投資初心者の場合、まずは投資信託から考えることをオススメするよ!
投資初心者なら投資額も少なく始めるのが推奨ですし、ETFは後回しですね。
ETFは必要?投資信託でよいのでは?
ETFについて学んだところで、あらためてETFの必要性について考えてみましょう。
結論を先に言ってしまうと、投資信託だけでもよいです。
ただし、次に当てはまるような人はETFは検討の余地があります。
- つみたてNISAの上限額を超えて資産運用をしたい人。
- 手間がかかっても、少しでも手数料を抑えたい人。
- 配当金が欲しい人。
- 初心者なりに自分の裁量で投資をしたい人。
- ステップアップして、もっといろいろな投資・資産運用をしたい人。
私はこれらにすべて当てはまる人です。
なんせ、初手から個別株を購入しましたもんね…
あれは初心者としてダメな行動だった…反面教師になると思うので、その時の記事を置いておきます。
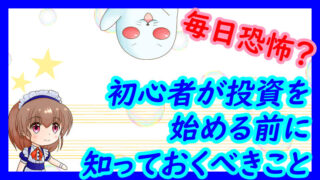
それでは、投資信託ではなくETFを選ぶ理由を少しくわしく見ていきましょう!
投資信託よりもETFが優れている、というわけではないので、そこは注意!
投資信託、ETF…それぞれに一長一短ありますね。
つみたてNISAの上限額を超えた資産運用
まずはETFに投資するよりも「つみたてNISA」を利用して投資信託に投資することをオススメします。「つみたてNISA」の上限額を超えて投資をするならば、ETFを検討する余地が出てきます。
繰り返しになりますが、つみたてNISA自体は税制面の有利性から使わないともったいないといえる制度です。
NISAには「つみたてNISA」「一般NISA」があります(’21/7/25現在)。
NISA口座は一人一口座しか持てません。また、「つみたてNISA」「一般NISA」のどちらか一方しか選べません。
細かい話は他のサイトの記事に任せるとして、個人的な結論を言ってしまうと初心者には「つみたてNISA」が適しているでしょう。
理由は次の通り。
- 上限額が少ない代わりに運用可能期間が長い。
- 長期投資を考えると一般NISAよりも最大運用額が大きい。
- 利用可能な投資信託が厳選されている。
まあ私は「一般NISA」を選んでしまったけどね!
初手から個別株の売買をやる気満々でしたもんねw
初心者が「自分はうまく株の売買ができる」とおごった結果だね…失敗だったね…
「つみたてNISA」の口座では、個別株やほとんどのETFは扱えません。基本的に投資信託をやるための口座だと思った方がよいです。
「つみたてNISA」の上限額を超えても、特別口座などで投資信託をさらに積み増してもOKです。
NISAの枠を超えた時、投資信託以外の投資対象(ETFや個別株など)を選ぶかどうかは人それぞれです。
少しでも手数料を安く
長期投資をするならば、手数料は少しでも安い方がいい!手数料が安い分だけ利益が増える!
しかし、ETFの購入は基本的には手動であるため、投資信託よりも扱いに手間がかかります。
そのため、資産運用の手間を苦としない人であれば、投資信託よりもETFを選ぶのはありです。ETFの方が基本的には手数料が安いからです。
ただ、ETF購入の手間の省略については、SBI証券の「定期買付サービス」の利用という手段もあります。
手数料の差よりも税金の影響の方が大きいから、まずはNISAの範囲で投資信託、というのは前提条件だよ。
「ETFでの運用の手間」と「手数料の安さ」、どちらを取るかは人によりますね。
そもそも手数料なんてかからないのがベストです。投資信託もETFも所有資産に対して年間○%という形で手数料が取られてしまいます。
一方、個別株への投資ならば、所有しているだけで年間○%というような手数料は発生しません!
よって、手数料を避けるのであれば、そもそもETFでも不十分ということです。
しかし、初心者が投資に慣れていくステップを考えるのであれば、個別株よりも分散の観点で運用が楽なETFを先に経験した方がよいでしょう。
配当金が欲しい人
これは後でくわしく説明します。配当金はETFをオススメしたい一番の理由です。
個人的には、投資信託だけでなくETFも利用したい理由は配当金の存在が一番大きいよ!
あこがれの配当金生活!
自分の裁量で投資したい
投資信託は定期定額投資を自動的に実行してくれます。
初心者は下手に投資判断をするよりも自動的に投資をしてくれる設定の方が無難です。これが再現性(誰がやっても同じような結果になる)にもつながります。
初心者の内はプロに資産運用を任せる方が無難ですね。
しかし、「一歩進んで自分の裁量、判断で投資をしたい」と考える人にとっては、投資信託はやることがないのでつまらない投資になります。
そこで出てくるのがETF!
良くも悪くもETFの場合は、上場している株式の購入と同様の作業が必要になります。
ETFの購入は手間にはなるけど、上場している株式と同じ感覚で売買ができるから、投資している実感が沸くね!
逆に投資・資産運用に手間暇かけたくない人には全然オススメできませんね…
自分の裁量で投資判断するから、そもそもうまく投資できなかったりもするね…
投資の世界にさらに一歩踏み込みたい人向けですね~。
ステップアップしたい人
ETFの売買は上場している個別株と同じようにできるため、将来的に投資信託だけではなく本格的な投資も経験したい人にETFは向いています。
いきなり個別株などに手を出すよりもETFを間に挟むメリットは次の通りです。
- 個別株に比べると最低投資額が安い傾向。
国内株式は最低100株単位での購入が基本。ETFなら最低1株単位での購入が多い。 - ETFは基本的に分散が効いているので、個別株よりもローリスクローリターンの傾向。
⇒個別株よりもETFの方がローリスクのため、初心者向き。
個人的に老後の資産形成を目的として投資・資産運用するならば、ETFまでの投資で十分だと思ってるよ。
投資商品の幅を広げるようなステップアップは、投資により深い興味がある人向けですね。
なぜ高配当ETFがオススメなの?
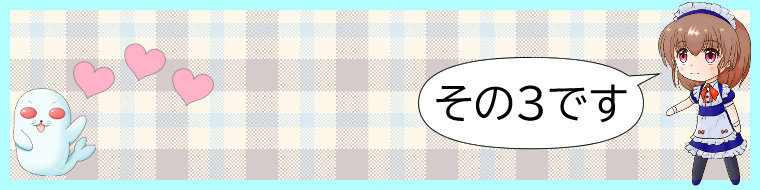
ETFの説明が長くなってしまったので、元々の目的をもう一度確認しましょう。
老後リスク回避が目的でしたね。「年金だけでは不安!」という心配をなくすためにはどうすればいいのでしょうか?
その答えのひとつが、「年金+配当金>生活費」を成立させることでしたね。

- 定年までは節約しつつ投資と貯金をがんばる。
- 定年後、年金だけでは不足する分を配当金でカバー。
資産の分類は、「高配当ETF(配当金用)+投資信託(緊急用資産)+貯金(安全資産)」で持っておくのがオススメかな。
このブログでのオススメ典型例ですね。
まあ私自身、個別株やら債券やらREITやら保険商品やらいろいろ持ってるしね…
どういう資産をどのくらいの配分で持つのかは人それぞれなので、自分なりの答えを持ちましょう!
私の場合、投資を覚えるのがもっと早かったら、保険商品はほとんど持たなかっただろうなぁ…
話が脱線しましたが、年金で不足する分を配当金でカバーしよう、というのが老後リスクを回避するための考え方ですね!
そして、配当金を得る手段として初心者にも比較的やさしいのが高配当ETFということだね!
年金の不足分を配当金以外でカバーするのはダメなの?
「年金を増やす手段は配当金だけじゃないよね?」と思った方。その通りです!
配当金以外の手段のデメリットも把握した上で、その手段を選択するのは問題ありません。
年金をカバーする手段としては、「終身でお金を得られる手段」について考えるよ!
一時金や期間限定の年金では、老後リスクのひとつである「長生きリスク」をカバーできませんからね。
年金保険はダメなの?
年金の不足をカバーしようと思った際、投資を視野に入れていない人はおそらく年金保険が思いつくのではないでしょうか?
「投資をして配当金を得ようなんてリスクが高すぎる!保険の方が安全だ!」
そういう考えもありでしょう。どこにどれだけリスクを取れるのかは人それぞれです。ただし、年金保険を使うのであれば、年金保険のデメリットをも把握しておいた方が良いでしょう。
保険という商品はそもそも平均的に損をするようにできています。そうでないと保険会社は被保険者に保険金を払えませんからね!徴収している保険金以上に支払う保険金が多いようでは商売が成立しません!
端的にいうと、平均寿命よりもそれなりに長生きしないと納めた保険料以上の年金を受け取れないと思った方がよいです。
また、保険会社も商売ですから、預けた保険金の運用利率も比較的低く設定されています(手数料が高い)。自分で資産をしっかり長期運用できる人ならば、年金保険で資産運用をする利点はあまりないですね。
もう一点、デメリットを挙げると、受取額が決まってしまっている以上、インフレに対しては弱いです。インフレで貨幣価値が落ちた分、受取額が増えればよいのですが、そんなことはないですね。
老後リスクをなくす目的ならば、長生きリスクにも対応しないといけないから、受取は終身にしたいところです。
受取を終身にすると保険料もそれだけ割高に…
支払った保険金分以上の年金を保険から受け取れる可能性もそれだけ低くなっちゃうんですよね…
資産運用が低効率であっても、平均以上に長生きできず受け取れる年金が元本割れになってしまったとしても、「老後終身で受け取れる年金がある」という安心を買いたいという人には年金保険はありです。
実は私自身、年金保険やってるんだ…投資を知る前からやってるのがあってね…
投資を始めてから、年金保険の積立金額はガクっと落としましたね~w
投資信託だけじゃダメなの?
繰り返しになりますが、投資信託だけの運用もありです!
あまり投資を深くやりたいと思ってない人、そもそも老後の資産形成のために時間を使いたくない人にとっては、投資信託だけの方が向いてるかと思います。
複利効果を考えても、配当金を受け取るよりも自動的に再投資に設定した投資信託の方が資産管理の面でも便利でしょう。
ただ、老後の資産形成を投資信託でした際、少し課題があります。それは、資産を取り崩すタイミングです。
- 老後のための資産取り崩しは自分で手動で行う必要がある。
⇒取り崩しペースを考えないといけない。 - 取り崩しペースを間違えると資産を半永久化ができなくなってしまう。
⇒判断ミスで資産が底を突いてしまう。
投資信託は運用利回りの範囲内で取り崩す限り、資産を維持しつつ半永久的にお金を取り出すことができます。これも老後の長生きリスクに耐える方法です。
投資信託の利回りは単年でみるとプラスだったりマイナスだったりするから、平均利回りを見ながら取り崩しても問題ないペースを考えないといけないね。
投資信託の利回り以内の取り崩しなら、資産は永久化できますね!
投資信託の取り崩しペースの一例として4%ルールというのがあるよ。だけど、自分が持ってる資産の平均利回りをしっかり確認して自分でペースを決めるべきだよ。
ともあれ、高齢になってから「考えて判断しないといけないこと」があるのは確かにデメリットですね…
高配当ETFは便利!
高配当ETFは、配当金が比較的高いETFです。
ETFは投資信託と違い、基本的に手動で投資しなければいけないので手間がかかります。しかし、手間がかかるゆえにメリットもあります。
【高配当ETFのメリット】
- 配当金という形で勝手にお金が入るので、老後の資産取り崩しを考える必要がない。
- 配当金なので、比較的安定した金額を定期的に受け取ることができる。
- 投資してからすぐに不労所得が入るため、投資へのモチベーションを維持しやすい。
- 配当金が実質的に利益確定になるので、運用成績マイナスの時でも精神的ショックが和らぐ。
①②は理由としてうなずけますが、③④は気持ちの問題なのでは…?
理にかなってないようだけど、投資において精神的に安心できる要素は大事だよ!実際に投資やってると実感するよ!
あぁ~…相場の上下に揺さぶられたり、成果が出ないまま時間だけ過ぎてしまったり…そういうやつですね。
「投資先を間違えることなく投資!あとは放置!」ってサッパリと自分を信じて投資して放置できれば長期投資としては問題ないんだけどね。
投資したからには成果が気になってしまうのが人間ですね…
じゃあ、高配当ETFのメリットについて、ひとつずつ掘り下げてみてみようか!
配当金なら資産の取り崩しペースを考える必要なし
初心者にとって、資産運用はなるべく「自己判断」を加えない方がうまくいくもの。
投資信託は投資や運用は自動化できるけれども、資産取り崩しは「自己判断」が必要でしたね。
一方、配当金は逆に、投資や運用は自動化できないけれども、資産の取り崩しは自己判断不要です。なぜなら、配当金という形で定期的に勝手にお金が振り込まれるからです!
老後、運用してきた資産を使う段階になって、「資産を取り崩す事なくお金を受け取れる」というのは精神的にも効果が大きいです!なぜなら人間、一度持った資産はなかなか減らしたくないと思うものだからです。
逆に、配当金の受け取りのみであれば、投資信託のリスクのように取り崩しペースを誤って資産をなくしてしまう心配もないですね。
歳を取れば、お金(数字)を考えるのもやりにくくなるから、お金を受け取るペースを自分で調整する必要がないのは大きいよ。
「受取を自動化」されている配当金は楽でいいですね!
他にも「配当金なら資産を取り崩す必要がない」のも心理的に強い!
お金の受け取りが自動化できてないと、老後になっても節約続けて貯め続けてしまったり…ありそうですね…
受け取れる配当金は比較的安定している
投資信託を自分で取り崩してお金を受け取る場合、運用成績がマイナスだと取り崩す金額に躊躇したり、逆に運用成績が良かったら取り崩す金額を多くしてしまったり、人の判断が入ると取り崩し金額に安定感がありません。いわゆる4%ルールでの取り崩しでも暴落時には取り崩し量が少なくなったりします。
一方、ETFの配当金の場合は比較的受け取れる金額が安定しやすいです。個別銘柄であれば配当金が突如ゼロになったりすることもありえますが、ETFの場合はそもそも分散されていることもあって、配当利回りが比較的安定です。暴落時でも(銘柄によりますが)配当金にまで大きな影響が出にくかったりします。
受け取れる配当金(収入)が安定しているのは、それだけで安心感につながるよ。
収入が不安定だとそれだけで不安を感じますもんね。
配当金の安定性については、やっぱり米国の高配当ETFが信頼性高いね~。(’21/7/28現在)
高配当ETFならなんでもよいというわけではない、という点は注意ですね!
オススメの高配当ETFの話はまた後でしよう!
配当金はモチベーションになる
老後の資産形成は、節約を頑張りつつ、コツコツ積み上げていくもの。そして、時間がひじょうにかかるもの。
それだけに、投資を長期間続けるにはモチベーションの維持が大事です!
投資信託の場合はコツコツ積み上げた成果をなかなか実感することがないし、頑張った結果として今の生活が楽になるわけでもありません。その状態を定年まで続けるのはなかなかの根気が必要ですよね。
しかし、配当を受け取れるETFでコツコツ積み上げた場合、配当金の入金という形で割とすぐに成果を実感することができます!たとえば年に2回か4回、配当金を受け取ることができます。
ETFへの投資をコツコツ積み上げるにしたがって、配当金の受取額は増えていく一方!今の生活が楽になっていく実感が沸くことでしょう!
30年、40年と成果を実感できないまま、節約とコツコツ投資を行うのはなかなか根性が必要だよ…
成果をすぐに実感できる配当金は、投資のモチベーションを上げてくれるというわけですね!
初めて配当金を受け取った時は少額だったけどうれしかったね~。
配当金を受け取る時期になるとワクワク感がありますね!
受け取るたびに増えていく配当金!そしてこれが不労所得というのもまた大きい!
不労所得がある安心感は凄いですね…増やしたい、不労所得!
配当金は実質的な利益確定
投資信託にしてもETFにしても、リスク資産であるがゆえに、市場の基準価額の上下は避けられません。
投資信託なら5年後に-10%の評価になっていれば、その時点の評価損益は-10%です。
しかし、配当利回り2%のETFが5年後に-10%の評価になっていたらどうでしょうか?評価損益は-10%で間違いないですが、配当金として10%分をすでに利益として受け取っているので、損失は出ていません。(分かりやすさ優先で単純にパーセントを足し引きしてます。)
配当金はある意味で、常に利益確定しながら(お金を受け取りながら)資産運用しているようなものです。よって、配当金を受け取った分を考慮すると評価損益がマイナスになっても精神的ダメージが小さく済みます。
配当金再投資している投資信託と高配当ETFの評価損益を単純に比較してよいわけではないですが、配当金による「マイナスへの感じ方」という精神面の効果は少なからずあります。
「損をした!このままではマズイのでは!?」という損から逃れようという心が資産運用・投資の判断を誤らせることが多いので、「それほどの損ではない」と思える支えになる配当金の効果は大事なのです。
評価損益の損失の考え方についてはなんだかダマされているような…?
理屈ならそもそも複利を考えて再投資が理想だし、配当金の受け取り自体は長期的には得ではないかもね。だけど、投資をするのが人間である以上、配当金の精神面の効果は無視できないよ!
少しずつ利益確定になる配当金が、リスク低減になっているという考え方をしてもよさそうですね。
まあ、リスクを低減した分、リターンも低減になるんだけどね…そもそもリターンを増やすなら、配当金は再投資だからね!
儲けた分を再投資…「倍プッシュだ!」ってやつですね!?w
リスクとリターンという視点からも、分かりやすい例えかもw
高配当ETFオススメの振り返り
高配当ETFをオススメする理由が長くなったので、改めて全体を振り返っておきましょう。
高配当ETFのオススメポイントは次の通りでしたね。
- 保険商品よりも利回りがよい。
- 保険商品と比較して、(ETFの中身によるが)インフレに対して強い。
- 半永久的に(一生涯)不労所得を得られる。
- 投資信託と異なり、老後の資産取り崩しのペースを考えなくてもよい。
- 配当金の受取額が比較的安定している。
- 投資のモチベーションを維持しやすい。
「損をする可能性が高くてもとにかく不確定要素は嫌い」という人でないなら、年金保険を利用よりも資産運用を自分でやることも視野にいれた方がよいと思うよ。
投資信託と高配当ETFは一長一短あるので、選択は人それぞれですね。
個人的には、投資信託も高配当ETFも両方やるのがよいと考えてるよ!
とにかく資産運用に手間をかけたくない、という人なら投資信託のみでも十分。投資の世界に一歩踏み込みたい、という人はETFも視野に入れるってところですね。
高配当ETFのデメリットは?
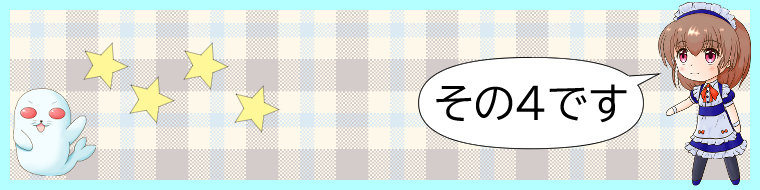
高配当ETFのメリットばかりをお伝えするのも誤解を与えてしまうので、デメリットも挙げておきます。
高配当ETFに限りませんが、金融商品についてはメリットだけを見ず、デメリットも必ず理解した上で、その金融商品が自分にとって投資する価値があるのかどうかを判断しましょう!
この記事では高配当ETFをオススメしている都合上、デメリットの記載については不足もあると思います。
そもそも私自身、高配当ETFに実際に投資するくらいには高配当ETFを評価しているからね。私がデメリットと感じてないだけで、他の人にとってはデメリットと思うことがあるかもしれないね。
お金に関しては一か所からの情報だけでなく、いろいろな視点による情報を参考にしつつ、自分で分析・判断、取捨選択するのが大事ですね。
高配当ETFの主なデメリットを先にまとめておくと、次の通りです。高配当ではなく単純なETFとしての特徴はすでに書いているので省略します。
基準価額は上がりにくい
一般的に企業が配当金を出すことは、自社への利益のストックもしくは自社への投資をせずに、株主に利益を還元する行為です。
そのため、配当金を出さない企業と比較すると、企業の成長速度は低下する傾向です。このことから、配当金を出す企業というのは自社への投資がそれほど必要がない成熟企業が多い傾向です。
よって、「高配当が出る=企業成長力は低い」という傾向があります。つまり、株価(基準価額)の成長率が低い傾向ということです。
成熟していて高い配当金を安定して出してる実績の企業というのは、要するに安定性のある企業だね。
安定性が高い分、成長性が低い傾向ってことですね。
基準価額が下落した結果の高配当に注意
高配当の判断目安として、配当利回りというものがあります。
「配当利回り=配当金÷基準価額」
⇒投資した商品の基準価額に対してもらえる配当金の割合。銀行の金利みたいなイメージ。
要するに、暴落時には基準価額が大きく下落するので、配当利回りが高く見えてしまう、ということです。こうしたことから、配当利回りが高いだけの投資先は「実は罠商品」ということもありえます。
ETFの場合、投資先はプロが選定しているし、そもそも分散も効いていることからピンポイントで罠商品を掴む可能性は低いとは思いますが、ETFにしても投資信託同様、投資先の選定には注意が必要です。
ただ単に配当利回りが高いだけの商品には要注意!
信用できる投資先なら一時的な基準価額の下落は買い場とも言えるのですけどね~。
配当が高くても資産価値が下落する一方というのは損になっちゃうからね。注意だね。
インカムゲインはプラスだけど、キャピタルゲインはマイナス!という状態ですね。トータルで損してる!
ハイリスクによる高配当に注意
どんな金融商品もリターンが高ければリスクも高いもの。これを忘れてはいけません。
ハイリスクハイリターンとハイリスクローリターンはあっても、ローリスクハイリターンはありません!
分かりやすい例は、ジャンク債を集めたETFです。デフォルトリスク(債務不履行)のリスクがある分、リターンが大きい債券を集めたETFですね。高いリスクの見返りに高いリターンが付いているのです。
ついつい、配当利回りに注目して高配当ETFを比べてしまうものだけど、ETFの中身にも注意なんだよ~。
他と比べて利回りが高いETFを見つけたら「なんで高いんだろう?」と疑問に思うことが大事ですね。
リスクを把握した上でなら一部資産をハイリターンに投資するのはありだと思うよ。ハイリターン商品に集中投資するのはオススメはしないけどね…
複利の力の低下
長期の資産運用において、複利の力は非常に大きい!1%でも高い利回りで長期間資産運用したい!
…なのだけど、配当金を受け取った分、資産の利回りは低下してしまいます。複利の力を最大限に活かすのであれば配当金の受け取りはよい手段とはいえません。
キャピタルゲイン(資産価値上昇)が5%、インカムゲイン(配当金)が2%とあったら、年利7%で資産運用できていることになります。
しかし、配当金を再投資せずに受け取った場合、複利効果があるのは5%だけになってしまいます。
配当金を再投資した場合は7%で複利が効くので、長期で資産運用することを考えると差が大きいです。
しかも、配当金は受け取る時に税金もかかるからね。投資信託で分配金なしで資産運用してもらう方が効率的ではあるね。
高配当ETFのメリットと天秤にかけて、どう考えるのか、人それぞれなところですね。
デメリットに対する注意点まとめ
どうにもならないデメリット
- キャピタルゲイン(資産価値上昇)が低い傾向
- 複利の力を最大限に活かせない
注意が必要なデメリット
- 基準価額下落が長期的に下落傾向のある商品
(配当金を得られても、基準価額のマイナスの方が大きければトータルで損) - ハイリスクゆえの高い配当利回りの商品
繰り返しになるけど、投資信託と高配当ETF、どちらもやるのが個人的にはオススメかな。
どちらにもよいところがあるし、足りないところもあるって感じですね。
複利の力を全力で矜持するのは投資信託に任せて、配当金狙いがETFってところかなー。
高配当ETFとの付き合い方
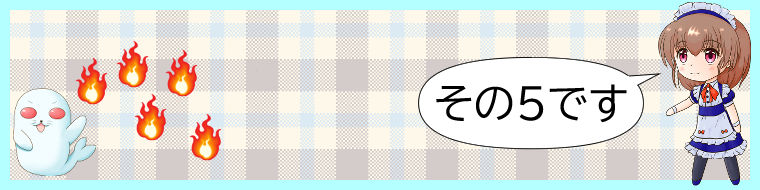
老後に向けた資産形成について、少し振り返ります。
高配当ETFの位置付けを思い出しましょう!

高配当ETFの役割
- 半永久的な年金の不足分の補助
- 資産を半永久化するために基本的に取り崩しをしない
- 老後の前から配当金を受け取れることにより、投資モチベーションの維持
- 老後の前から配当金を受け取れることにより、日々の生活向上を実感できる
投資信託の役割
- 福利の力を活かして最速で資産形成
- 老後でも基本的には取り崩しをせず、緊急用資産として維持
- 「年金+配当金」で不足の場合、平均運用利回り以下で取り崩して使う
(たとえば、4%ルールなどにより資産額は維持しつつ使う) - 緊急時、貯金(安全資産)でまかなえない場合は、取り崩して使う
基本的に老後の生活費は「年金+配当金」で考えるよ。
資産を半永久化するためにも、配当金であれば自分で資産の取り崩しペースを考えずに済むのが利点でしたね。
資産を半永久化できるというのは、経済的自由につながるし老後の長生きリスクの心配もなくなるから、大事なポイントだね!
長期保有のコツコツ投資
高配当ETFも老後の資産形成のための投資なので、投資信託同様、長期の資産運用が前提です。
必要な配当利回りは、自分の生活スタイルと投資ペースを考えて計算しておきましょう。過去の記事が役立つと思いますので、記事を置いておきます。
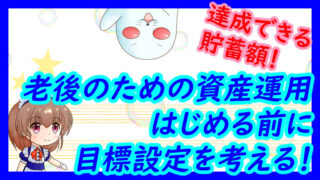
配当金を得るための資産(高配当ETF)、緊急用資産(投資信託+貯金)は分けて考えようね。
高配当ETF、投資信託は「リスク資産」ということは忘れずに!「安全資産」である貯金も大事ですよ!
投資方針ですが、高配当ETFであっても基本的には投資信託の時と同じです!投資初心者だからこそ、下手な投資判断はなるべくしない!
つまり、基本は次の2点です。
- 定期定額購入(時間分散、ドルコスト平均法)
- 投資対象は分散
定期定額購入
定期定額購入の意図は時間分散(ドルコスト平均法)によるリスク低減です。
投資信託なら金額指定で投資ができますが、ETFの購入は1株単位の購入なので定額購入はできません。だから、なるべく定額で購入を心掛けるとよいですね。
定期購入については手動になるので、こちらもなるべく定期で購入を心掛ける、といった程度です。
海外ETFだと為替も絡んでくるし、実際に基準価額を見てしまうと「あと1日待ってみよう」とか考えちゃったりするんだよね。
数字を見てしまうと考えてしまいますもんね~。投資信託だと「自動で定期定額」の投資ができるっていうのは初心者にとって本当便利ですね。
まあ、ETFはある程度、定期定額ができていればよいと思うよ。慣れてきたら、機械的ではなく考えて購入するのもよいかもしれないね。
ETFは投資信託からのステップアップとも言ってましたもんね!
投資対象は分散
投資の格言「卵はひとつのカゴに入れるな!」を愚直に守る方が、ローリスク化できます。その代わり、リターンも安定化するので、大きなリターンを生み出せる投資法ではなくなります。
老後のための資産形成はローリスクローリターンで安定堅実が基本です!
ETFは投資信託と同じようにそもそも分散されているのですが、どの範囲で分散されているのかを気にする必要があるのも投資信託と同じです。
たとえば、AIというように特定分野の範囲へ投資しているだけでは、分散範囲としては広くありません。
まあ、高配当ETFというだけで、あまり勧められるETFは幅広くないのだけどね…
高配当にこだわらなければ、投資信託のようにインデックス投資など安心感のある投資先も多いのですけどね~。
高配当ETFの運用ポイント
高配当ETFの運用ポイント、付き合い方を手順を添えてまとめておきます。
- 老後に必要な生活費と受給年金から、毎月の生活費の不足金額を考える。
- 不足額を賄うために、高配当ETFへ投資する資産額と配当利回りを考える。
- 目標とする毎月投資額と配当利回りから、購入する高配当ETFを考える。
- 購入する高配当ETFを決めたら、毎月コツコツ、長期で定期定額投資を積み上げる。
①②はすでに紹介した記事を参考にして、自分の目指す生活水準と受給年金の予定額から考えよう!
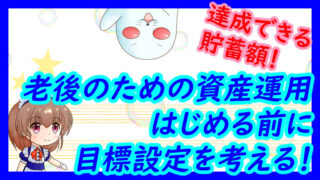
③の購入する高配当ETFは次の項でお話ですね!
④はついさっき話した通り、「定期定額(ドルコスト平均法)」「分散」を意識して、あとは景気動向や周囲の意見に流されることなく、ひたすら愚直に積立投資を続けることだね。
自動で投資してくれる投資信託と違って、ETFは「ひたすら愚直に続ける」というのが難しいんですよね~…
オススメの高配当ETF銘柄は?
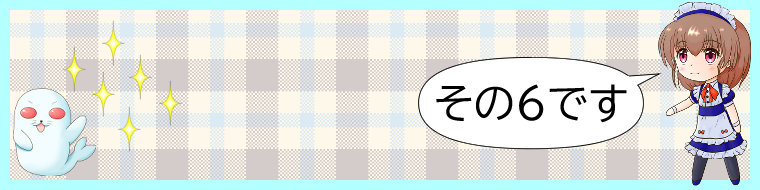
オススメの高配当ETF銘柄…といっても、人の投資に対して責任を負うことはできないので、「こういう高配当ETFがあるよ」程度にさせていただきます。
そもそも、高配当ETFという時点でわりと候補は絞られてしまいます。
高配当ETFを選ぶ上でのかんたんなポイントを押さえておきましょう。
高配当ETFを求めると、行き着く先は米国ETFになる!(’21/7/30時点)
国内ETFはダメなのですか?
長期で安定・右肩上がり、というのがちょっと難しいね…
とはいえ、米国、米ドル一極集中というのも…?
投資の世界で米国は最大手だからね。米国一強と言われるくらいで、米国集中を投資方針にしてる人もいるよ。 (’21/7/30時点)
どこまで分散を考えるのかは人それぞれですね。
具体的な銘柄は?
代表的な高配当ETFを紹介しておきます。オススメというよりも一例としてみてください。
しつこいけど、投資は自己責任!
私は人の投資に責任を負えませんので、そこはご承知おきください。
- VYM (バンガード・米国高配当株式ETF)
運用会社はバンガード。高配当ETFの中ではローリスクローリターンの傾向。 - HDV (iシェアーズ コア米国高配当株ETF)
運用会社はブラックロック。 - SPYD (SPDR ポートフォリオS&P500 高配当株式ETF)
運用会社はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。高配当ETFの中では比較的ハイリスクハイリターンの傾向。
これら「VYM」「HDV」「SPYD」は、高配当株でネット検索すば情報は多数出てきます。詳しい説明は他サイトにお任せします。
私はどうしているのか、ということを参考に載せておきます。
個人的には上記した高配当株式のETFの他にも、投資商品の多様化のため、債券ETFやREIT ETFも少し投資しています。基本は配当利回りを高めるために、株式ETFが中心ですが。
また、日本人である以上、ドルだけではなく円資産もある程度は持っておきたい(貨幣の分散)ため、キャピタルゲインは期待できないですが、国内ETFも少し持っています。
自分にあった投資スタイルを自ら考えよう!投資は自己責任!
リスクとリターンをどれだけ取るのかは、本当に人それぞれ。リスク許容度によって変わりますね。
まとめ:高配当ETFの振り返り
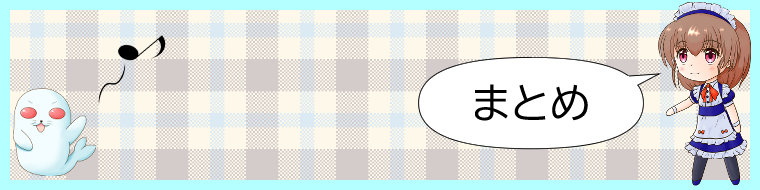
最後に高配当ETFについて全体のおさらいをしましょう!
投資信託には投資信託の、高配当ETFには高配当ETFの、よいところ、期待する役割がそれぞれあるよ!
高配当ETFだけをオススメするわけではないということですね!
そもそも分散の視点では株式中心の財産も偏ってるし、結局は安全資産(貯金)も含めて全体の資産割合が大事だね。
リスク資産(投資)は余裕資金の範囲にしておきましょう!
投資は自己責任です!
投資は人に流されてなんとなくするものではありません。投資にはリスクがあることを理解した上で、投資をする必要性・目的がある場合に、はじめて投資・資産運用という選択肢が出てくるものと考えます。
投資ペースも人に流されるものではありません。自分のペースを守って安全資産を確保した上で余裕資金の範囲で投資を行うようにしましょう。
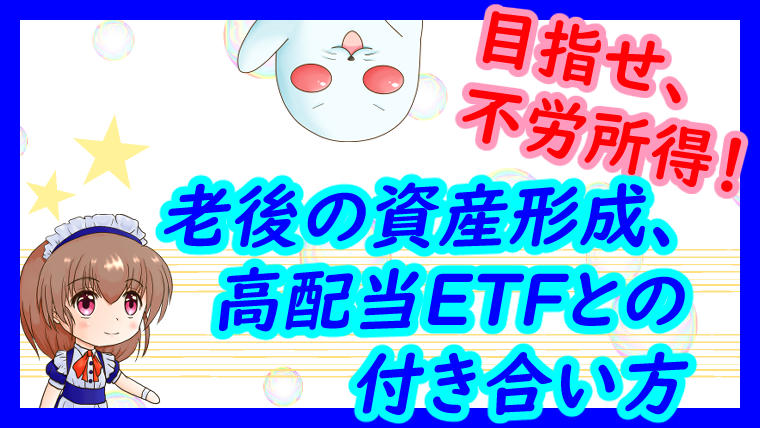


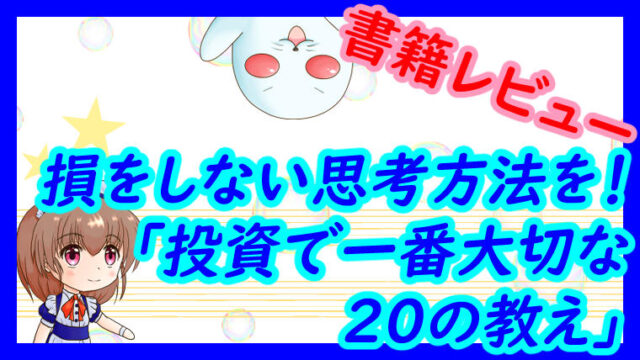
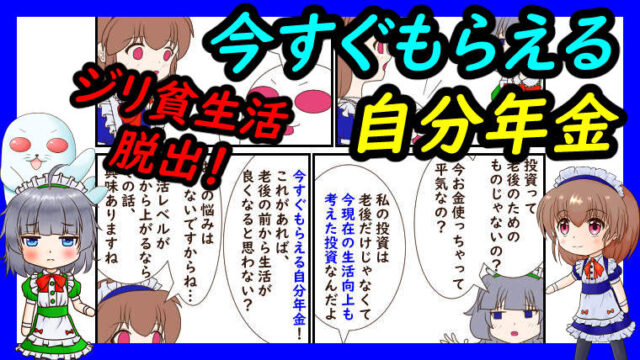
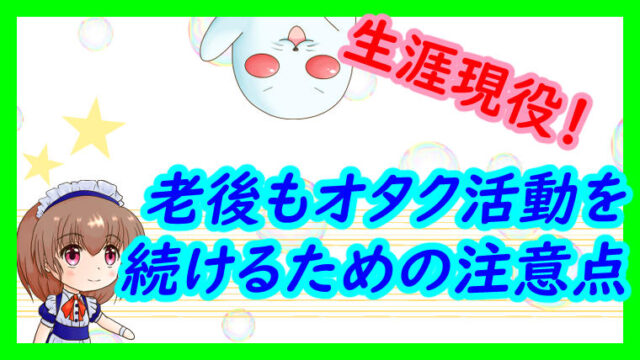
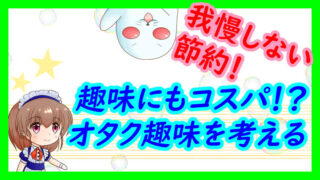

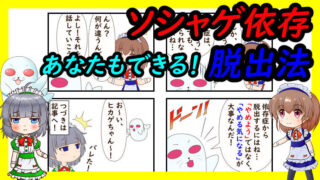




高配当ETFはインカムゲイン(配当金のような収益)が望める分、キャピタルゲイン(資産価値)の上昇は望みにくい傾向。