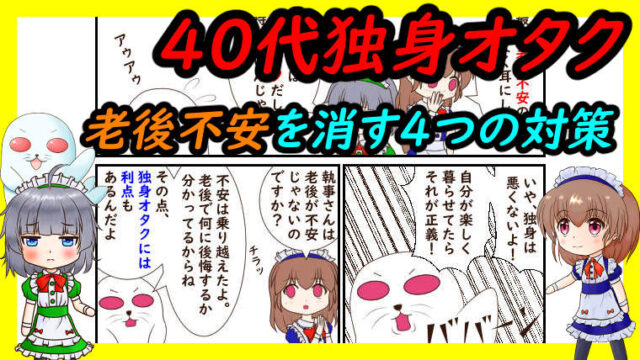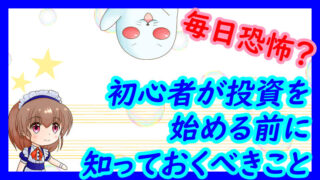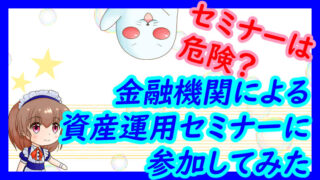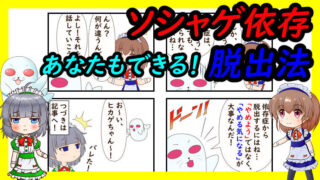「失明しちゃえばよかったのに!」
私はいじめ被害経験者です…
冒頭の一言は、いじめを受けていた頃に言われた言葉ですね。
いじめを乗り越えて大人になった今でも忘れられないよ…
いじめを受けた側は一生ものの心の傷として残るんですよね…
世間でいじめやパワハラのニュースを見るたび、昔を思い出していたたまれない気持ちになります。いじめは子供に対するものだけではなく、大人になってもパワハラと言葉を変えて発生します。
このブログの趣旨とは全然違う話題ですが、いじめを乗り越え大人になった今、少しでもいじめをなくせる社会風土作りの役に立つことはないかと思い、ちょっとしたキッカケから記事にすることにしました。
世間で言われている事は「その通り」と思うものもあれば、「実際にいじめを受けた人だったらそんなこと言えないよ」と思うような意見、いろいろあります。
いろいろな立場の人がいるから、いろいろな意見が出るのは当たり前。
じゃあ、いじめの本当の原因ってなんなの?
いじめる側が悪いのか?いじめられる側が悪いのか?
私はどちらも本質とは違うように思えています。私は現在、製造業に携わっています。その製造業の立場から、いじめの原因と対策について、できる限り理論的に考えてた結果を紹介します。
できる限り「理論的に」を心掛けていますが、私自身がいじめ被害経験者なので、無意識に被害者目線になってしまうところもあるかもしれません。そこはご容赦ください。
- いじめの根本原因を取り除くのは困難。
- いじめは発生するものという前提での対策が必要。
- モラル・ルールと罰則(抑止力)の用意と周知が必要。
- いじめる側、いじめる側ではなく、より上位の管理者の采配が重要。
いじめは自然現象
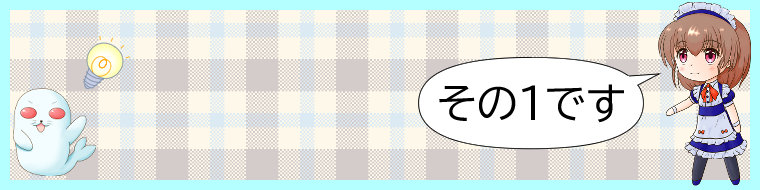
いじめを解決するにはまず原因の追究です。そもそもいじめはなぜ発生するのか?
私の考えでは、いじめは自然現象です。発生すべくして起き、避けられないものとして考えています。
いきなり、身も蓋もない結論ですね…
そんなこといったら、「いじめ」はなくせない!どうすればいいんだ~!?
いじめは発生するもの、という考え方は、製造業ならば「ヒューマンエラー」に相当するのではないでしょうか。
製造業はこの「ヒューマンエラー」は発生する前提として、いかにして「ヒューマンエラー」を防止するか、もし発生したとしてもそれを食い止めるための防波堤を作っています。
この記事では、製造業の観点から「いじめ」は発生するものとして、その「いじめ」をいかに抑制し、防止し、発見するのか、について考えています。
さて、少し根本的なところから「いじめ」について考えてみます。
社会は集団を作り、集団は格差を作る
まず、我々は社会の中で生きています。
社会の中では必ず集団が作られます。何をするにも集団は効率的ですからね。
集団というと、パッと何のことか想像がつきにくいかもしれませんが、例えば、学校、会社などです。
もう少し細かくすると、友達でのコミュニティだったり、学校の部活、サークルだったり、会社の中の組織、グループだったり。家族もひとつの集団ですね。
人間社会の中で生きている以上、何かしらの集団に属しているのが通常かと思います。
そして、この集団の中にはリーダーがいるものです。集団は属している人の中でピラミッド構造を取るのが自然の流れですね。リーダーがいた方が集団を効率的に運用できるからです。
こうしたお話は人間に限った事ではないですよね。
例えば、猿。猿にも社会があって、ボス猿が存在しますね。動物の群れまで考えると、もはや集団で生きるのは知恵ある生物の習性ともいえるでしょう。
そして、集団ができれば、その中で平均以上の人、以下の人が必ず存在します。
人は十人十色。集団の中でそれぞれ能力的な問題等で上下の評価は必ずできます。どんなに優秀な人が集まっている集団であっても、その中で平均を取れば、必ず平均以上、以下の人が出るのです。
集団ができれば、集団の中で格差が発生するのは避けられません。
社会があって、集団ができて、その中で格差ができる、という構造は、社会の枠組みに所属する限り避けられないものです。
集団の上に立つには、努力するか、他者を蹴落とすか
集団ができれば、必ず格差ができる。
その格差の中で生きる人にとって、上に見られたい、という心理は少なからず出るものです。人より上にいる、という認識は自己肯定にもつながり人からも称賛され気持ちのよいものです。
全員が向上心を持ち、努力して実力で上に上がれるような人であれば、何も問題はないです。しかし、多くの人間は「できる限り楽をしたい」という怠惰な感情から逃れられません。
そして、欲望、虚栄心、嫉妬心…時に集団の中で上に立ちたいという感情は時に悪感情から生まれます。
怠惰と悪感情が重なると、上に上がる方法として思いつくのが、自分を上げる事ではなく、人を落とす事です。人を落とす事で相対的に自分が上になる事を考えます。
これが「いじめ」が発生する要因のひとつだと考えています。
「要因のひとつ」と書いたのは、もっと短絡的に発生する要因もあるからです。
それは「快楽」です。ストレス発散も快楽のひとつと考えています。
いじめの根本原因を取り除くことは困難
ともあれ、「いじめ」は、誰しもがもつ感情が根っこにあるものだと私は考えています。人である以上、感情からは逃れられません。ゆえに、「いじめ」の根本原因を取り除くことは無理だ、という考えに至っています。
猿の集団でもいじめはあるっていうよね…
もはや、いじめは本能のレベルなのでは…?
いじめの根本が人の感情であり、本能であるというのであれば、もうどうしようもないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
人間は理性的な生き物です。「本能」を抑えて行動できるのが人間です。「本能」を抑える存在、それが「理性」です。
では、「理性」を働かせるために必要なものはなんでしょうか?
社会に必要なふたつの物…ルールとモラル
人間社会を作っている大事な要素として、「ルール」と「モラル」があると考えています。ルールは法律と言い換えてもよいです。モラルはマナーや常識といってもよいかもしれませんね。
人間が「理性的な行動」ができるのは「ルール」「モラル」が基本になっているはずです。
「ルール」も「モラル」もなかったらどうなる?
それはもはや、人間社会ではないのでは?
…世紀末の世の中の始まりですねw
窃盗しようが詐欺をしようが悪いことではありません。捕まりません。
そんな世界で真面目に働く人がどれだけいるでしょうか…?
そんな世界だったら、まじめに働いても給料なんて保証されません。誰しもが自分勝手に生きるでしょう。
「理性」による遠慮も制限も必要ない、むしろそんなことを考えていたら損をする!「本能」だけで生きることになるのです!
いじめには、「ルール」の整備と「モラル」の教育が必要!
そして「ルール」「モラル」を守るのが人間社会で生きるということ!
幕間:いじめる側が悪い?いじめられる側が悪い?
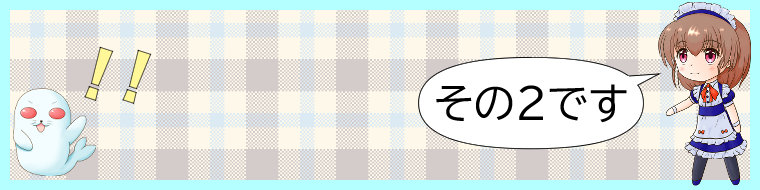
ここまで読んでくれた人なら、根本的に良し悪しを語るポイントはそこではないのでは?と思ってくれるかもしれません。私自身、そう考えています。
いじめられ経験がある私としては「いじめる側が悪い」の一択と言いたいところなのですけどね…
「いじめられる側が悪い」という意見には個人的には猛反発したいですね。
個人的な感情は置いておいて…いじめを対策しようと中立視点で議論するならば、どちらが悪いのか、という議論は論点が違うと考えています。
とりあえず、論点の話は置いておいて、「いじめ」についての一例を考えてみましょう。
A君とB君がいました。部屋の角君がいました。部屋のすみで縮こまっていたB君を見つけたA君は、A君を睨んだかと思ったら唐突にB君に嚙みつきました!
あなたは、A君が悪いと思いますか?B君が悪いと思いますか?
・・・
・・
・
答えは考え付いたでしょうか?
この問題に答えはありません。
「実はA君は猫で、B君はネズミでした!A君はあなたの部屋に住み着いたネズミを退治したのです!」
こう聞いたら、悪いのは害獣のネズミ、と考えるのではないでしょうか?
「…なのだけど、B君はあなたの飼っていたハムスターでA君はあなたの部屋に侵入した野良猫です。」
こう聞いたら、悪いのは野良猫だ、と考えるのではないでしょうか?
つまり、善悪を決めるのは、その人の中の「ルール」によるものなのですよね。
世間的な「ルール」いわゆる法律が浸透して適用されれば、誰もが心の中に同じ「ルール」を持ちますよね。
もし「ルール」を共有する環境がなければ、個々人がどうその状況を捉えたのか、で良し悪しの判断なんて変わってしまいます。
人それぞれ、自分なりの正義を持っているものですよね…
「自分の正義」と「他人の正義」が必ずしも一致しないのが、世の中の難しいところだね…
いじめが起きる前提で防止するための考え方
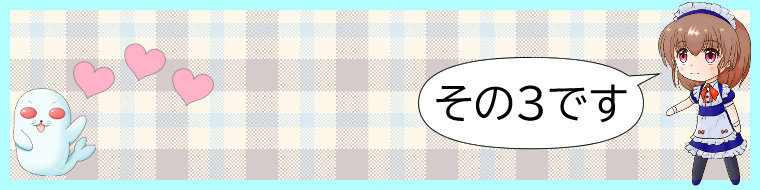
ここまでで、「いじめ」は自然発生するもの、それを抑制するのが「ルール」「モラル」というお話をしてきました。
いよいよ、製造業の視点で、自然発生するものとして考える「ヒューマンエラー」をどう抑制するのかを考えていきましょう。
「ヒューマンエラー」とは字のごとく、人によるミスです。
これは様々な要因で発生します。見落としだったり、ルール不遵守だったり、やり方を間違えてしまったり…こうした「ヒューマンエラー」はすぐに製品の「不良」につながります。
製造工程で不良を発生せないための考え方として「発生防止」と「流出防止」があります。また、発生した「不良」について、二度と同じ原因で不良を発生させないために「再発防止」という考えがあります。
「発生防止」「流出防止」「再発防止」はどれも発生した問題について考える、という共通点があります。しかし、そもそも問題は発生しないにこしたことはありません。そこで出てくるのが「未然防止」です。
では、「いじめ」を防止するためにはどうすればよいのかを考えてみましょう。
結論は、「ルール」と「モラル」、そのための「教育」です。
「教育」が人を作るというのは全然過言ではないですよね。
発生防止
いじめが発生する原因を考えます。ここでは「いじめの発生」を「加害者がいじめをしようと考え、実行すること」と定義します。
いじめは自然現象と書きました。「いじめをしよう」と考えてしまうのは、ザックリ分けるとこんな感じでしょうか。
いじめをしようと考えるポイント(加害者視点)
- 自分を集団の中で上の存在と認知されたいため
- 自分より弱いものを作ることで安心感を得るため
- 自分自身の快楽のため
いじめを実行しようと考えるポイント(加害者視点)
- いじめをしても自分に実害はない
- いじめをすることによる自分への実害を認識できていない
- いじめを悪いことだと考えていない
- ストレス等で正常な判断ができなくなっている
いじめはそもそも加害者がいなければ被害者も発生しません。よって、発生原因は加害者視点しかありません。
端的に言ってしまえば、加害者側の「自分勝手な感情」「正常なリスク判断ができない」ことが原因ですね。
「感情」を抑制するのは「理性」です。「理性」により「正常なリスク判断」を下せます。「正常なリスク判断」をするためには「教育」が必要です。
また、当然ではあるけれど、「他者」がいるからこそ「いじめ」は成立します。この観点では「集団が存在しなければいじめは発生しない」といえますが、この解決方法は社会自体を否定してしまうので、この論点は省きます。
これらのことから、「いじめ発生」を防止する手段を考えると…?
いじめ発生の防止
- 何がいじめになるのかを知るための教育
- いじめが悪いことだと認識できるための教育
- いじめをすることによる自分に跳ね返るリスク教育
教育により「ルール」と「モラル」を身に付ける!
結局は、犯罪を防止するための法整備と同じ!
悪いことを悪いと認識させ、悪いことをすれば報いがある、という当たり前のことを学ぶ!
こうした「教育」こそが「いじめ」を発生させない抑止力になります!
現状、いじめに対する法整備が甘いことが問題のひとつですね…(執筆時、’21/6/12)
悪いことをしても報いがないのであれば、悪いことを考え実行する人は後を絶たなくなるよね…
流出防止
次に、いじめが流出する原因を考えます。ここでは「いじめの流出」を「いじめが発覚せずに継続されること」と定義します。
では、いじめが止められることなく継続されてしまう原因を考えてみましょう。ポイントはこんなところでしょう。
いじめを見ても止めようとしない(周囲視点)
- いじめを止めると、今度は自分がいじめの標的になってしまうかもしれない
- そもそも人に無関心、自分に害がなければよい
- いじめを止める行為そのものが面倒くさい
いじめの仲間に加わってしまう(周囲視点)
- 集団心理。場に流されて、いじめに直接参加せずとも同調してしまう
- 「この人はいじめてもよい人だ」と勘違いしてしまう
いじめられていることに我慢してしまう(被害者視点)
- 人に助けをもとめることに遠慮してしまう、強がってしまう
- いじめられている事を告白する勇気が出ない
- いじめられている事を受け入れてしまい、抜け出す行動が取れなくなる
いじめに気づけない(保護者、管理者視点)
- いじめ加害者も被害者もいじめを隠す傾向がある
- いじめに対するアンテナがそもそも低い、発見努力の不足
- SNS等、第三者が発見困難なコミュニケーションの存在
- 忙しくて時間が割けない、いじめの可能性を考えない
- 表面上うまくいっているのであれば、いじめの存在を心理的に否定してしまう
最初は特定のひとりからいじめを受けていたのに、それが広がっていろいろな人からいじめを受けるようになる絶望感…
精神的な孤立感も加速、居場所もなくなり最悪ですね…
基本的にいじめは休み時間の出来事だったり校外でのできごとだから、意外と教師とかは気付かないんですよね…
SNS上だと、保護者ですら気付くのは困難ですね…
「発生」は加害者のみによるものでしたが、「流出」についてはいろいろな視点があります。それにも関わらず、どの視点も機能しづらいです。
ポイントになるのは、各視点での行動のための心理的ハードルを下げることでしょう。
いじめ流出の防止
- 報告者の匿名性を保証したいじめ報告窓口を作る
- いじめ発見者が報告をする気になるルール・環境を作る
(たとえば、独占禁止法の通報と同じ考え方。通報者にメリットがあれば、進んで通報をするようになる。会社であれば報告に対する報奨も考えらえるが、学校では何らかの加点は困難か。) - 保護者、管理者がいじめに向き合う時間を作る
- いじめが発生していないか定期的にチェックする仕組み作り
(たとえば、月に一回、クラス全体で匿名性を約束して「自分のクラスでいじめがあると思う。YES/NO」のようなアンケート。個人名を聞かない方が、アンケート回答のハードルが低い。)
いじめ発生を通報させるための仕組み作りが大事!
加害者、被害者がともに隠そうとしてしまうと、発見は非常に困難!隠された事を調査する仕組み、通報させる仕組みの整備は有効と考えます!
保護者、管理者による調査は、行き過ぎると個々人の監視になってしまうので難しさはありますね。SNSを第三者にチェックされるとか監視カメラとか。
「見られているかもしれない」という気持ちがあるだけでも大きな抑止力にはなるのだけどね。
一方で周囲の人は、たとえいじめの仲間に加わることがなくても見て見ぬふりというのはよくある行動ですよね?
周囲の人たちに一歩、手間をかけて行動してもらうことができれば、いじめの発覚率は上がるのだろうけどね。
「通報しやすく、通報をするメリット」の仕組みが作れれば効果は高そうですね。
「発生防止」と「流出防止」は1セット。まずは「発生」を抑え込むのが大事。万一「発生」してしまったための防波堤として「流出防止」があります。
いじめは加害者によって「発生」します。その意味で、「被害者」と「加害者」どちらが問題の発端かというと私個人は「加害者」側の動向を重要視するべきだと考えています。
ただし、私の最終的な結論は「加害者」「被害者」よりも、集団の環境を作る「管理者」がいじめをなくすためのキーパーソンだと考えています。
再発防止
「発生防止」にしても「流出防止」にしても、問題が発生してから、原因と対策を考えるものです。これらの原因・対策を考えることは「再発防止」につながります。
集団Aで発生した問題の「発生・流出防止」の対応が完璧に完了した場合、集団Aでは同じ問題は起きないでしょう。しかし、集団Bでは同じ問題が起きるかもしれません。対策は集団Aでしかされていないのですから。
「再発防止」は過去の問題・トラブルから学び、二度と同じ問題を起こさないようにするためのものです。重要なのは過去のトラブルを学び忘れないこと。そして、知識と経験を他の集団と共有することです。
製造業でいうところの「過去トラ」(過去トラブル)と「横展」(横展開・水平展開)ですね。
過去のトラブルを集積し、定期的にそれらを思い出すように教育する。自分のところで起こった問題を他の部署にも展開して共有する。過去のトラブルとその対策実施は会社の財産です。
過ちは繰り返すな!
過ちを繰り返さないために歴史を学ぶのが重要なのと同じですね。過去を知ることがどれだけ大事なことか…
歴史を学ばない、歴史を間違って伝承する…そんなことになったら、「学ばない人類」を体現してしまうね。
いじめやパワハラ、という問題に関しては社会問題といえるレベルのものですが、その問題の詳細や対策実施など、あまり集団(学校や会社)の枠を超えて共有されるものではありませんよね。
いじめ・パワハラについては、個人のプライバシー問題もあるし、学校や会社のイメージダウンにもつながるため、積極的に詳細情報共有される分野ではない、という状況ではないかと思います。特に加害者が未成年の場合はむしろ情報は秘匿されますよね。
いじめをなくすために「発生防止」「流出防止」「再発防止」の考え方は役立つでしょうけれど、今の社会情勢的にこうした製造業での考え方を適用するのは難しそうです。
加害者、被害者どうこうではなく、「ルール」「モラル」といった環境を変えることがいじめ対策の根本である、と私が考える理由のひとつでもあります。
未然防止
「発生防止」「流出防止」「再発防止」…
どれも問題を繰り返さないという点で大事な活動です。
しかし、どれも「事後対策」という点が欠点です。問題が起きてから、その問題について考える、という活動ですからね。
これではまるでモグラたたきのようです。
Aという問題が起きたら、今度は別のBという問題が…!すべての問題をつぶしこむまでに、どれだけのトラブルが発生してしまうのでしょう?
そのため、「未然防止」という考え方も重要です。
トラブルが起きる前に、「こういうトラブルが発生するかも?」と検討する活動ですね。
多くの人がこういう考えを常日頃からしているはずです。例えば、自動車教習所でやるような「危険予知トレーニング」(KYT)。
視界の限られている住宅街の中、車を運転しているとします。そして、十字路に差し掛かりました。塀があって十字路左右の状況は見えません。
どんな危険が考えられますか?
十字路から人や車の飛び出しの危険!?
こんな感じで、実際に事故を経験せずとも、危険を予測できますよね。
人間は危険を予知できるのです!
「かもしれない運転」とかもよく言われる言葉ですね。未来に発生するかもしれない危険を予測しながら活動することは、自分の身を守る上で重要です!
危険予知トレーニング(KYT)は、製造現場などでは特に大事ですね。
しかし、そもそも危険が発生しない現場にすることも重要です。そこで出てくるのが工程FMEAです。設計FMEAというのもありますね。
FMEAは、不良品を作らないための検討ツールとして非常に重要で有名な手法です。これは次の項で掘り下げます。
いじめやパワハラについても、未然防止の観点でできることがあるんじゃないかな?
怪しい雰囲気を感じた時に、学校なら先生から生徒への声かけ、会社なら上司や先輩から部下への声かけ。これだけでも環境改善につながりそうですね。
会社ではコミュニケーションを密に、という活動があったり、パワハラ密告の窓口があったりする会社も徐々に増えてきているのではないかな。
学校では三者面談とかがコミュニケーションの機会になるでしょうか?
親がいると話しにくいこともあるかもしれないので、先生と生徒だけの場というのも大事かもしれないね。
もちろん、先生側が聞く耳を持っているタイプでないとダメなですけどね…
ちなみに、私がいじめ被害を脱するキッカケになったのは三者面談の時だったよ。
その事例はいじめ発生事後なので、この記事の定義では、未然防止ではなくて流出防止にあたりますね。
いじめのFMEA
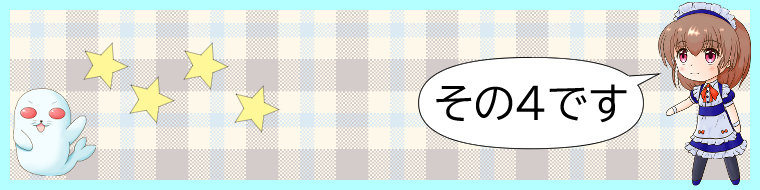
「未然防止」をするためには、トラブルが起きそうなポイントは、トラブルが起きる前に発生原因、流出原因を潰しておくことです。
FMEAは、トラブルになりそうなポイントを抽出して、現実に発生する可能性が十分考えられるトラブルに対して事前に対策を講じるためのツールです。
FMEAは、Failure Mode and Effects Analysisの略です。日本語では「故障モード影響解析」と呼ばれています。
FMEAを簡単に部分的に説明しておきます。
それ、文字で説明しても全く伝わらないやつですよ!w (読み飛ばそう…
- ある製品のある「機能」について考える。
- その機能を失う「故障」を考える。
- その故障が発生することによるリスクを「危険度」として点数付けする。
- その故障が発生する「原因」を考える。
- その原因が発生する頻度を「発生度」として点数付けする。
- その原因を発見できる頻度を「検知度」として点数付けする。
- 「危険度」「発生度」「検知度」を総合して、高得点を獲得した「故障」については重大トラブルとして対策を講じる。
- 対策を講じた結果、「危険度」「発生土」「検知度」の点数付けが下がれば、その「故障」については懸念がなくなったと考える。
まあ、説明を書いてみたものの分かりにくいよね…w
例題を見た方が手っ取り早いです!
「横断歩道」について考える。
- 機能:人が安全に車道を横断する。
- 故障:停電により信号が使えない
- 危険度:大 ※交通事故で人の命に関わる!
- 原因:大型台風
- 発生度:小 ※頻繁ではないがたびたび発生
- 検知度:小 ※停電で信号が使えない状態は見れば気づく
「危険度」「発生度」「検知度」は問題がある時に高得点を付ける。よって、検知度は気付きにくいほど高得点。
つづけて、本題の「いじめ」についてFMEAを考えてみましょう!
「いじめ」は社会生活における「故障」ですね!
- 機能:社会生活
- 故障:いじめ
- 原因:加害者要因、被害者要因、周囲要因、管理者要因
加害者要因の原因
自分を上位の存在と示す優越感、ストレス発散、快楽の享受
被害者要因
被害を隠してしまう、人に伝える勇気がでない、我慢してしまう
周囲要因
自分がいじめられないようにいじめに加わってしまう、いじめを見ても見ぬふりをする
管理者要因
いじめに気づけない、いじめに関わるのが面倒くさい、自分の管理下でいじめが起きるとは思っていない(いじめは他人事という意識がある)
次に、危険度、発生度、検知度について考えるよ。
現実問題、これらの点数が高くて、いじめは発生すべくして発生している、というのが今の社会環境ですよね…
危険度
いじめをしようと考え、実行するのは加害者によるものです。
いじめに我慢するのは、被害者です。
いじめを意図的にでもそうでなににしても放置してしまうのは周囲の人や管理者によるものです。
加害者視点
いじめの加害者にとって、いじめが発覚した場合、どれだけの被害を被るでしょうか?未成年の場合は、社会的に保護されることもあって、致命的なダメージとまではいかないことが多いのではないかと思います。
私の実体験では、結局教師が間に立ち加害者側を説き伏せた結果、加害者からは「もういじめはやめたよ」の一言で終わりました。謝罪の言葉はありませんでした。
謝罪の言葉はありませんでしたね。
当時の私としては、いじめがなくなることが重要だったから、謝罪とかもうどうでもよいとは思ってたけどね。
いじめを受けた被害者の状況にもよるでしょうけれど、未成年者にとって、いじめの加害者になるということは低リスクの行為になっているのではないでしょうか。
一方、大人のいじめ、いわゆる○○ハラスメント(パワハラなど)の場合はどうでしょうか?
社会人がこんなことをして発覚したら、減給・降格待ったなしです。場合によっては解雇もありえます。社会的に致命的です。
大人にとって、いじめの加害者になるということは致命的なダメージといえるでしょう。
それでも、○○ハラスメントというものが発生するのは、加害者側がパワハラなどを行っているという自覚がないためでしょう。
自覚がなければ、自分の行動がリスクに結びつくこともありません。
- いじめを行うリスクは、加害者が未成年か社会人かで大きく異なる。未成年の場合はいじめを行うことは比較的低リスクになってしまっている。
- いじめにせよパワハラにせよ、加害者側はいじめを行っているという意識がない場合がある。
被害者視点
被害者にとって、いじめを受け続けるのはリスクでしかありません。
しかし、いじめをやめさせるための行動はいじめを受け続けるよりもハイリスクな行為と認識をしてしまい、その結果、いじめを我慢し続ける、ということになりがちです。
要するに、他者にいじめを訴えかけるのが怖いんだ…
下手なことを言うと、「もっといじめがひどくなってしまうのではないか」って考えたりもしちゃいますよね。
他者に訴えたとしても「即行動で」助けてくれると信じられるほどの人が周囲にいない、というのもあるかもしれないね…
「即行動で」助けてくれないと、どこからか「先生に言いつけたな!」と伝え聞いた加害者側からのいじめがエスカレートするかもしれない、という怖さが…
いじめを我慢し続けると、それが日常と化して無気力化していきます。ますます自分の殻に閉じこもるようになります。精神的にも追い詰められて正常な判断もできなくなります。
いじめがエスカレートすれば、もはやいじめを我慢するよりも自分の人生を終わらせる方が楽な選択肢になりかねません。
いじめの恐怖よりも人生を終わらせる恐怖の方が低く感じてしまうのです。自らの命を断つよりも怖いいじめ。もはや拷問です。
- 「いじめを我慢するリスク」よりも「いじめをなくすための行動」の方がハイリスクに感じてしまう。
- 精神的に追い詰められた結果、正常なリスク判断ができなくなる。
- 結果的に我慢し続けてしまう。
周囲視点
いじめを目の前にした時、「被害者を助ける」という正義感よりも「巻き込まれなくない」という保身の方が優位にたってしまいがちです。
ひと昔前ならともかく、現代社会において、下手な正義感は損をする、という認識が強くなっている、という感覚があります。
これは人との接点が減っていることの影響が強いと思います。
例えば、身近な人、例えば親しい友人だったり家族だったりが被害を被れば、他人事ではなく自分事として問題解決に協力的な姿勢を取る人が多いと思います。
しかし、人との接点が薄い場合は「自分の身内」と判断する範囲が狭くなります。この結果が、「人に無関心」です。
他人を助けるためにリスクを負いたいと思う人は少ないでしょう。
子供の頃に親から受けた教育で、「人との助け合い」を教えられる人も少なくなってるのではないでしょうか?
Give & Takeが成り立たないと「人との助け合い」も成立しませんよね。今となっては、知らない人にも声をかけて「助け合い」ができる人は少数派ですよね。
「知らない人に声をかけられてもついていくな」というのは少なくとも私の世代ではよく言われてたね。
「他人を疑え」を基本姿勢にしないといけない、というのも世知辛い世の中です…
それだけ、詐欺とかが横行してしまっているのだよね…
いじめの現場を目の当たりにした時には、まさに「人に無関心」が働いてしまう瞬間かと思います。
「正義感」よりも「保身」が先に立てば、「自分がいじめの対象にならないように、自分もいじめに加わる」「関わらない、何もしない、無視をする」のどちらかでしょう。
- 周囲にとって、いじめに対して何かをする方がハイリスク。
- 「加害者の仲間になる」もしくは「何もしない」ことがローリスク。
管理者視点
真っ当な認識であれば、いじめを発見さえできたならば、いじめを放置することがハイリスクだと認識できます。しかし、短期視点と長期視点でリスクの感じ方も変わります。
長期視点でみた場合、いじめが世間的に発覚するまでは「ほぼノーリスク」です。
発覚した場合は、学校の教師の立場でも会社の上司の立場でも、現在の地位が揺るがされるほどハイリスクです。
短期視点でみた場合、いじめに対してアクションを取る方がハイリスクになりがちです。
学校の教師にしても会社の上司にしても、通常、仕事に追われて何か追加で活動するような時間の確保が困難です。
また、教師の場合は生徒の親との折衝も出てくるので、いじめに対してアクションを取ることはよりハードルが高くなります。
今の世の中、親側の対応にも問題が出ることもありそうです。
会社の上司としても、会社の調査、説明・報告など、余計な業務が増えるわけです。
長期的にはいじめが発覚するまでは「ノーリスク」、短期的にはいじめに対する対応に動くことが「ハイリスク」ということから、管理者視点でも、いじめ問題を先延ばしにしてしまいかねない環境です。
- いじめ問題は、責任ある立場の人にとってはハイリスクな問題。しかし、発覚しなければノーリスク。
- いじめを対処するだけの時間的、精神的余裕がない管理者が多い。
発生度
いじめは本能的なものであって、発生する前提で考える必要がある、と説明してきました。その点では、発生度は「高い」といえるでしょう。
しかし、高い発生度を抑えることはできると思っています。
繰り返しになりますが「ルール」「モラル」などによる社会的抑止力もしくは精神的抑止力(理性)を高めることです。
たとえば、犯罪といわれるような事柄。
傷害事件は起こりにくく、万引きは起こりやすい。危険度とも重なってしまうけれど、人間は損得勘定とリスクの高低を見積もって、有利だと考える選択肢を選びます。
いじめの発生を抑えるためには、そもそもいじめはハイリスクローリターンだと思わせる必要があり、そのための手段が「ルール」「モラル」と考えています。法律とマナーといってもよいです。
とても個人的な意見を言ってしまうと、「抑止力」というのはあまり好きではないんだよ…
根本的な原因を解決できないので、力で押さえつけるようなものですからね。
ひとつ例を挙げるならば、「戦争」だね。人間の本能ともいえるのか、戦争はよくないとみんなが考えつつも歴史上で繰り返されているよね…
戦争を回避するために軍事力を持たなければならないのは、まさに「抑止力」という考えですね。
いじめにしても「発生原因」を取り除くのが困難だからこそ、「抑止力」の考え方が必要になってしまうかな…
- いじめの発生原因を根本的に取り除くのは困難。
- 抑止力を持って、いじめを行うことは損である、という認識を持たせることがひとつの手段。
- いじめ被害の痛みを学ぶことも抑止力になる。
検知度
いかにいじめが世間的に問題視されるようになるか。つまり、いかにバレやすいか、ですね。
集団内で起きている問題であれば、その集団内ではいじめは周知でしょう。
それが集団外にバレるかどうか、という視点です。
「バレるとマズイ」「バレたら大問題」という状況下であれば、「バレやすい」というのは相当リスクが高いことになります。
いじめが発覚しやすい、バレやすい環境を作ることは非常に重要です。
加害者視点
いじめ自体、他者がいて成り立つ行為なので、少なくとも小集団の中ではいじめは周知です。
しかし、その小集団から外にいじめの事実が発信されるのかというと、ここが引っかかるところです。
いじめが発生している集団内でいじめの対象となっていない人は、いじめの現場を見せつけられているので「いじめ加害者を敵に回すのはマズイ」という思考になりがちです。
いじめ加害者からすると、いじめをすることで、小集団内で自分の地位が向上し、いじめによる優越感を感じ、周囲からのいじめ告発の抑止力にもなってしまいます。
いじめ被害者も恐怖で支配されれば告発をしなくなります。いじめ加害者からすると、発覚のリスクは低く見積もられることでしょう。
いじめ加害者要因で、世間的にいじめが発覚する事例としては、刑事事件になるレベルまでいってから、という事例も珍しくない気がします。
いじめ被害者やパワハラ被害者が自から命を断ってしまった…というニュースで見るのは非常に痛ましいです…
加害者要因でいじめが発覚するような状況は、手遅れのケースも少なくないです…
被害者視点
いじめ被害者自身からのいじめの告発は、いじめ発覚の大きな一歩です。
問題はこの一歩が非常に重いということ。
繰り返しになってしまいますが、いじめ被害者はいじめ加害者によって精神的に恐怖で支配されていることが多いです。いじめのエスカレートを恐れて、下手な行動が取れなくなってしまっています。
また、すでにいじめがエスカレートしている段階になると、正常は判断力は失われ、無気力になってしまい、いじめから逃れるための手段として周囲を動かす(告発を含む)よりも、命を断つ方がハードルが低くなってしまうほどになってしまいます。
とはいえ、いじめ被害者からの告発は、いじめを止める手段として重要です。周囲がいじめ問題に対して積極的に取り組んでくれることが前提になります。
その上で、告発のハードルを下げる手段を用意してあげる必要があります。
現状では、周囲の協力を得ることが難しく、告発のハードルを下げる仕組みも不十分に感じます。
いじめ問題がニュースになった際、責任者が責任逃れやその場しのぎのような言動をしていると非常に残念な気持ちになります…
私がいじめ被害から脱したのは、被害者である私自身からの告発が決め手となったよ。
訴えた先の教師が真っ当な人であったことも幸運でしたね。
「誰に訴えるか?」は非常に重要なので見極めが必要になってしまうけど、精神的に本気で追い込まれる前に一歩を踏み出す勇気を持って!
「自らの命を断つ」という選択肢が脳裏に浮かび始めたら、もう精神的に限界の状態ですよ!
そうなる前に勇気の一歩を!
周囲視点
残念ながら、現状、周囲視点からはいじめ告発をするメリットがほぼ見受けられず、リスクしかないです。
周囲の立場から告発することがあるとしたら、自分の親しい友人がいじめられているような事例でしょう。
しかし、いじめのスタートは友人間のグループから始まったりするものです。
この場合、味方になってくれるような身近な周囲視点は最初からないです。自分の保身を考えれば、一緒になっていじめに参加する方が安全とさえ言えるでしょう。
昨今、自分の危険を顧みずに他人を助けてくれる人は少数派です。
いじめ問題だけではなく、今の世の中は人に関わるリスクを重く見る風潮がありますね。
人に無関心になることが珍しくない世の中…
深刻化しているいじめは、周囲からの助けで発覚するケースは少ないのではないかと思います…
周囲からの告発によるメリットがあればよいのだけどね。
パワハラの通報者には報奨金!とかあれば、周囲からの告発率は上がりそう?
それはそれで、痴漢冤罪のように告発者の立場を悪用する人も出てきそう…他の問題が発生するね。
うーん…結局、人の「モラル」が大事、という話に戻りますね…
管理者視点
管理者のような責任ある立場の人は、いじめの現場にいないことが大抵です。例えば、親だったり教師だったりがそうですね。
いじめの現場になるのは学校であれば休み時間であったりSNS上であったりするでしょう。そこに教師の目は届きません。
パワハラの事例だと、そもそも管理者にあたる人がいじめ加害者になるのですからどうにもなりません。さらに上位の管理者の目は届きにくい、というのはザラにあるでしょう。
ともあれ、大抵の組織や集団で、管理者のいじめ・パワハラに対する発見能力は低いといえるでしょう。
常に監視するようなことをすればいじめ発見率は上がりそうだけど、プライバシー問題やコストの問題もあり難しそうだね。
会社だと情報セキュリティの観点から、撮影・録音も自由にできませんしね。
- どの視点においても、いじめの検知度の点数は高い(発見率は低い)。
- いじめ発見率を高める方策を打ち出すことは重要な一手。
まとめ
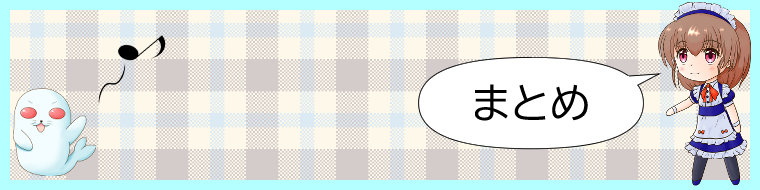
いじめ問題は、加害者、被害者だけを考えるのではなく、社会の仕組み自体を問題視する必要があります。
犯罪の取り締まりと同じです。
詐欺事件でも、だます方が悪い、だまされる方が悪い、という議論はあるでしょうが、そもそも詐欺をなくそうと思ったら、詐欺を考える人に「詐欺する事は損だ」という認識にさせる必要があります。
また、詐欺をしようと考える人の犯行理由を考えるとお金であることが多いでしょう。その視点で考えると、お金に不自由する世の中が悪い、ともいえます。
もっと雇用を安定させて生活水準が上がれば、そもそもリスクを負って詐欺をする必要自体がなくなります。
日本の場合、金融教育がなされず、お金の問題を抱える人が多い、という話も聞きます。お金に困らない生活をするための教育も詐欺を抑制する重要な手段となりえるのではないでしょうか。
いじめにしても、根本解決を図る必要を感じます。
これまで書いてきたことを最後にまとめましょう。
どの視点からみても、いじめはローリスク、実行しやすい、バレにくい、と見積もられてしまいがちです。当事者たちにとって、いじめはハイリスク、実行しにくい、バレやすい、と高く見積もらせる必要があります。その方針として何を考えるべきでしょうか?
- ルール(法律)の整備
いじめに対する処罰の厳格化
ルールを学ぶ(知らないルールは守られない) - いじめに対する知識教育
なにがいじめにあたるのか
いじめにあった、いじめを見た時の対処方法を学ぶ(無関心をなくす) - いじめに対するモラル教育(定期・継続)
いじめ被害事例(過去トラブル)を学ぶ
いじめ被害者の気持ちを知る - いじめ告発のハードルを下げる仕組み作り
匿名性のある告発窓口
告発者にとってメリットがある仕組み(悪用されない程度の告発報奨など) - 定期的ないじめ実態調査
匿名アンケート、見回り・聞き込みなど
会社では、徐々に○○ハラスメントに対する対策・仕組み作りが強化されていっています。問題が起きれば、社名を公表されてニュースになります。経営にも悪影響です。
定期的な○○ハラスメントについての教育が実施されたり、上司を通さず会社の対処部署に直通で告発メッセージを送れる仕組みができたり、環境は徐々によくなっているように感じます。
いじめ問題は現場レベルで根本解決は困難です。責任ある立場の人が対策に乗り出すことがいかに重要であるか。仕組みを作れる人が積極的に動いてくれることを望みます。