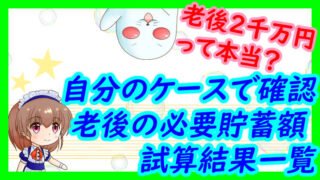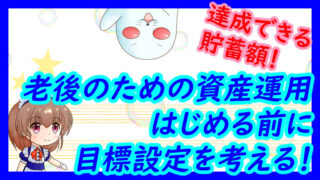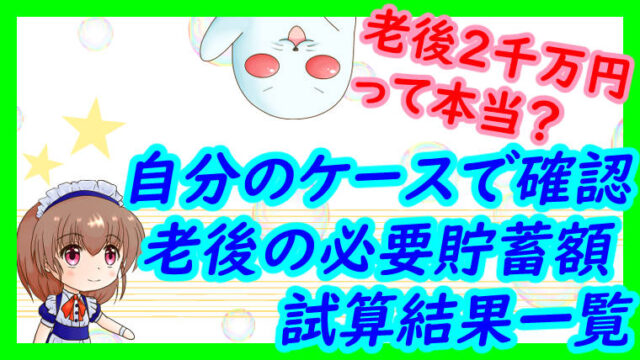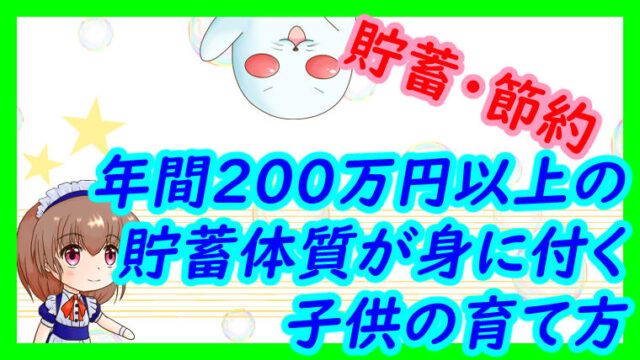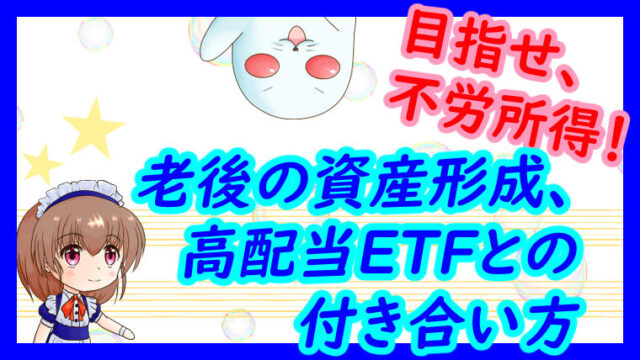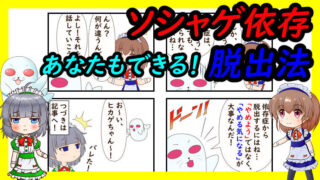老後リスクに対して、まず取り組むべきは何よりも家計簿をつけること!
家計簿は資産寿命を教えてくれます。これは、お金の面からみた自分の寿命にあたります。
この記事は、老後不安を解決したいけど、具体的になにをすればよいのか分からない、という人に役立つ内容です。
なぜ家計簿が大事なのか、先にポイントを押さえておきましょう。
家計の管理は基本ですね!
私は家計簿をつけるようになって、年間200万円まで貯蓄ペースを上げた!
- 今の生活レベルを維持するための毎月の支出を把握する。
⇒老後リスクを解決するための目標貯蓄額を出すのに必要。 - 収入と支出の両方を把握する。
⇒毎月の貯蓄可能額と老後の貯蓄寿命が分かる。 - 節約意識が高まる。
⇒収入と支出が数字として見えるようになるため、自然と収支を意識するようになる。
毎月の「収支の把握」「貯蓄可能額の把握」「自主的な節約意識」は老後リスクを解決するために必須!
お金を貯めたい人は、このまま記事を読んでみてね!
家計簿の必要性、家計簿のつけ方について学んでいきましょう!
家計簿をつけて、節約して、資産運用して…老後リスクを解決するための活動は一朝一夕ではできません。長期戦です。老後リスクと長く付き合っていくために、まずは自分事思考を身に付けましょう!
安易な気持ちで始めた活動は長続きしません。老後リスクを解決するための自分事思考を身に付けたい人は、こちらの記事をご覧ください。
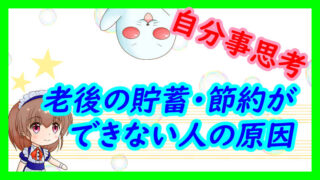
老後リスクに向けて、なぜ家計簿が必要なのか?
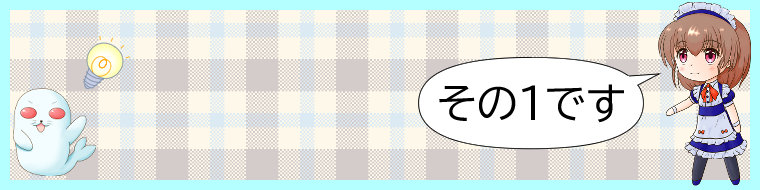
老後リスク…って何が不安になっているのか?
老後リスクに限らず、不安というものは「分からない」からこそ湧きあがる感情です。解決の仕方が分かっていて、それが自分にとって実行可能なのであれば不安にならないはずです。
人間、「分からない」が「怖い」のです。
「分からない」を「分かる」に変えるのが不安をなくすために必要なこと!
老後不安を「分かる」に変える手段が「家計簿」なのです!
「お化けが怖い」というのと同じでしょうか?お化けも理解できない存在だからこそ怖く感じるのですよね。
そうそう!老後リスクも解決できるのだと分かるようになれば怖くなくなるよ!
先に老後リスクの解決の道筋を確認しておこう!

「年金だけだと老後の生活には不足」と言われてるよね。老後リスクで一番怖いのは「お金が足りなくなること」だね。
年金で足りない分を「配当金」で補うのですね!
「年金+配当金>生活費」にできれば、長寿リスクも問題なし!老後に貯金が尽きる心配から解放される!
老後リスクの解決策は分かりましたけど、今回のお話の「家計簿」とはどうつながるんですか?
家計簿があれば現在の収支状況が分かるから、今後に必要な生活費や節約ポイントを見極めることができるんだよ。
生活費が分かれば「年金+配当金」をいくらにすればよいか目標が立てられるし、節約ができれば経済的自由達成のハードルが下げられるからね。
なるほど。「家計簿」の情報がないと、そもそも老後リスクの議論ができないのですね。
老後のための資産形成の目標立てには、「毎月いくら必要なのか?」「毎月いくら老後のために貯蓄できるのか?」という情報が必要です。
老後の生活費は人によって変わります。ネットで調べた平均値は参考にしかなりません。自分の場合はどうなのか?を確認することが大事です。
支出を把握する
お給料は誰もが気になりますよね?給料明細をチェックしている人は多いでしょうし、通帳を見ればすぐに今月の振込金額を確認することができます。
しかし、毎月の支出を把握できている人はわりといるのではないでしょうか?給料と違って一ヶ月の出費というと一目で分かりませんからね。
最近では、キャッシュレス決済も進んでいます。クレジットカードでも同様ですが、お財布の中身で現金が減っていく様が見えないことにより、お金を使っている感覚が薄くなり、ついつい使いすぎてしまう、という経験がある方もいるかもしれません。
家計簿をつけて、その上で家計簿を「チェックする」ことは、自分の支出を把握すると同時に、支出を意識するという観点からも重要です。
家計簿アプリで集計しているだけでチェックをしていないようだと、家計簿をつける意義は大きく損なわれてしまいます。
収入だけではなく、支出も把握しよう、ということだよ。
いくら稼いでも、同じだけ使っていたらいつまでたってもお金は貯まりませんもんね。
だから、収入と支出の両方を管理して、収支がいくらなのかを把握するのが大事なんだ。
黒字なのか赤字なのか、大きな分岐点ですもんね。
漠然とした黒字・赤字ではなく、数字でいくら黒字・赤字なのかを把握しようね。
貯蓄可能額を把握する
収入と支出を把握できれば、貯蓄可能額は分かりますね。ここは単純です!
もしも収支がマイナスになるようであれば、すぐに自分の家計状況の改善に取り組んだ方がよいです。また、貯蓄に回すほどのお金が残らない場合も改善を考えることをオススメします。
家計状況の改善ってどうするの?って疑問が出るよね。
そうはいっても「今だって懸命に毎日を生きているんだ!改善の余地なんてない!」っていう人も多いのではないですか?
その通りだけど、話を聞くと「改善の余地あり」と思うケースもあるんだ。改善の方法を知らないだけだったりね。
節約術とかですね!?
方法のひとつだね。家計を改善しようと思ったら「収入を増やす」か「支出を抑える」しかない。
「収入を増やす」というのはサラリーマンだと容易ではないのでは…「支出を抑える」方がすぐにできそうですね。
サラリーマンも副業がやりやすくなったし、資産運用も考えれば「収入を増やす」のもやる気の問題かもね。
まずは取り組みやすい「節約」から考えたいですね。
節約意識を高める
家計簿の大きなメリットは、支出と収入が見える化することです。家計簿を自分で付けることによって、自然と家計簿の収入・支出の数字を意識するようになります。
毎月赤字であれば不安になるし、黒字になれば安心するでしょう。「このままで大丈夫」という意識がある限り、人間なかなか改善には動かないものです。節約を始めるために必要なのは「このままではマズイ」という意識です。
老後不安を解決するために必要な毎月の貯蓄額まで考慮すると、毎月黒字だから大丈夫、というのも通用しないかもしれません。
自分の財政状況は定年後まで見据えて大丈夫なのか?問題があれば節約を始めた改善に踏み出すべきです。
家計状況について危機感を数字で知らせてくれる家計簿の存在は大きいのです。
経験的に手作業で家計簿をつけることで収支を非常に意識するようになったんだよね。
それが節約意識につながったんですね。
本来は収支を管理するための家計簿だけど、もしかしたら節約意識を強める効果の方が大事かもしれないね。
ポイントまとめ
- 毎月の支出情報(生活費)
⇒老後生活に必要な目標貯蓄額を計算。 - 毎月の貯蓄可能額
⇒老後生活に必要な目標貯蓄額を達成できるかの試算に使用。
家計簿の情報があれば、老後不安解決のための計画を立てられる!
目標達成が困難な見通しであれば、節約を考え貯蓄額を増やす検討が必要!
節約を考える基になるのも家計簿の情報!
私は実際に家計簿をつけるようになってから、節約意識が高まり続けて貯蓄速度が確実にアップしましたね!
年間100万円貯蓄が200万円にまで増えたって言ってましたね!
節約の効果は偉大だよ!
とりあえず、家計簿から得られる情報を改めて整理しておこう。
記事の最初に見せた図をチェックしてみましょう。

60歳定年プランのうち、「60歳(定年)まで」の「給与=生活費+投資+貯金」のすべてが家計簿から数字で分かるんだね。
老後のマネープランに家計簿が必須というのは分かった気がします!
家計簿の付け方
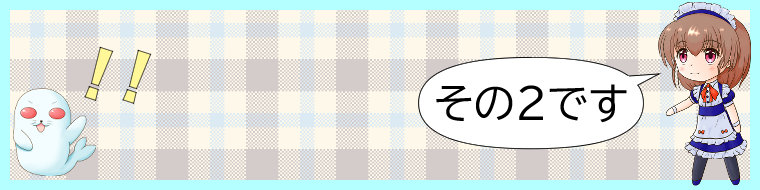
家計簿は単につけるだけでは意味がないです。家計簿は自分の収支バランスを知るためのツールであって、家計簿はつけた後に「見る」ことが大事です。
家計簿を見るのは自分です。自分にとって見やすくて分かりやすい家計簿をつけましょう。…といっても、付け方の方針は必要ですよね。家計簿をつける際のポイントを見ていきましょう。
- 毎月の収入が分かること
- 毎月の出費が分かること
- 節約を検討する際に分かりやすくカテゴリー分けされていること
- 月ごとにまとめて、年ごとに集計すること
「①毎月の収入」は特に考えることはないですね。「②毎月の出費」については次の「③カテゴリー分け」が大事になります。「④月ごと、年ごとに集計」も少し補足が必要なので、以下で③④について少し詳しく書いていきます。
家計簿で把握したい「給与=生活費+投資+貯金」のうち、「①が給与」「②~④が生活費」を出すためのものだね!
「投資+貯金」の部分は給与と生活費が出れば自動的に計算できますね!
③のカテゴリー分けは節約を考えやすくするための作業だよ!
節約を検討するためのカテゴリー分け
家計簿を見直しする時には、どこが節約できるポイントなのかを見極めなければなりません。よって、出費の種類を大まかにカテゴリー分けをして考えると良いでしょう。
最低限、次の方針でカテゴリー分けにすることを推奨します。この作業があとで節約を考える助けになります。
なぜなら、このカテゴリー分けにより、節約の優先順位がつけられるようになるからです。
- 生活上必須な消耗品の出費:食費、生活必需品など
- 生活上必須ではない出費:趣味、交遊費など
- 生活上必須な固定費:家賃、スマホ代など
- その他(突発的な一時金):医療費など
この大きな3つの切り分けを意識しつつ、後は自分に合った具体的なカテゴリーを当てはめていくのがよいです。私が実際に使っている家計簿のカテゴリー分けを一例として示しておきます。
- 食費
- 交通費(公共交通機関)
- 雑貨・生活用品
- 趣味
- 交遊費
- 家(家賃など)
- 公共料金(電気・ガス・水道・携帯代など)
- 保険代
- その他(通院費など)
- 投資
私はエクセルで家計簿を自作しているけど、アプリとかを使うのでもよいと思うよ!
かなり昔からエクセルでやってるから、今さらアプリにも切り替えにくいんですよね…
まあ、エクセルは手作業間あって、家計簿の数字を意識しやすくなるっていうメリットがあるんだよ!?
まあそういうことにしておきましょう。エクセルは自由度高いというのもありますしね。
ちなみに、カテゴリー分けの項目名は自由だよ!自分にあった項目を作ろう!
節約の切り口
節約については別途詳しく記事を作っていきます。ここでは簡単に触れるに留めておきます。
まず単純にどのカテゴリーでの出費が一番高いのか?それが見えるようになります。数字で見えるようになったことで、自らが「ここ、お金使いすぎなのでは?」と意識できるようになります。これが節約の切り口になるのです。
節約をしようと思っても、そもそも「お金を使いすぎている」という感覚を実感できない限り、節約しようという発想になりません!ここは非常に重要です。
次に、カテゴリー分けをした中で「生活に必須、生活に必須でない、毎月固定の出費」というのが見えてきているはずです。これはお金を使いすぎているカテゴリーとは別の視点で、「無駄使いがどれだけあるのか」を数字で見せてくれます。
- 生活に必須の出費:適切な出費(生活レベルを落とさない限りは下がらない)
- 生活に必須でない出費:贅沢にあたる出費 ※削減ポイント
- 毎月固定の出費:無駄が含まれているかもしれない出費 ※削減ポイント
「生活に必須でない出費」には、趣味や飲み会などにかけるお金が含まれます。ただ、趣味の出費などを削っていては生活自体が楽しくありません。無理をした節約は長続きしません。
そのため、まず自分自身が節約の必要性を強く認識することが節約の必須条件です。よって、自分自身で「使いすぎちゃったな」と思わない範囲までは無理して削らなくてよいと私は思います。
繰り返しになりますが、数字を見て、自分で節約意識を高めるのが家計簿の役割です。数字を見ても適切な出費だと考えられるのであれば、それは適切なのでしょう。
次に「毎月固定の出費」についてですが、これは本当に無駄なお金が含まれている可能性があります。そして、毎月固定の出費は、手間はかかるものの一度見直してしまえば普段の生活を送るだけで毎月節約が達成できる部分です。
最近では、スマホのプラン見直しなどがそうですね。他に大きなところとしては生命保険などです。家計簿をみて、一番初めにメスを入れるべき場所はこの領域でしょう。
まあ、私は趣味にお金を費やすために食費を真っ先に削っていた時代もありますけどね!w
(ソシャゲにハマっていた時代があった…)
ソシャゲのガチャは闇…
まあ、真面目なところで、保険とスマホ(通信費)の見直しは効果大でしたね。
心配性だから特に保険加入は過剰でしたもんね。万単位で出費が変わりましたね!
あとは、買うかどうか迷った時に「買わない後悔よりも買う後悔」という精神は吹き飛んだね。
「今だけセール」とかに弱いですもんね~。買い逃したら「節約できた」くらいのプラス思考でいきましょう!
買い物の前に「これは本当に必要なものかどうか」と一日くらい自問自答するようになるだけでも、無駄な買い物は結構減るね!
毎月、毎年の集計をする
節約の観点では、出費のカテゴリー分けが必要でした。家計簿の他の用途として、老後のマネープランを立てることにも使います。
老後のマネープランに必要なものはなんでしょう?
それは、毎年の収入と毎年の出費です。毎月の集計は小計として実施して、毎月、自分の生活費を見直すことに使えますが、基本的には月ごとに収支はバラツキが発生するものです。季節柄のバラツキもあれば、ボーナスや残業時間によって収入だって月ごとにバラツクでしょう。そのため、老後のマネープランを考える際には、年単位での収支を考えます。
よって、家計簿は最低限、1年以上はつけてほしいですし、基本的には半永久的につけていくことをオススメします。お金という数字を意識しなくなったら、マネープランはあっという間に破綻しますからね…自分のお金を管理するのは自分自身です!
収入と支出のバランスが大事だよ!
収入と支出の把握は、毎月いくら貯蓄する能力があるのかの確認にも大事ですね!
老後リスクを解決するための貯蓄計画の立て方
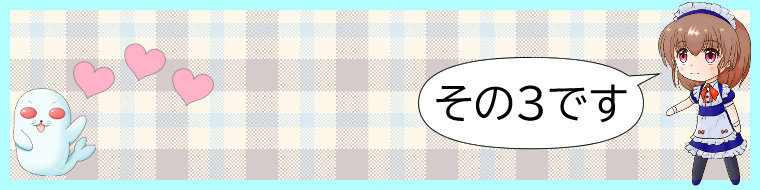
家計簿をつけることにより、毎年の収入、支出が把握できるようになりましたね。カテゴリー分けをしたことで、老後には不要になる項目もある程度切り分けできるかと思います。その結果、今の自分の生活における貯蓄能力と老後の支出予測が立てられるはずです。
実際には毎年のインフレも考慮して計算しなければなりませんが、おおよそ、以下の内容が家計簿から読み取れます。
- 老後の毎年の生活費
- 定年までに貯蓄できる金額
上記2つの数字から、「何歳まで貯蓄がもつのか(貯蓄寿命)」が分かる。
この「何歳まで貯蓄がもつのか」というのはある意味で残酷な数字です。自分の貯蓄状況が寿命みたいなものです。「あなたは何歳までしか生活できません」と言われるに等しいです。
それゆえに、この数字を計算すると今の生活を続けていて大丈夫なのか?と不安がより現実的なものに見えてきて怖くなってきます。
しかし、それでよいのです。
漠然とした不安を現実的な不安として感じるようになるのは、老後不安を解決するために必要な気持ちです。老後不安を解決するための活動は長期間かけておこなうものです。必要性を実感せずに継続するのは人間の心情的に無理というものでしょう。
そして、現実的な不安に感じるからこそ、「節約」という言葉の重みが変わるはずです。
「変わろう!」と思った時が新たなスタート!
現実的に解決できる計画を立てられれば不安もなくなるよ!
詳しくは別記事でご説明します!
かるく復習しておくと、現役時代に節約しながら貯蓄(投資+貯金)をして、老後は年金+配当金で経済的自由を獲得だよ!
かなり早期に投資活動していればFIREも見えてきそうだけど、あまりリスク取らずに40代からの投資活動開始だと、このプランがやっぱり無難ですかね…

正直、できる限り早く会社辞めたいけどね…あまりリスクを負いたくない人が実行するプランとしては無難だと思うよ。
定年延長とか嫌ですよね~…60歳で引退がせめてもの抵抗!
まとめ:目標貯蓄額を達成するために
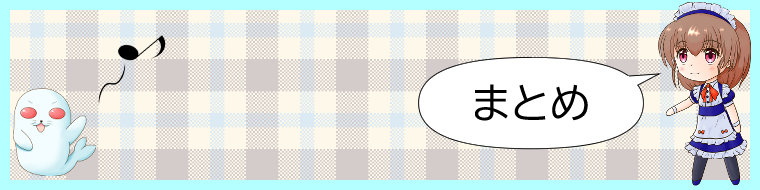
「あなたは何歳まで生きたいですか?」これにより、目標貯蓄額も異なってきます。
「Die with zero」という本もありますね。死ぬ時に資産ゼロ、というのは数字上は理想的です。使わない資産のために無駄な時間と努力を割いて貯蓄した、なんて人生の無駄ですよね。
ただ、私は減っていく資産に怯えながら人生を生きるのは嫌です。精神的に参ってしまいそうです。自分が何歳まで生きるかなんて分かりませんからね。計画した以上に長生きしたら資産が底を突いて困ってしまうことでしょう。
また、資産で寿命が決まるのも好きではありません。これまで伝えてきたことをひっくり返すようなことをになってしまいますが、「出費<収入」の状態を維持できれば資産は減りません。定年後だからといって、貯蓄を毎年削っていくしかない、なんてことはないはずです。
この考えについても別の記事で書いていきます。ともあれ、老後リスクに立ち向かうにあたり、何をするにも家計簿は土台になります。自分の財政状況を把握していない人は、ぜひ家計簿をつけるようにしていきましょう!
投資活動が出遅れた40代のサラリーマンの方々でFIREが現実的ではなかったとしても!
60歳で経済的自由を得て引退はできる!
定年延長に流されない強い意志!
老後の資産形成が間に合わない場合は、仕方なく定年延長を受け入れるしかなくなっちゃいますからね…
できるかぎり早く!むしろ「今」!老後リスクについて動き出すべし!