自分の子供が将来お金に困らないような教育をしたい。
無駄使いをしない、節約・貯蓄ができるような子供に育てたい。
そんなことを求めている人に役立つ記事です!
実体験って…子育てなんてしたことないですよね?独身じゃないですか!
実体験で間違いないよ!まあ、子育てされた側だけどね!w
騙されたような気はしますけど、確かに実体験ですね…
はい!私自身、貯蓄・節約体質が染みついてしまっている人です。つまり、この記事では私の子供時代に親から受けた教育の実体験を伝えていくよ!
社会人になってから年間100万円貯蓄。今では年間200万円以上貯蓄!でしたね。
貯蓄、節約の考えが根付いているのは、親からの教育の賜物だよ。私が受けたその教育方法を紹介していくよ!
- お金の大切さが身に付くおこづかい制度
- 人生を変えた子供時代の習い事
- 学び続ける精神の育て方
- 時に親は反面教師
端的にまとめると、小さいころから「自分のお金の管理」「自分の努力でお金を得る」ことを学びました。
詳しくは記事の中で説明します。
貯蓄・節約体質の基盤になっている親から学んだこと
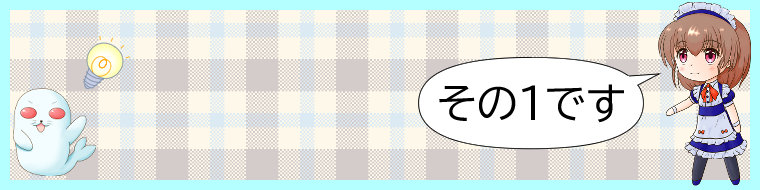
先に貯蓄・節約が身に付いたと感じるポイントを挙げておきます。誰でも思いつくポイントではあるけど、貯蓄・節約力に差が出るのはこれらポイントが身に染みているかどうかでしょう。
- 物を購入するとき、それが本当に必要かどうかを考える。衝動買いしない。
- お金の管理は自分でする。
- お金は労力の結果得られるものである。容易に手にしたお金は容易に出ていく。
- 学ぶことを怠らない。
- 「今」を重視しすぎない。未来も考慮しながら今を生きる。
- お金については自分で考え動く。基本的に他人を頼りにしない。
ポイントは容易に思いつく内容だし、割とすんなりと納得できることではないでしょうか?
だけど、これを実践できるかどうか、それは子供時代の経験に強く左右されるのではないかと思います。子供時代に得た学びというのは、大人になっても自分自身を構築するピースになっていますよね。
子供時代の経験って本当に大事!
子供時代に身に付いたものって一生ものですよね~。
子供時代に学んで習慣化したことって、大人になっても無理せずできてしまうというのは強みだろうね。
子供時代に身に付いた習慣というのは、確かに意識せずとも続いてたりするかも…
子供時代の「習慣化」も大事だし、「体験」することも大事だね!
子供のころから「お金の管理」「お金を稼ぐ」の体験をしてるのは、確かに珍しいのかも…
人生一度だけ…無駄使いを怒られた幼少時代の事件
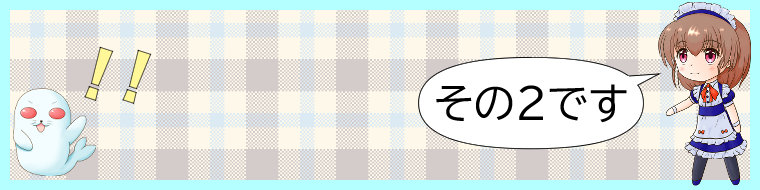
お金について私が一番最初に学んだ体験というのは、思い出せる限りではこの事件。小学校低学年の頃でした。
あれは、家族で買い物に行く、といった日に私が「行きたくない!」とダダをこねて、友達と遊びに行ってしまった時のお話。
一緒に遊んでいた友達は、今思うとそこそこお金に余裕がある家庭だったのかと思います。子供のおもちゃが売っているような駄菓子屋が大きくなったようなお店で、玩具のピストルが売っていたんですね。子供の玩具なのにちょっとした火薬を仕込むもので、撃つと「パンッ」と音と煙が出るものでした。お値段、たしか1000円だったか…
私はその頃からおこづかいをもらっていたので、その時の手持ちをすべて出せば買える、という価格でした。そして一緒にいた友達が買ったことから、私も一緒に同じ物を買ってしまいました。
この買い物が、後から凄い勢いで親に怒られたのです!
小学校低学年でしたからね。1000円は大金です。その大金を一回の買い物で使ってしまうのは親としては本意でない使われ方だったことでしょう。
まあ、与えてもらったおづかいを即座に使ってしまうなんて、今思えばとんでもない浪費のしかたですw
今思うと、私の人生で一番最初に起きたお金に関する事件だったかな。
こういう人生における事件的な体験って大人になっても絶対忘れませんよね。
忘れないからこそ、やっぱり「実際に体験する」っていうのは大事なんだと思うよ。
たまに怒られるようなことがると、印象に強く残りますね…嫌な事ではあるけど、ポジティブに考えるなら人生の経験を確実に積んだということでしょうか。
まあ、怒られたことを真摯に受け取れられればだけどね。怒られたことを聞き流すようだと記憶に残らないからね。叱る方も相手が納得できるような𠮟り方をする事が大事だよね。
お金の管理は自己責任!貯めるも使うのも自分で計画的に。
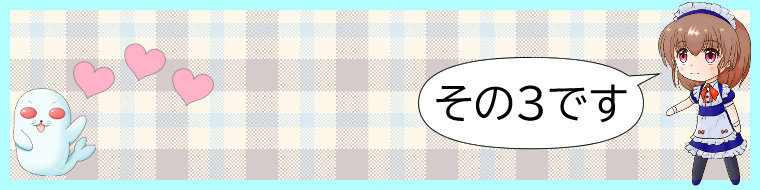
私はすっかり「貯蓄」の体質が身についていました。幼少期のお年玉は親が預かる、という家庭の話も聞いたことありましす。しかし親の方針だったのか、私の家庭では小学校低学年のころからお金は自己管理でした。
何が欲しいのか?欲しい物を買うためには何を我慢する必要があるのか?そういうのを考えながら貯蓄するようになるのは自然なことでしたね。
「貯蓄」して「計画的」にお金を使う、というのを実体験で学んでいったのはこうした環境によるものです。私にとっては自然なことでしたが、今思うと小学校低学年からこんなこと考えているのは珍しいのでは?w
私はゲームが好きだったのですが、ゲームのハードをおこづかいとお年玉を貯めて自分のお金で買うのは多分少数派だったと思います!w ふつうは誕生日プレゼントとかでもらうものなんだろうなぁ…
自分のお金は自分で管理する、というのは非常に大きな経験だったね。
小学校低学年から自分のお金を持って、それを自分で管理するのは珍しいのかもしれないですね。
「貯める」「我慢する」「計画通りに欲しい物を手に入れる」という子供の頃の体験は、すごいよい経験だったと思うよ!
これもまさに「実際の体験は最大の学び」ですね!
あとは、欲しいものは自分で買うという考えができてたから、「親に何かを買ってもらう」という思考は他の子より弱かったように思うよ。
それはそれで子供らしくないような…w
お金はタダで手に入るものではない!幼少時代のおこづかい制度
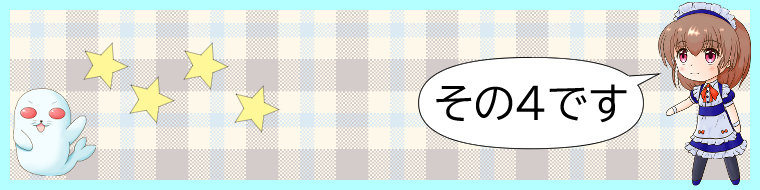
いろいろな家庭の事情は分からないけれど、幼少時代のうちの家庭では、おこづかいは毎月もらえる分とお手伝いでもらえる分(お駄賃)がありました。
頻度は多くなかったけど、親が「手伝ってほしい」と言った時はお駄賃チャンス!w それだけで積極的にお手伝いする子供のできあがりですね!w
とはいえ、これにはメリットとデメリットがあると思いますね。
【メリット】
- 「労働=お金」という思考が身に付く。
- 苦労してお金を入手する経験を積む分、お金を大事に使うようになる。
- 人のお手伝いすることに積極的になる。
【デメリット】
- 何かとお金に結びつけて思考しがちになる。がめつくなる。
- タダ働きを嫌うようになる。
「毎月無償でもらえるおこづかい」だけだと、「お金は何もすることなくもらえるもの」という思考が育ってしまうのが欠点。
お金は親から湧いてくるもの、という思考に染まると、大人になってからヤバいですね…
大抵は学生時代にバイトを通じて「労働=お金」に結びつくのだろうけど、私の場合はそれが子供のころに小規模ながら体験されられてたって感じだね。
何にしてもお金についての教育を受けるのが早かったんですね~。
でもまあ、子供の頃に「老後=お金」が強く結びついてしまうと、お金がないと何も手伝わない子供になりかねないから注意は必要かもしれないね。
「おこづかい付きのお手伝いの頻度」というのはたまくらいが良いのかもしれないですね。
こんな注意を書いてるのは…私自身が若干お金にがめつい方だからだよ!w
他人よりも少し損得勘定をしがちなところはありますよね…
損得勘定は、メリットもデメリットもあるから必ずしも良い癖とはいえないね…
人生に大きな影響を与えた子供時代の習い事
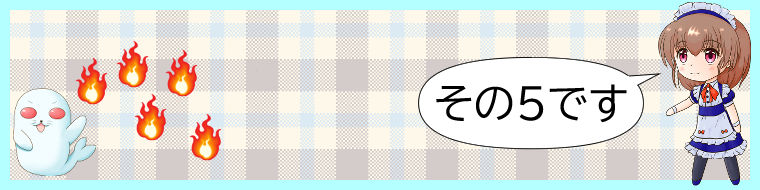
子供に習い事をさせよう、という教育熱心な親は多いのではないでしょうか?
私は幼いころ、幸いなことに親に習い事をさせてもらっていました。
私が小学校の頃にやっていた習い事は「そろばん」です。
この習い事は私の人生に大きな影響を与えてくれました。そろばんがあったから今の私がいるといっても過言ではないです。というのも、数字に強くなって算数・数学が得意になったのは「そろばん」のおかげでした。
そして、結果的に私は理系人間になりました。世の中、数字に強いと便利な場面は多々あります。確率計算とか統計的な考えとか…単純に数字とにらめっこするにしても、考えが一歩深くなる傾向があります。世の中、数字で動いていることが多いのですよね。
一方で、文系分野にしても世の中に役立つこと、生活を豊かにしてくれる知識は豊富なんですよね…私は得意な分野ではありませんが、法律などを始めとして、世の中知らなくて損することがいかに多いことか…
あと、子供の頃には重要視していなかった社会科や歴史!数学や物理などに比べると理系職業を目指していた私にとって、将来なんの役に立つのかと思った科目ですが、今思うと世の中を知ることが社会で生きるための基礎なのですよね。
知識があれば、選択肢が増える。知識がないとそもそも選択肢が浮かばないなんてことも!結局、理系にしても文系にしても、学びの対象はなんであれ大切!
ともあれ、私の場合、今の仕事は理系であることでつながった道だし、「そろばん」は私にとっては人生において有益な習い事でした。
どんな習い事がよいか、というよりは、学ぶ大切さを子供の頃に知って「得意」を作るのが大事といった感じでしょうか。
私は習い事がキッカケで、理系科目が得意になったんだよね。得意が好きに変わるのにそれほど時間もかからなかった記憶だよ。
子供のころに「得意科目」といえるものができるのは、勉強を嫌いにならない大事な要素なのかもしれませんね!
どんな分野であっても、「得意」を作って「人に教えられる」くらいになると、物の考え方も変わるよ。人に聞くのではなく自分で考えるようになる、というのは人生においてすごく大事な癖だと思うよ。
学びはお金になる!学生時代のおこづかい制度
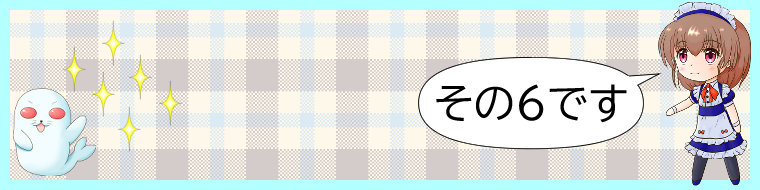
中学校~高校時代、おこづかい制度が変わりました。テストの点数でボーナスが出るようになったのです!ふつうの子供なら学校のテストなんて嫌いでしょう。しかし、私にとっては稼ぎ時でチャンスでした!
対象のテストは中間・期末テスト。小テストとかは対象外でした。そしておこづかいのボーナスのレートはこんな感じでした。ちなみに、対象教科はすべてです。
- 80点以上:500円
- 90点以上:1000円
- 1000点:3000円
このおこづかい制度になってから、私は勉強を必至でがんばった!w
自分でがめつくなったというだけはありますね…w 完全にお金に釣られてますよw
当時、親はそんなにおこづかいを出ことになるとは思ってなかっただろうなぁ…w
中学校2年生くらいで成績が跳ね上がって、2年の後半くらいから学年トップになってました。この学年トップは大学院修士までずっと維持してました。まあ、私はランクの高い学校に行っていたわけではないからこそ取れたトップでしたけどね。
ともあれ、お金の大切さを学び、貯蓄を好むように育った私にとって、おこづかい付きのテストは完全にボーナスでした!
労働ではないけど、努力がお金に結びつく、というのがもう自然な感覚になっていたし、自主的に勉強することが自然になっていっていました。
このおこづかい制度は高校で終了だったのですが、大学に入ってからも勉強の習慣は消えないままでしたね。親にとってはテストが来るたびに想定外の出費だっただろうけど、勉強習慣を率先して身に付けさせてくれた親には感謝ですね。親から勉強しなさい、と言われた記憶が全然ありませんw
学ぶことは大事な自己投資!
私自身はおこづかいを通じて「学ぶことがお金になる」という思考で当時、勉強をがんばったけど、必ずしも健全な方法ではないかもしれない。ただ、お金が努力の先にあるものだ、というのを実体験させるのには有効だったとは思う。
お金の話はおいておき、自主的に学ぶように仕向けるためには、正攻法は「勉強の必要性を説くこと」だとは思います。
大抵の場合、役に立つかどうか分からないことを学ぶのは苦痛ですよね。しかし、役に立つと分かっていることは、誰かに言われずとも自ら進んで学ぶもの。
子供的な例を挙げるのであれば、ゲームに詰まった時にゲームの攻略を調べるのと同じ行為ですね。必要性を感じれば、自ら調べようとするのですね。
まあ話を戻して、キッカケはお金だったけど、学ぶ習慣がついたのは人生において大きな財産になったと思うよ。
あれ?元々の話は「貯蓄癖が身に付く子供時代の教育方法」じゃないでしたっけ?
それについては、「努力がお金につながる」を実体験できたという点で間違ってはないかな。
そして、努力の末に手に入れたお金は手離れしにくいですしね。
「悪銭身に付かず」とは逆に、お金を努力で得た経験は貯蓄体質につながるとも思うね。
それど同時に「学ぶ習慣」は人生の財産になるなら、お金にとって一石二鳥!?
人生の転換期…頼るべきは自分自身!
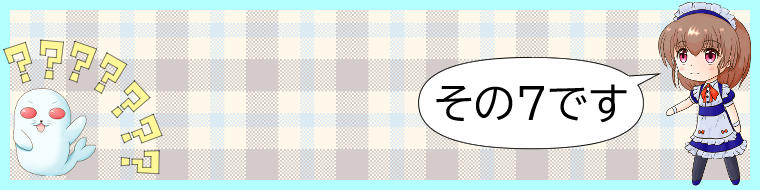
大学2年の時、人生に大きな影響を与えることとなる事件が起きました。父親の他界です。
これまで書いてきたお金に関する教育は、父親によるものです。当時、家庭の経済状況はほぼ教えてもらうことができなかったけれど、用意周到な父親は生命保険にもしっかり入っていて、さすがだな、と感じたものです。
私の学費もけっこうなものだったと思うけど、生命保険のおかげで大学院修士卒まで通わせてもらえましたしね。これまでの勉強の成果のおかげで返済不要の奨学金がもらえたのも助かりました。
お金に関して以外でも父親からの教育は身に刻まれています。例を挙げると…
- 自分が嫌なことは人にもするな
- 分からないことがあったら調べる癖を付けろ
- 食べ物は残すな
これらは他では聞かない特別なことではないけれど、どれも大事なことですよね。
思い返すと、お金に関しての教育もまだまだいろいろありましたね。お金の貸し借りの危うさとか…
物を大事にする、無駄にしない、という点でも食べ物については特に厳しかった。自分に取り分けた食べ物を残すと激しく怒られた記憶があります。必要以上に手を付けない、というのもこうした環境で自然に身に付いたのでしょうね。
子供のころの教育って勉強以外もすごい大事ですよね。
まさに「人生の生き方の基本は子供の頃に形成」されるといった感じだね。
自分が成長する環境とは?
父親がいろいろな面で優秀であった分、母親はいろいろ社会的なことが苦手な人です。優秀な人が近くにいて頼れる環境だと自分は育たないからね…母親が社会的な事柄でいろいろなことができないのは必然だったのかもしれない。
いまさらながら、私には姉もいましたが、姉もどちらかというと母親寄りで頼りにするには弱々しいタイプでした。
反面教師…というと言葉が悪いけれど、周りに頼れる人がいない環境と言うのは、自分でどうにかしなければならないから、必死にもなるし色々必要性が高まって学ぶものです。
人任せにしない、自分がやる!
この精神は自身の成長において非常に大事!もしかしたら、周囲に優秀な人がいる環境は一長一短なのかもしれませんね。
向上心が強い人にとっては身近に優秀な人がいるのは良い環境でしょう。しかし、人に頼る癖がある人にとっては身近に優秀な人がいるのは不幸な環境かもしれません。なぜなら、学ぶ機会を手放してしまっているからです。
周囲に頼れる人がいても、まずは自分で考える・調べる、それでも分からない時に人に頼る、この流れが大事ですね。
周囲に頼れる人がいるのは凄い助かるけれど、頼りっぱなしだと自分の成長にはつながりませんね。
人に頼らず、自分で考え自分で動く。学ぶ、という点について、自立思考は大事。
その上でまだ困ったり解決しなかったりするようなら、人に頼るというのはもちろんアリですね!
自分のことを他人任せにしない、という前提の下、助けを求めるのはもちろんOK!
自分で考える…自立思考って、前にやった自分事思考とも似てそうですね。
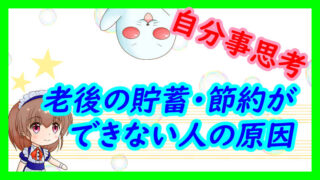
自立思考ができないことによる弊害
自分で考えることができず、自分で行動できない人はどうなってしまうのか?
私にとってこの答は身近な存在から学ぶことができます。父親に頼り過ぎていた我が家族です。どうなってしまうのか見てみましょう。
- お金の管理ができない、しない。
家計簿をつけようともせず、収支計算ができない。結果として、お金をどんどん使ってしまう。貯蓄にまったく向かない。 - 先を見通すことができない。今だけを重視して考える。
将来に向けた貯蓄にまったく興味がない。
「今」を変えたくないから新しいことをしようとしない。
新しいことを学ぼうとしない。 - 物事の判断ができない。判断基準が他の人。
「他の人はこうだから大丈夫」「他の人がやってるからやった方がいい」という思考で、自分で考えて判断することができなくなってしまっている。かんたんに人に流されてしまう。
ひとことでまとめるなら「停滞」だね。人は新しいことを学んで体験して成長するんだ。これはいくら年を取ったとしても学び続ける限り人は成長できる!
とはいっても、新しいことを始める怖さはありますよね…世の中保守的な人はいっぱいいますし。
早くも「他の人」に思考がひっぱられてるよ!?
ハッ!?ついつい楽な方向に考えが流されてしまうのは人間の特性でしょうか…「変わらない」ことは楽ですからね。
もちろん、守るべきものがあっても良いとは思うよ。だけど「改善できる点」を考え続けるのは大事だよ!
周囲に頼れる人がいないことを自覚したことで、私の自立思考精神は加速しました。しかし、根本的に自立思考は父親からの教育マインドにもあったんだと気づかされます。
それは子供のころから言われ続けた「分からないことがあったら調べる癖を付けろ」という言葉です。父は自分が教えられることでも「自分で調べろ」というスタンスでした。自分で動くという癖は子供の頃から学ばされていたんですね。
ちなみに、調べるための環境は十分与えられていました。幼少期から国語辞典、漢字辞典に始まり、図鑑とかもありました。
“なるべく”人に頼らないというのは、学びの最短ルートではなかったかもしれないけれど、自分で手を動かして学んだことは記憶に残りやすいのもメリットかもしれません。
まとめ
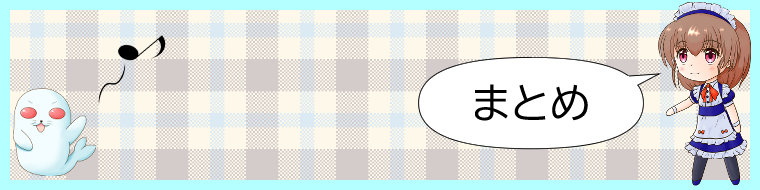
最後に要点をまとめます。子供の頃の体験は一生を左右しかねない大事な学びの時です。
- 「労力(努力)=お金」を実体験させる。
- 自主的に学ぶよう誘導する。学ぶことでプラスになる実体験をさせる。
私の体験ではテストでのおこづかいが餌だったけど、ベストは将来に向けて勉強の必要性を説くことかもしれないですね。役に立つか分からない物事を学ぶのは誰だって苦痛を感じますからね。 - お金を自分で管理させる。「貯蓄」「節約」「欲しい物を手に入れる」というプロセスを体験させる。
- 自立思考を身に付けさせる。まずは自分でやらせ、考える癖を付けさせる。すぐに答えを教えたり助け舟を出さない。
ここに書いたことは、あくまで私の実体験に基づくものです。しかし、誰にでも当てはまる一般的なことではないかもしれません。現に同じ環境で育った私と姉ではお金に関する考え方に大きな差があります。
ただ、私は父親寄りで姉は母親寄りであったことが、お金への考え方の差として出たのかもしれません。
ともあれ、この記事で書いていることは「絶対」のお話ではなく、あくまで「とあるひとりの体験談」です。その上で、参考になるところは参考にしてみるのもありかもしれません。
大事なのは「自立思考」!すべての情報を鵜呑みにせず、使う情報も収取選択です!
実際にこういう子供時代を経験してきた私は、貯蓄・節約の成果として、社会人になった初年度以降は毎年100万円以上の貯蓄を続けて、今では毎年200万円以上の貯蓄ができるまでになっています。
なんか、お金に関しては成功例のように聞こえますけど、失敗談とかないんですか?
もちろんあるよ!節約・貯蓄については強かったかもしれないけど、お金をうまく運用するという点では全然知識を持ってなかったからね…

本当、何事も勉強と体験ですね…
資産運用なんて危ないもの、という先入観があったからね。定期預金とか保険積立とかずいぶんもったいない時間を過ごしてしまったね。
どんな資産運用にしても、危ない面があるのは間違いではないのでしょうけど…
貯蓄・節約を身に付けたら、次は資産運用も勉強していこう!お金にとって時間は味方だよ!
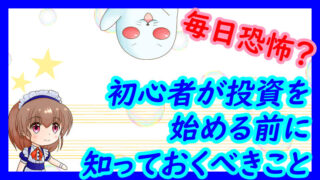



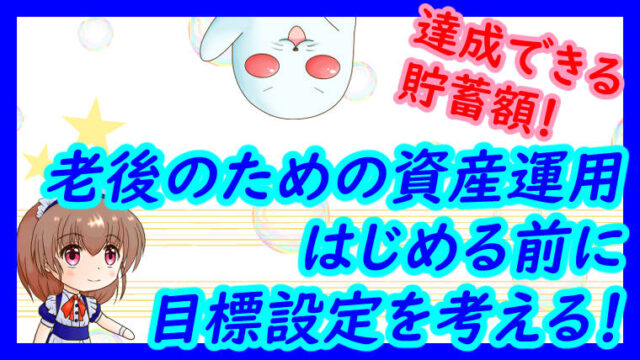
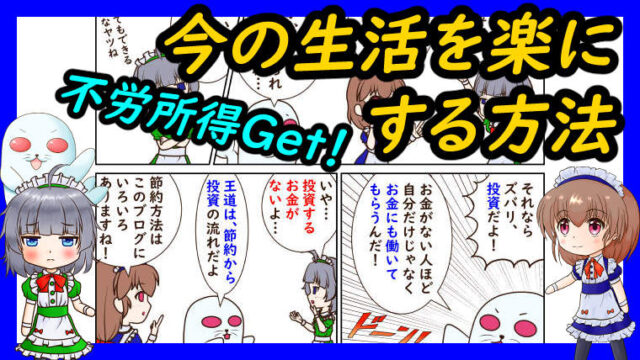
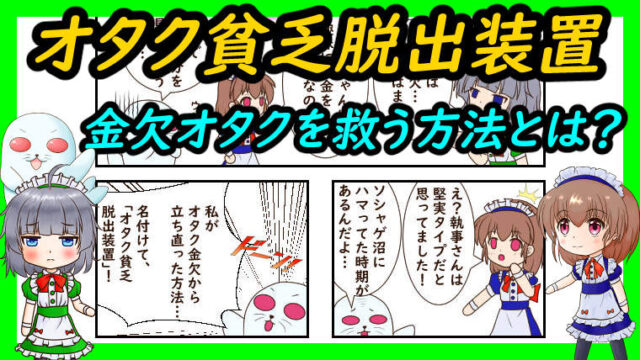


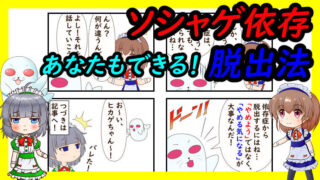




この体験は「無駄遣いをしない」「衝動買いしない」「お金は持ってるだけ使ってよいものではない」という戒めを与えてくれました。私にとってのお金に対する基本マインドですね。
当時は凄い泣いてしまった事件なのだけど、振り返ってみると怒ってくれた親に感謝ですね!